東京大学理系 Part 3
ホーム > Gno-let > Gno-let23 > 東京大学 理系 Part3
| 片山 鈴音さん(理Ⅰ・桜蔭) | 馬場 愛奈美さん(理Ⅱ・桜蔭) |
| 松田 竜さん(理Ⅱ・麻布) | |
■入塾のきっかけ
なぜグノーブルを選んだのでしょうか?
高1のときに受けた講習の明るい雰囲気に魅力を感じて、授業内容も「ここなら間違いない」と実感したからです
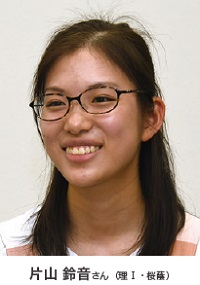
片山:
もともと英語は好きな科目だったので、塾でも嫌いにならず楽しんで学びたいと思っていました。
グノに決めたのは、高1のときに受けた講習の明るい雰囲気が魅力的だったのと、授業内容も「ここなら間違いない」と実感したからです。その時期は部活が忙しかったので継続受講は見送って入塾したのは高2の夏期講習からでした。
グノの英語は本当に楽しかったので、もっと早くから通えば良かったと感じています。
グノに決めたのは、高1のときに受けた講習の明るい雰囲気が魅力的だったのと、授業内容も「ここなら間違いない」と実感したからです。その時期は部活が忙しかったので継続受講は見送って入塾したのは高2の夏期講習からでした。
グノの英語は本当に楽しかったので、もっと早くから通えば良かったと感じています。
馬場:
私は片山さんより早くて、高1の春に英語と数学で入塾しました。
2つ年下の弟が中学受験グノーブルに通うことに決めたとき、母が説明会で代表の中山先生のお話を聞く機会があったんです。当時中2だった私は母からグノの良さを聞きました。中学生のうちはまだ入るつもりはありませんでしたが「入るならグノ」と思っていました。
高1の春まで塾には通っていなくて、そろそろ塾に入ろうと思ったとき、一番頭にあったグノの説明会に参加しました。一応、他塾も検討しましたが見学に行った塾の中ではグノが最も雰囲気が良かったので結局、予定通りグノにしました。
2つ年下の弟が中学受験グノーブルに通うことに決めたとき、母が説明会で代表の中山先生のお話を聞く機会があったんです。当時中2だった私は母からグノの良さを聞きました。中学生のうちはまだ入るつもりはありませんでしたが「入るならグノ」と思っていました。
高1の春まで塾には通っていなくて、そろそろ塾に入ろうと思ったとき、一番頭にあったグノの説明会に参加しました。一応、他塾も検討しましたが見学に行った塾の中ではグノが最も雰囲気が良かったので結局、予定通りグノにしました。
松田:
僕も馬場さんと同じで、高1の春から英語に通い始めました。
入塾するまで、僕はグノのことをあまり知りませんでした。麻布ではそもそも塾の話をあまりしませんし、当時はグノが話題になることはほとんどなかったからです。「みんなが通っている塾の方がいいのかな?」と思うことも最初はありました。
でも、がんばる人は伸びると考えて、塾の規模や実績ではなく雰囲気で選びました。そのうち、学年が上がるにつれて、グノに通う麻布生がどんどん増えていきました。
入塾するまで、僕はグノのことをあまり知りませんでした。麻布ではそもそも塾の話をあまりしませんし、当時はグノが話題になることはほとんどなかったからです。「みんなが通っている塾の方がいいのかな?」と思うことも最初はありました。
でも、がんばる人は伸びると考えて、塾の規模や実績ではなく雰囲気で選びました。そのうち、学年が上がるにつれて、グノに通う麻布生がどんどん増えていきました。
■グノーブルの授業
英語の授業はどんな雰囲気だったのか教えてください。
英文法の勉強が楽しいと思えるようになったのは、私の中では大きな変化でした。普通の受験勉強とはひと味もふた味も違っていました
片山:
他塾に通っている仲の良い子の話を聞いて、「グノとは全然違う」と思っていました。
他塾だと宿題の量も多いし、英単語の覚え方も、丸暗記をしないグノとは全然違いました。
他塾だと宿題の量も多いし、英単語の覚え方も、丸暗記をしないグノとは全然違いました。
松田:
グノの宿題は確かに他塾に比べると少ないと思います。文化祭関係が忙しかった時期でも、宿題の重圧がなくて、学校生活と両立できました。
グノは授業で演習した内容をその直後に解説を受けて理解します。それを復習で身につける復習中心の塾なので、ひたすら宿題をやっていくスタイルとは違って、気持ちの上でも負担が少なくて助かりました。
他塾の場合、別に集中していなくても時間が過ぎていくような授業が多く、僕は緊張感のある授業をほとんど受けたことがありませんでした。
それに対して、グノの授業には程よい緊張感がありました。緊張感といっても、生徒の自主性を抑えつける厳しさは全くありません。生徒が自分の頭を使って考えていくことを促すような雰囲気でした。
先生は生徒の意見を尊重してくださいますが、授業内で添削があるし、解説のときには先生と生徒がやり取りしながら進むので、それによって緊張感が保たれています。
とても刺激的で気持ち良く集中できる授業でした。
グノは授業で演習した内容をその直後に解説を受けて理解します。それを復習で身につける復習中心の塾なので、ひたすら宿題をやっていくスタイルとは違って、気持ちの上でも負担が少なくて助かりました。
他塾の場合、別に集中していなくても時間が過ぎていくような授業が多く、僕は緊張感のある授業をほとんど受けたことがありませんでした。
それに対して、グノの授業には程よい緊張感がありました。緊張感といっても、生徒の自主性を抑えつける厳しさは全くありません。生徒が自分の頭を使って考えていくことを促すような雰囲気でした。
先生は生徒の意見を尊重してくださいますが、授業内で添削があるし、解説のときには先生と生徒がやり取りしながら進むので、それによって緊張感が保たれています。
とても刺激的で気持ち良く集中できる授業でした。
片山:
毎週添削をしてもらえるのはとても良かったです。添削のおかげで気が緩むことなく、モチベーションを保てました。
それから、適語補充や並べ替え、間違い探しなど、いろいろな種類の文法問題を解けるので飽きることがありませんでした。
英文法の勉強が楽しいと思えるようになったのは、私の中では大きな変化でした。文法事項の成り立ちや、現在の語法になった変遷の解説、様々な違った言い回しの共通点が浮き彫りになっていく説明など、グノは普通の受験勉強とはひと味もふた味も違っていました。
それから、適語補充や並べ替え、間違い探しなど、いろいろな種類の文法問題を解けるので飽きることがありませんでした。
英文法の勉強が楽しいと思えるようになったのは、私の中では大きな変化でした。文法事項の成り立ちや、現在の語法になった変遷の解説、様々な違った言い回しの共通点が浮き彫りになっていく説明など、グノは普通の受験勉強とはひと味もふた味も違っていました。
馬場:
授業内で演習してすぐに添削してもらえるので、効率良く効果的に勉強できました。
宿題にされると他のことで忙しかったり、家だとダラダラしてしまうこともありますが、授業で集中していれば深く考えられるし、時間あたりの演習量は飛躍的に上がります。
家での復習は音読が中心でしたが、それで英語の力がどんどんつきました。
宿題にされると他のことで忙しかったり、家だとダラダラしてしまうこともありますが、授業で集中していれば深く考えられるし、時間あたりの演習量は飛躍的に上がります。
家での復習は音読が中心でしたが、それで英語の力がどんどんつきました。
■グノーブルの音読
英語の指導では音読が重視されていますが、皆さんはどのように取り組みましたか?
英文を読み込んでいると、気づいていなかった面白さがさらに見えてくることもありました。そんな経験をときどきするので、音読は楽しくてやめられません

馬場:
音読については、グノに入った高1のときから先生方が強調されていましたが、そのときは半信半疑でサボりがちでした。でも、学年が上がるにつれてしっかり取り組むようになりました。声を出して音読できるのは家でしたが、電車の中でもマスクをしてコソコソ呟いていました。
グノでは、受験直前期でも過去問を解くよりも音読をするように言われます。この時期は他の教科でやりたいことがたくさんありますが、音読だけでいいのだから、これだけはしっかりやろうと思えて気持ちが楽でした。
グノでは、受験直前期でも過去問を解くよりも音読をするように言われます。この時期は他の教科でやりたいことがたくさんありますが、音読だけでいいのだから、これだけはしっかりやろうと思えて気持ちが楽でした。
片山:
私は週によって音読にムラがありました。添削で点数が良くなかったり、先生から厳しい指摘をいただいた週はしっかり音読して、添削で点数が良かった週などは少ししか取り組みませんでした。
受験直前期は、理科や数学の過去問をやっていてつらくなったら、気晴らしに英語の音読をしました。特に物語文は読んでいて楽しかったので、良い息抜きになりました。
受験直前期は、理科や数学の過去問をやっていてつらくなったら、気晴らしに英語の音読をしました。特に物語文は読んでいて楽しかったので、良い息抜きになりました。
松田:
グノの英文は本当に面白くて、行き帰りの電車の中で英文を読み込むのが毎日の習慣になるほどのめり込みました。そのおかげで、毎日英語に触れることになって、英語力がぐんと伸びました。日に日に読むスピードが速くなるというよりも、突然速く読めるようになった経験があって効果を実感していました。
馬場:
解説を聞いて十分に理解している英文を、何度も繰り返し読み込むことには本当に効果があります。
音読するにしても、中途半端に読んでいるだけだとそれほど力はつかないと思います。内容を意識しながら、英語のまま人に読み聞かせて伝えるつもりになることが音読の秘訣です。それには、授業で先生がおっしゃっていた解説をしっかり理解している必要があります。
英文を読み込んでいると、気づいていなかった面白さがさらに見えてくることもありました。そんな経験をときどきするので、音読は楽しくてやめられませんでした。
グノの先生は、過去の授業で扱った英文と関連のある英文を改めて用意して取り上げてくださることもあります。以前読んだ英文の著者が書いた別の分野の英文や、以前読んだ英文の反対意見が書かれたものを読むこともあります。そうすると、こちらの理解度がさらに深くなって、誰かに伝えるつもりの音読が、さらにやっていて楽しいものになります。
音読するにしても、中途半端に読んでいるだけだとそれほど力はつかないと思います。内容を意識しながら、英語のまま人に読み聞かせて伝えるつもりになることが音読の秘訣です。それには、授業で先生がおっしゃっていた解説をしっかり理解している必要があります。
英文を読み込んでいると、気づいていなかった面白さがさらに見えてくることもありました。そんな経験をときどきするので、音読は楽しくてやめられませんでした。
グノの先生は、過去の授業で扱った英文と関連のある英文を改めて用意して取り上げてくださることもあります。以前読んだ英文の著者が書いた別の分野の英文や、以前読んだ英文の反対意見が書かれたものを読むこともあります。そうすると、こちらの理解度がさらに深くなって、誰かに伝えるつもりの音読が、さらにやっていて楽しいものになります。
■グノーブルの英語の特長
グノーブルの英語の特長はどんなところにあったと思いますか?
授業で扱う英文が新鮮でいろいろな分野の英文と出会え、その解説でも面白い話がたくさん聞けるので、英語を勉強しながら英語以外のことも学べて知識の幅が広がりました

松田:
他塾では、志望校別にクラスが分かれると聞いています。例えば医学部志望だと、医学系の英文ばかり読まされるみたいです。グノにはそうしたことが全くなくて、いろいろな分野からの英文を先生が教材にしてくださいます。
英文の内容解説の詳しさと楽しさも、グノは随一だと思います。僕は受験のためだけに難しい英文を読むのが性に合わなくて、それではやる気が出ませんでした。
グノでは、受験を意識しすぎることもなく、純粋に面白い英文に触れられて、やる気を持続できました。
グノの英文は本当にバラエティーに富んでいます。物語もあれば時事的な話題もあり、哲学的な難しい英文もありましたが、どれも面白いものばかりでした。
最新のニュースを翌週の授業でリアルタイムに読めることも多く、自分が知りたいことを英文で読めるのが楽しかったです。 受験生の精神状態に役立つ英文もあって、僕は「入試本番前はこの英文を読もう」と事前にそれを選んでいて、実際にその英文が本番の緊張感をなくすのに役立ちました。
英文の内容解説の詳しさと楽しさも、グノは随一だと思います。僕は受験のためだけに難しい英文を読むのが性に合わなくて、それではやる気が出ませんでした。
グノでは、受験を意識しすぎることもなく、純粋に面白い英文に触れられて、やる気を持続できました。
グノの英文は本当にバラエティーに富んでいます。物語もあれば時事的な話題もあり、哲学的な難しい英文もありましたが、どれも面白いものばかりでした。
最新のニュースを翌週の授業でリアルタイムに読めることも多く、自分が知りたいことを英文で読めるのが楽しかったです。 受験生の精神状態に役立つ英文もあって、僕は「入試本番前はこの英文を読もう」と事前にそれを選んでいて、実際にその英文が本番の緊張感をなくすのに役立ちました。
片山:
知的な刺激を受けられるのはグノの英語の大きな特長です。
授業で扱う英文が新鮮で、時事的な話題をはじめ、いろいろな分野の英文と出会え、その解説でも面白い話がたくさん聞けるので、英語を勉強しながら英語以外のことも学べて知識の幅が広がりました。
倫理政経の話題とリンクする論説文や、生物の授業で習った単語が出てきたときは、うれしくなりました。
高3の後半からは東大の総合読解で出題されるような物語文もよく扱いました。文学的な英文は説明文と違って想像力を働かせながら読まなければなりませんが、どの文章も本当に楽しめました。決して子どもっぽいものではなく、恋愛と絡んでいるものもあって、まるで日本語の小説を読んでいるようでした。
私は英語を受験勉強の教科としてガリガリやりたくありませんでした。英語が好きだったのは洋楽を聞いたりして楽しんでいたからで、そうした楽しさを壊したくなかったんです。
だから、「英語の語順通り英文を前から解釈する」とか「市販の単語帳の暗記はしない」という学び方は私にぴったりだったんです。
グノは確かに、あたりまえだとされている英語の勉強法とは違います。でも、グノで勉強しているうちに「これいいな!」と実感できるようになり、不安は全くありませんでした。
授業で扱う英文が新鮮で、時事的な話題をはじめ、いろいろな分野の英文と出会え、その解説でも面白い話がたくさん聞けるので、英語を勉強しながら英語以外のことも学べて知識の幅が広がりました。
倫理政経の話題とリンクする論説文や、生物の授業で習った単語が出てきたときは、うれしくなりました。
高3の後半からは東大の総合読解で出題されるような物語文もよく扱いました。文学的な英文は説明文と違って想像力を働かせながら読まなければなりませんが、どの文章も本当に楽しめました。決して子どもっぽいものではなく、恋愛と絡んでいるものもあって、まるで日本語の小説を読んでいるようでした。
私は英語を受験勉強の教科としてガリガリやりたくありませんでした。英語が好きだったのは洋楽を聞いたりして楽しんでいたからで、そうした楽しさを壊したくなかったんです。
だから、「英語の語順通り英文を前から解釈する」とか「市販の単語帳の暗記はしない」という学び方は私にぴったりだったんです。
グノは確かに、あたりまえだとされている英語の勉強法とは違います。でも、グノで勉強しているうちに「これいいな!」と実感できるようになり、不安は全くありませんでした。
馬場:
私も、中学時代から周りの人たちが焦って単語帳を必死に覚えているのを見て、「こういうのはしたくない」と思っていました。その流れに入りたくなかったんです。
かといって、「単語帳は要らない」と言われても初めは半信半疑でした。ただ、グノに入塾したのは高1で、すぐに学力を上げなければいけない状況ではなく「グノのやり方を信じてやってみて、成績が上がらなかったら変えよう」くらいの気持ちでした。グノのやり方を否定せずとりあえずその通りに勉強してみたら、成績も安定してとれるようになり、困ることもなかったので、そのまま信じて続けることにしました。単語帳を使わずにできるならそれが一番ですから。
かといって、「単語帳は要らない」と言われても初めは半信半疑でした。ただ、グノに入塾したのは高1で、すぐに学力を上げなければいけない状況ではなく「グノのやり方を信じてやってみて、成績が上がらなかったら変えよう」くらいの気持ちでした。グノのやり方を否定せずとりあえずその通りに勉強してみたら、成績も安定してとれるようになり、困ることもなかったので、そのまま信じて続けることにしました。単語帳を使わずにできるならそれが一番ですから。
■英語の力が伸びた時期
普段の努力が成績の向上として実感できたのはいつ頃からたったのでしょうか?
気晴らしにずっと洋画を見ていたんですが、そこで流れてくる英語を理解できて「使える英語が身についた」と実感しました
松田:
高2の夏に受験を意識してから、一気に読むスピードが上がりました。それまで英語の伸びを感じることもなかったので、急激な変化でした。
それから、高3の夏明けに肺気胸になって家から出られない日が続きました。このとき、気晴らしにずっと洋画を見ていたんですが、そこで流れてくる英語を理解できて、「使える英語が身についた」と実感しました。
それから、高3の夏明けに肺気胸になって家から出られない日が続きました。このとき、気晴らしにずっと洋画を見ていたんですが、そこで流れてくる英語を理解できて、「使える英語が身についた」と実感しました。
馬場:
以前から私は英語が好きでしたが、得意だとは思っていませんでした。中学時代はどの科目が得意とか苦手とかはなく、英語も普通のレベルでした。
高1でグノに入って音読を続けていたら、ほとんどの模試で一番安定して得点できる科目が英語になっていて、英文を読む力が身についているのがわかりました。
高1でグノに入って音読を続けていたら、ほとんどの模試で一番安定して得点できる科目が英語になっていて、英文を読む力が身についているのがわかりました。
片山:
私も馬場さんと同じで、模試の成績を見ると、自分が思っていたよりも英語ができるようになりました。それからグノの授業で先生の質問に対して答えがわかる度合いが少しずつ上がっていきました。入塾前の私は「英語が得意」と思っていましたし、学校のテストや模試でも一番できる科目でした。それなのに、入塾直後のクラスはα3*1でした。このことに危機感を抱いてがんばったから、気づかないうちに英語の力が伸びていたんだと思います*2。
*1 この学年の高2時の英語は、α(最上位)から、α1、α2、α3、α4、α5の設定。
*2 片山さんはTLP の認定を受けました。TLP(Trilingual Program):「グローバルリーダー育成プログラム」の一環。東大の英語入試で上位1割程度に入った学生に認められています。
*1 この学年の高2時の英語は、α(最上位)から、α1、α2、α3、α4、α5の設定。
*2 片山さんはTLP の認定を受けました。TLP(Trilingual Program):「グローバルリーダー育成プログラム」の一環。東大の英語入試で上位1割程度に入った学生に認められています。
■グノーブルの数学
数学の授業の印象はどうだったでしょうか?
問題を解いているときには、先生がいつも一人ひとりの座席をまわり、優しい言葉やアドバイスをくださったりしたので、いつも安心して数学の問題に向かえました
馬場:
高1のときは受験を意識することもなく、抽象度が上がった高校数学の考え方を純粋に楽しんでいました。私たちが問題を解いているときには、先生がいつも一人ひとりの座席をまわってくださって、優しい言葉をかけてくださったり、アドバイスをくださったりしたので、いつも安心して数学の問題に向かえました。
高2、高3になると先生が変わり、数学に向かう姿勢も変わりました。ただ楽しく問題を解いていくのではなく、「1個1個の問題ではなくて全体を見る」という教わり方になりました。数Ⅰ A Ⅱ Bと数Ⅲではそれぞれ別の先生に習いましたが、どちらの先生も1個1個の問題を詳しく解説してくださるだけでなく、その問題のテーマをタグづけして分類し、テーマごとに気をつけるべき点を教えてくださいましたから、どんな問題もテーマと関連づけて解けるようになりました。
高3ではセルフチェックシートを書くことが求められます。前期は、予習の演習問題を解くだけでも大変なのに、さらにシートの欄を埋めなければならず、最初は「こんなことに時間を使っていていいのかな?」と思いました。でも、徐々にその効果を実感できるようになりました。
予習形式だと、まだ習っていないことだから手も足も出ないことがあります。その「わからない」をセルフチェックシートで把握することに意義がありました。
シートに書いていると、同じ「わからない」でも、本当に全くわからないのか、ここまでわかったけれどここからはわからないということなのかが自覚できます。その上で授業を受けると、授業の理解度が深まりました。「あの問題と似た問題だから、こう解けばいい」で終わってしまう復習重視の授業とは異なるアプローチでした。
後期のテスト演習でも、テスト結果についてセルフチェックシートを書きます。時間が無制限な予習とは違って、90 分のテスト形式だと「ここで考えすぎたからこちらに時間が回らなかった」などという新たな課題も出てきて、それをセルフチェックシートに書きました。
1回1回を大切にできたのは、このように書く機会があったからです。後期になると数学の力だけでなく戦略も大事になってくるので、問題の復習だけでは獲得できない視点を得られたのが有益でした。
高2、高3になると先生が変わり、数学に向かう姿勢も変わりました。ただ楽しく問題を解いていくのではなく、「1個1個の問題ではなくて全体を見る」という教わり方になりました。数Ⅰ A Ⅱ Bと数Ⅲではそれぞれ別の先生に習いましたが、どちらの先生も1個1個の問題を詳しく解説してくださるだけでなく、その問題のテーマをタグづけして分類し、テーマごとに気をつけるべき点を教えてくださいましたから、どんな問題もテーマと関連づけて解けるようになりました。
高3ではセルフチェックシートを書くことが求められます。前期は、予習の演習問題を解くだけでも大変なのに、さらにシートの欄を埋めなければならず、最初は「こんなことに時間を使っていていいのかな?」と思いました。でも、徐々にその効果を実感できるようになりました。
予習形式だと、まだ習っていないことだから手も足も出ないことがあります。その「わからない」をセルフチェックシートで把握することに意義がありました。
シートに書いていると、同じ「わからない」でも、本当に全くわからないのか、ここまでわかったけれどここからはわからないということなのかが自覚できます。その上で授業を受けると、授業の理解度が深まりました。「あの問題と似た問題だから、こう解けばいい」で終わってしまう復習重視の授業とは異なるアプローチでした。
後期のテスト演習でも、テスト結果についてセルフチェックシートを書きます。時間が無制限な予習とは違って、90 分のテスト形式だと「ここで考えすぎたからこちらに時間が回らなかった」などという新たな課題も出てきて、それをセルフチェックシートに書きました。
1回1回を大切にできたのは、このように書く機会があったからです。後期になると数学の力だけでなく戦略も大事になってくるので、問題の復習だけでは獲得できない視点を得られたのが有益でした。
■グノーブルの物理・化学
物理・化学の授業の特色を教えてください
化学は実験の印象が残っていたので「この物質はあの実験で出てきたものだ」と思い出せて、暗記や理解も捗りました
馬場:
高2の夏から物理を受講しました。グノの物理は、公式の導出を一からすべてやります。その公式を発見した歴史上の人物を一人ずつ追いながら、成功に至る過程だけでなく、失敗も含めてたどっていくんです。この人は1回こうやってこう思ったけれど、違ったからこっちを考えてこの公式に至ったというような話が本当に楽しかったです。
ただ、公式を一から導出するのは結構大変で、さらに物理学者が考えたことを一緒に考えるのは難しいのも事実です。だから、最初は「公式をそのまま覚えた方が楽だ」と思いました。でも、高3後期に応用問題を解く段階になると、公式丸暗記だと引っかかる問題も引っかからずに解く力が身についていることを実感できました。
化学は高2で夏期講習だけ受講したあと、部活が忙しかったので先生に相談して一度お休みにしました。
高3で復帰してからは、後期のテスト演習が始まるまでの実験がとにかく楽しかったのを覚えています。私の場合、前期は数学に力を入れていて、化学の勉強をあまりしていませんでした。それでもグノで実験を生で見られたり、生で見られない実験はビデオで見せてもらえたりして、塾っぽくない授業を純粋に楽しんでいました。
化学の勉強を本格化させた後期では、前期の実験の印象が残っていたので、「この物質はあの実験で出てきたものだ」と思い出せて、暗記や理解も捗りました。
ただ、公式を一から導出するのは結構大変で、さらに物理学者が考えたことを一緒に考えるのは難しいのも事実です。だから、最初は「公式をそのまま覚えた方が楽だ」と思いました。でも、高3後期に応用問題を解く段階になると、公式丸暗記だと引っかかる問題も引っかからずに解く力が身についていることを実感できました。
化学は高2で夏期講習だけ受講したあと、部活が忙しかったので先生に相談して一度お休みにしました。
高3で復帰してからは、後期のテスト演習が始まるまでの実験がとにかく楽しかったのを覚えています。私の場合、前期は数学に力を入れていて、化学の勉強をあまりしていませんでした。それでもグノで実験を生で見られたり、生で見られない実験はビデオで見せてもらえたりして、塾っぽくない授業を純粋に楽しんでいました。
化学の勉強を本格化させた後期では、前期の実験の印象が残っていたので、「この物質はあの実験で出てきたものだ」と思い出せて、暗記や理解も捗りました。
■グノーブルの先生
先生方はどのように皆さんの勉強と関わってくれましたか?
先生が英語のどういうところに面白さを見出していらっしゃるのかが伝わってきて、「自分もこうなりたい」と毎回思いました
片山:
グノの先生から一番感じたのは英語に対する愛や情熱でした。先生が英語のどういうところに面白さを見いだしていらっしゃるのかが伝わってきて、「自分もこうなりたい」と毎回思いました。「自分のレベルだとこの程度にしか読めない英文でも、もっと英語ができるようになったら、先生のようにさらに面白い英文に見えてくるんじゃないか?」と思うと、英語をがんばるモチベーションになりました。
自分の趣味として、「洋書を読んだり、洋画を観たりしてみたい」とか「日本語で勉強した教科を英語で勉強したらどうなるのかな?」とか、グノで英語を勉強していると次々と興味が湧き、英語がどんどん好きになりました。
自分の趣味として、「洋書を読んだり、洋画を観たりしてみたい」とか「日本語で勉強した教科を英語で勉強したらどうなるのかな?」とか、グノで英語を勉強していると次々と興味が湧き、英語がどんどん好きになりました。
馬場:
グノの先生は様々な個性をお持ちですが、どの先生も生徒を第一に考えてくださっているのが伝わってきました。先生というと偉そうなイメージがありますが、グノの先生には偉そうな感じがありませんでした。例えば、授業前に早く教室にいらして、生徒が入ってくると挨拶してくださいます。そして、授業が終わっても、先生が真っ先に帰るのではなく、最後まで教室にいてくださって、生徒全員に「さようなら」と挨拶してくださいます。そういうところから生徒第一の姿勢が伝わってきました。
グノの先生は腰が低く、生徒としても居心地が良かったです。
グノの先生は腰が低く、生徒としても居心地が良かったです。
松田:
グノの先生は優しいです。一人ひとりの成長を見てくださいますし、一人ひとりの意見も尊重してくださるので、生徒を大切にしているのがよくわかりました。一方で、勉強を教える立場としての一定の厳しさはどの先生にもありました。そのおかげで僕はだらしなくならずに勉強できました。
■グノーブルの環境
学習環境の面でグノーブルの良いところを教えてください
グノの教室のきれいさには僕もいつも感謝していました。勉強に集中する場所としてふさわしい環境だったと思います
馬場:
学校で私が所属していたリズム水泳部は発表会のある11 月がとても忙しく、他にも応援団をやっていたので体育大会のある5月も忙しかったです。
そんな学校生活でしたが、忙しい時期でもグノの宿題に追われることはなかったので助かりました。習い事のバレエも、グノの振替制度を活用することで両立できました。
そんな学校生活でしたが、忙しい時期でもグノの宿題に追われることはなかったので助かりました。習い事のバレエも、グノの振替制度を活用することで両立できました。
片山:
私も通常授業に通い始めてしばらくは、塾と部活が重なっていました。
でもグノでは、夕方の5時前に始まる授業と7時過ぎから始まる授業があって、私は後コマの授業に出席していたので遅刻することもなく通えました。授業前に時間があるときは学校の宿題を終わらせることもできました。塾と部活との両立がしっかりできてありがたかったです。
それから、受付の方が親切で丁寧でした。電話の対応も話し方から丁寧さが伝わってきて、毎回「すごい」と思っていました。
それと、黒板がいつもきれいでした。授業の入れ替わりのときには、どの先生も黒板をすっかりきれいにしてから教室を離れていきます。いつも新品みたいな黒板で、私たちの学習環境に対する配慮を感じました。
でもグノでは、夕方の5時前に始まる授業と7時過ぎから始まる授業があって、私は後コマの授業に出席していたので遅刻することもなく通えました。授業前に時間があるときは学校の宿題を終わらせることもできました。塾と部活との両立がしっかりできてありがたかったです。
それから、受付の方が親切で丁寧でした。電話の対応も話し方から丁寧さが伝わってきて、毎回「すごい」と思っていました。
それと、黒板がいつもきれいでした。授業の入れ替わりのときには、どの先生も黒板をすっかりきれいにしてから教室を離れていきます。いつも新品みたいな黒板で、私たちの学習環境に対する配慮を感じました。
馬場:
私も片山さんと同じく受付が印象的でした。他塾に通う友達は「受付が怖い」とか「受付の人がぶっきらぼうだ」とか話していましたが、グノにはそういうことが全くありませんでした。忘れ物して「ごめんなさい」という気持ちになっているときも、受付に行くと優しく対応していただけました。振替でもとてもお世話になりました。
松田:
僕も受付の対応には親切さを感じました。自習室を使うときもすぐに対応してくださって、生徒のことをきちんと見ていてくださるのがありがたかったです。
それから、グノの教室のきれいさには僕もいつも感謝していました。勉強に集中する場所としてふさわしい環境だったと思います。
それから、グノの教室のきれいさには僕もいつも感謝していました。勉強に集中する場所としてふさわしい環境だったと思います。
■後輩へのアドバイス
これから受験する後輩に向けて一言お願いします
幅広く本質的な出題をする東大の英語には、グノの幅広い英語への取り組みがぴったりです
松田:
グノの先生は、どんな質問をぶつけても真剣に返してくださいます。だから、ちょっとでも疑問に思うことがあれば、先生を質問攻めにしてください。得られるものは大きいはずです。
そして、先生の言葉に従って、グノが用意してくれた英文を読み込んでいけば、東大に受かる英語力が間違いなくつきます。グノは東大重視の塾ではありませんが、幅広く本質的な出題をする東大の英語には、グノの幅広い英語への取り組みがぴったりです。グノを信じて勉強してください。
そして、先生の言葉に従って、グノが用意してくれた英文を読み込んでいけば、東大に受かる英語力が間違いなくつきます。グノは東大重視の塾ではありませんが、幅広く本質的な出題をする東大の英語には、グノの幅広い英語への取り組みがぴったりです。グノを信じて勉強してください。
片山:
毎回の授業で行われる要約や英作文の添削に全力で取り組むことが大事です。私はたまにどうしても言葉が思いつかず、妥協して要約などを書くことがありました。そういうときはもやもやしたり、「もっと良く書けたのでは?」と思ったりして、先生の解説に集中できませんでした。逆に、全力でやってダメだったときは、同じ授業を聞いても、得られるものが多く、後々そういう問題ほど印象に残っていました。この経験から、毎回の授業に全力で取り組むことの大切さを強調したいと思います。
馬場:
私は東大入試の全科目をグノで完結させました。
確かにグノの教え方や推奨する勉強法は学校や他塾と違って特殊なところがあります。でも、単語帳の暗記をしない、セルフチェックシートをつける、物理の公式を導出する、化学の実験をするなど、どれをとっても生徒が主体的になって本当の実力がつくようにと考え抜かれているからだと思います。
「グノでがんばる」と決めたからには他のことには手を出さず、グノの先生がおっしゃるやり方を忠実に守れば、それが合格への近道だと思います。実際、私はグノ一本で最後まで勉強して、とてもいい受験生活が送れたと感謝しています。
確かにグノの教え方や推奨する勉強法は学校や他塾と違って特殊なところがあります。でも、単語帳の暗記をしない、セルフチェックシートをつける、物理の公式を導出する、化学の実験をするなど、どれをとっても生徒が主体的になって本当の実力がつくようにと考え抜かれているからだと思います。
「グノでがんばる」と決めたからには他のことには手を出さず、グノの先生がおっしゃるやり方を忠実に守れば、それが合格への近道だと思います。実際、私はグノ一本で最後まで勉強して、とてもいい受験生活が送れたと感謝しています。