東京大学理系 Part 2
ホーム > Gno-let > Gno-let23 > 東京大学 理系 Part2
| 庄司 一毅さん(理Ⅰ・開成) | 西 真理夏さん(理Ⅰ・国府台女子学院) |
| 平山 愛梨さん(理Ⅱ・桜蔭) | 宮本 卓英さん(理Ⅱ・開成) |
入塾のきっかけ
英単語の覚え方
グノーブルの音読
グノーブルで扱う英文
英語の力が伸びた時期
グノーブルの数学
グノーブルの国語
グノーブルの先生
グノーブルの環境
後輩へのアドバイス
※は、web版のみの掲載項目
英単語の覚え方
グノーブルの音読
グノーブルで扱う英文
英語の力が伸びた時期
グノーブルの数学
グノーブルの国語
グノーブルの先生
グノーブルの環境
後輩へのアドバイス
※は、web版のみの掲載項目
■入塾のきっかけ
なぜグノーブルを選んだのでしょうか?
以前グノに通っていた姉の強い勧めもあり、実際にグノの授業を受けたら、とても面白くて「ここでがんばろう」と思いました

庄司:
きっかけは高1のときです。英語が苦手で学校の定期テストすら大惨事だったので、英語を強化できる塾を探していたんです。
いろいろな人から「英語といえばグノ」と聞いていたし、友達全員から勧められたこともあって、グノにしました。
英語だけのつもりでしたが、途中から数学も受講しました。
いろいろな人から「英語といえばグノ」と聞いていたし、友達全員から勧められたこともあって、グノにしました。
英語だけのつもりでしたが、途中から数学も受講しました。
平山:
私は高1の夏期講習から入塾しました。「英語に力を入れている塾に入りたい」と思い、塾探しを始め、宿題が多いところは初めから候補から外しました。
グノには部活の先輩がたくさん入っていて楽しそうだったこともあり、夏期講習を受けてみることにしました。実際に講習が良かったので、2学期以降もそのままグノに通い続けました。
グノには部活の先輩がたくさん入っていて楽しそうだったこともあり、夏期講習を受けてみることにしました。実際に講習が良かったので、2学期以降もそのままグノに通い続けました。
西:
私も高1からですが、最初に受講したのは国語です。国語が中学生の頃からとても苦手で、「東大を目指したい」と思ったときに危機感を抱いていたんです。以前グノに通っていた姉が「グノの国語、いいよ」と強く勧めてくれたこともあり、実際にグノの授業を受けたら、とても面白くて「ここでがんばろう」と思いました。
英語は高1の3学期から通い始めました。「英語をしっかり学べる塾に入りたい」と思っていましたが、やはり姉や、それから友人からもグノを勧められて講習を受けてみることにしました。初回の授業から気に入りましたし、宿題が負担にならない量だったことも決め手になって入塾しました。
英語は高1の3学期から通い始めました。「英語をしっかり学べる塾に入りたい」と思っていましたが、やはり姉や、それから友人からもグノを勧められて講習を受けてみることにしました。初回の授業から気に入りましたし、宿題が負担にならない量だったことも決め手になって入塾しました。
宮本:
僕は中1のときから英語に通っていました。兄がグノに入ったので一緒に、という流れです。
高1では古文も受講しました。グノは宿題の負担が少なかったので、学校生活と両立できたのも良かったです。
高1では古文も受講しました。グノは宿題の負担が少なかったので、学校生活と両立できたのも良かったです。
■英単語の覚え方
受験では数多くの英単語を暗記しなければならないと思いますが、どのように乗り越えたのでしょうか?
語源の解説はおもしろくて、時には感動することすらありました
西:
グノの英語は、「市販の単語帳で暗記しなくていい」というのが特徴です。
グノに入る前は、世間で出回っている単語帳を一生懸命やっていました。でも、小学生の頃から暗記がとても苦手で、覚えてもすぐ忘れるし、2回、3回と取り組んでも定着しないし、本当に嫌いでした。
グノでは、単語を覚えるのではなく語源から理解するので、それが私には合っていました。
グノに入る前は、世間で出回っている単語帳を一生懸命やっていました。でも、小学生の頃から暗記がとても苦手で、覚えてもすぐ忘れるし、2回、3回と取り組んでも定着しないし、本当に嫌いでした。
グノでは、単語を覚えるのではなく語源から理解するので、それが私には合っていました。
宮本:
語源に立ち返っての解説は特徴的で、他塾の人に話したら驚かれました。ある単語の語源について教わったあとに、それと同じ語源を持つ別の単語を学ぶと、以前教わった単語の復習にもなります。それで理解が深まるので、単語を簡単に覚えられました。
平山:
私も、語源から単語を教えてくれるのが本当に良かったです。語源の解説は面白くて、時には感動することすらありました。興味の湧くことは記憶に残りやすいし、同じ語源から派生した単語について何回も何回も繰り返して学べるので、1回では定着しなくてもいつの間にか覚えてしまいます。
■グノーブルの音読
英語の指導では音読が重視されていますが、皆さんはどのように取り組みましたか?
続けていると音声が脳内に勝手に流れてくるようになるんです。それが英作文を書くときにサンプルになるので、英作文の点数も伸びました
庄司:
グノの英文は使い捨てではありません。授業で解説を受けて十分に理解している英文をひたすら音読して自分になじませるんです。
先生はスポーツや楽器演奏の練習と外国語の練習は同じだとおっしゃっていましたが、同じ英文を読み込んで慣れていくのがグノの音読です。授業で理解したつもりの英文でも、家に帰ってみると1回目の音読から詰まってしまいます。それでも何度も何度も音読することで、段々スラッと読めるようになります。
その過程で、新しい単語や表現も、英文の中でしっかり理解できるし、英語のリズムや流れもわかるし、英語らしい文の組み立てにもなじめると思います。第一、英文をスラスラ音読できると「伸びている」と実感できてうれしくなります。
先生はスポーツや楽器演奏の練習と外国語の練習は同じだとおっしゃっていましたが、同じ英文を読み込んで慣れていくのがグノの音読です。授業で理解したつもりの英文でも、家に帰ってみると1回目の音読から詰まってしまいます。それでも何度も何度も音読することで、段々スラッと読めるようになります。
その過程で、新しい単語や表現も、英文の中でしっかり理解できるし、英語のリズムや流れもわかるし、英語らしい文の組み立てにもなじめると思います。第一、英文をスラスラ音読できると「伸びている」と実感できてうれしくなります。

西:
私は高2の3学期、グノでの受験学年が始まってから本格的に音読を始めました。普段は寝る前に30 分くらい、時間がなくても最低10 分は毎日欠かさず取り組みました。それまでも、授業前に自分の頭を英語脳にするため、音読にちょっとは取り組んでいましたが、そんなにがっちりはやっていませんでした。
音読は長期的に継続することで効果が出てきます。
グノでは、受験学年の読解の授業は毎回、英文の要約演習をして、それを先生に提出して添削と採点をしてもらいます。高2の3学期の間は毎週散々な結果でした。要約をするには、筆者の主張をちゃんと見抜いて、英文全体の構造をつかむ必要があります。それが私には難しくて高3の1学期の間は、クラスでもずっと下の方だったんです。
でも、グノの先生の言葉を信じて毎日音読を続けていたら、最終的には難しかった要約の点数も上がっていきました。
それから、グノの音読は、音声教材でネイティブの音声を聞きながら自分でも発音します。そうやって耳や口を鍛える練習をしているうちに、リスニングの点数も大きく伸びました。
音読は長期的に継続することで効果が出てきます。
グノでは、受験学年の読解の授業は毎回、英文の要約演習をして、それを先生に提出して添削と採点をしてもらいます。高2の3学期の間は毎週散々な結果でした。要約をするには、筆者の主張をちゃんと見抜いて、英文全体の構造をつかむ必要があります。それが私には難しくて高3の1学期の間は、クラスでもずっと下の方だったんです。
でも、グノの先生の言葉を信じて毎日音読を続けていたら、最終的には難しかった要約の点数も上がっていきました。
それから、グノの音読は、音声教材でネイティブの音声を聞きながら自分でも発音します。そうやって耳や口を鍛える練習をしているうちに、リスニングの点数も大きく伸びました。
宮本:
確かに続けることは大切です。
僕は最初、音読は日本人にはきついと思っていました。でも、続けていると、音声が脳内に勝手に流れてくるようになるんです。それが英作文を書くときにサンプルになるので、英作文の点数も伸びました。英作文で困って「何かないかな?」と考えるとき、音読した英文はとても思い出しやすかったです。
僕は最初、音読は日本人にはきついと思っていました。でも、続けていると、音声が脳内に勝手に流れてくるようになるんです。それが英作文を書くときにサンプルになるので、英作文の点数も伸びました。英作文で困って「何かないかな?」と考えるとき、音読した英文はとても思い出しやすかったです。
平山:
私の場合も、音読が英作文の役に立ったのは確かです。音読していると、英文の構造や表現について、「これが自然なんだな」ということがわかってきます。
庄司:
僕は音読するとき、内容を意識していました。英文の確実な理解はもちろん、さらにそれを自分が表現するというイメージで、プレゼンするように音読していました。
黙読でも頭の中で声に出しているつもりで読むことはできますが、実際に口に出してみることで得られる効果があります。口に出してみると舌が回らなかったり、イントネーションがうまくつかめなかったりすることがあります。練習してそうした部分を解消していくと、読解のスピードがアップします。
黙読でも頭の中で声に出しているつもりで読むことはできますが、実際に口に出してみることで得られる効果があります。口に出してみると舌が回らなかったり、イントネーションがうまくつかめなかったりすることがあります。練習してそうした部分を解消していくと、読解のスピードがアップします。
西:
私は、中学受験や高校受験をしていなくて、受験というものがどういうものかわかっていませんでした。物心ついてから初めての受験がセンター試験だったので、当日は緊張しすぎて昼食を食べられず、貧血気味になりました。でも、英語の問題用紙を開いたら英文がスラスラ頭に入ってきて、読解問題は満点でした。音読をやっていたから救われたんだと思っています。
■グノーブルで扱う英文
英語の授業はどんな雰囲気だったのか教えてください。
科学や医学の話題、経済や社会学などいろんな英文に触れられました。哲学の話題が占めた授業もあって、いつも新鮮でした

平山:
グノは英文自体が面白かったのも特徴です。
英語のニュースが教材になることも多く、哲学や科学の話題もあって、「こんな考えがあるんだ」という驚きの連続でした。
英語を学ぶだけでなく、それ以上に社会勉強みたいになっていて、それが本当に刺激的でした。先生の話を聞くだけでも楽しくて仕方ありませんでした。
英語のニュースが教材になることも多く、哲学や科学の話題もあって、「こんな考えがあるんだ」という驚きの連続でした。
英語を学ぶだけでなく、それ以上に社会勉強みたいになっていて、それが本当に刺激的でした。先生の話を聞くだけでも楽しくて仕方ありませんでした。
西:
授業で扱う英文のトピックは時事関係のことも多くて助かりました。受験勉強中は基本的にテレビでニュースを見なかったので、社会にどういう意見を持っている人がいるのかを深く知る機会がありませんでした。
でも、グノの教材を読んで、先生の話を聞いて、「こういう考え方をする人もいるんだな」と知ることができました。
でも、グノの教材を読んで、先生の話を聞いて、「こういう考え方をする人もいるんだな」と知ることができました。
宮本:
時事的な教材だけではなく、科学や医学の話題、経済や社会学などいろいろな英文に触れられました。他にも哲学の話題を扱うときもあって、いつも新鮮でした。
庄司:
自分の知らないことを英文で読めたので、そのことを僕は音読の表現にも活かしました。それを知らなかった頃の自分やまだ知らなさそうな人を目の前に思い浮かべて、「実はこうなんですよ」とプレゼンするつもりで音読していました。気持ちを乗せやすくなって、とても音読しやすかったです。
■英語の力が伸びた時期
普段の努力が成績の向上として実感できたのはいつ頃からだったのでしょうか?
高3の秋です。それまでは要約演習で的外れなことに重点を置いてまとめてしまう状態が続いていましたが、自分の中で押さえるべきポイントが見えるようになったんです
平山:
中学生の頃、学校内では英語は問題ありませんでしたが、高校に進学する直前に受けた全国規模の模試で、学校の英語との違いを感じました。全然わからない問題もあって怖くなってしまいました。
グノに入ってから半年後にまた模試を受けましたが、そのときはちゃんと解けて、「伸びているんだな」と安心しました。
グノでは、文法もしっかり教えてもらえましたし、かなりの長文を毎週たくさん読めました。英文の背景まで先生は解説をしてくださるのでよく理解できます。グノの授業は毎週完結型なので、1週間かけての復習もやりやすく、それでいろいろな力が定着したんだと思います。
グノに入ってから半年後にまた模試を受けましたが、そのときはちゃんと解けて、「伸びているんだな」と安心しました。
グノでは、文法もしっかり教えてもらえましたし、かなりの長文を毎週たくさん読めました。英文の背景まで先生は解説をしてくださるのでよく理解できます。グノの授業は毎週完結型なので、1週間かけての復習もやりやすく、それでいろいろな力が定着したんだと思います。
庄司:
僕も入塾直後に英語力の伸びを実感できました。
そもそも僕は、グノに入るまで英語を体系的に勉強したことがありませんでした。英文は主語述語の順番に並ぶということや、動詞が目的語をとる・とらないといったことも知らず、ただ単語が並んでいるだけの英文をどう読んだらいいかがわかっていませんでした。
そんな状態から、グノで英語の仕組みをひとつずつ教わり英文を読めるようになりました。この経験はかなり大きかったです。
その後、英語力は少しずつですが着実に上がっていきました。特に印象的だったのは高3の秋です。それまでは要約演習で思うように筆者の主張が見抜けなくて、的外れなことに重点を置いてまとめてしまう状態が続いていましたが、自分の中で押さえるべきポイントが見えるようになったんです。模試の要約問題でも満点をとれるようになりました。
グノのやり方で学んでいれば、文法理解の上に、単語の力も身につきます。単語を語源から学んでいるから文脈の中で生き生きと捉えられるようになるんです。プレゼンみたいに長文を音読する経験を積み重ねてどこまででも英語力を伸ばせるような気がしました。
実際に、入試直前期にも伸びを感じられたので、その成長が本番に向かうときの心の支えになりました。
そもそも僕は、グノに入るまで英語を体系的に勉強したことがありませんでした。英文は主語述語の順番に並ぶということや、動詞が目的語をとる・とらないといったことも知らず、ただ単語が並んでいるだけの英文をどう読んだらいいかがわかっていませんでした。
そんな状態から、グノで英語の仕組みをひとつずつ教わり英文を読めるようになりました。この経験はかなり大きかったです。
その後、英語力は少しずつですが着実に上がっていきました。特に印象的だったのは高3の秋です。それまでは要約演習で思うように筆者の主張が見抜けなくて、的外れなことに重点を置いてまとめてしまう状態が続いていましたが、自分の中で押さえるべきポイントが見えるようになったんです。模試の要約問題でも満点をとれるようになりました。
グノのやり方で学んでいれば、文法理解の上に、単語の力も身につきます。単語を語源から学んでいるから文脈の中で生き生きと捉えられるようになるんです。プレゼンみたいに長文を音読する経験を積み重ねてどこまででも英語力を伸ばせるような気がしました。
実際に、入試直前期にも伸びを感じられたので、その成長が本番に向かうときの心の支えになりました。
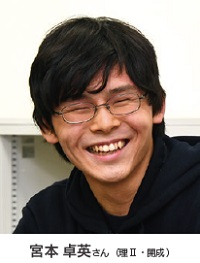
宮本:
僕は中1からグノに通っていましたが、真面目に取り組んでいなかったこともあって、伸びを実感するまでに時間がかかりました。
高3で毎週の要約演習が始まり、それまでは表面的に読めていただけで、実は深くまではわかっていなかったということがはっきりして、そこから本気になって取り組み始めました。
段落ごとに言いたいことがすっきりわかるようになったのは、僕も庄司君と同じで高3の秋になってからです。
高3で毎週の要約演習が始まり、それまでは表面的に読めていただけで、実は深くまではわかっていなかったということがはっきりして、そこから本気になって取り組み始めました。
段落ごとに言いたいことがすっきりわかるようになったのは、僕も庄司君と同じで高3の秋になってからです。
西:
グノには高1から通い始めていましたが、偏差値が大きく上がったのは高2の後半に学校で模試を受けたときでした。長文読解が好成績で、長い英文をしっかり読めるようになったのは、グノで興味の持てる英文をたくさん読めたからです。
高3の受験直前期にもうれしいことがありました。高3に入ってからは全然できない理科に勉強時間を費やしてしまい、得意な英語は後回しになりがちでした。英語の勉強は続けていましたが、自分で英語力の伸びを実感するほどのことはありませんでした。でも、直前期に過去問の添削をお願いしたとき、先生からうれしいコメントをいただけました。1年間見ていただいてきた先生からのコメントなので自信になりました。
東大受験の1日目の国語は、できたのかどうか自分でもわからない結果でした。数学は、「この問題は解けないといけない」と思う問題がいくら考えても解けませんでした。解答用紙が回収されているとき、その問題の解答欄が真っ白な人は私以外にひとりしかいなくて、1日目の試験の帰りは落ち込みました。
でも、2日目は私が一番好きな英語だったので、「英語で絶対挽回してやる」と諦めませんでした。最終的には無事、東大に合格できましたが、英語に救われたと思います。
高3の受験直前期にもうれしいことがありました。高3に入ってからは全然できない理科に勉強時間を費やしてしまい、得意な英語は後回しになりがちでした。英語の勉強は続けていましたが、自分で英語力の伸びを実感するほどのことはありませんでした。でも、直前期に過去問の添削をお願いしたとき、先生からうれしいコメントをいただけました。1年間見ていただいてきた先生からのコメントなので自信になりました。
東大受験の1日目の国語は、できたのかどうか自分でもわからない結果でした。数学は、「この問題は解けないといけない」と思う問題がいくら考えても解けませんでした。解答用紙が回収されているとき、その問題の解答欄が真っ白な人は私以外にひとりしかいなくて、1日目の試験の帰りは落ち込みました。
でも、2日目は私が一番好きな英語だったので、「英語で絶対挽回してやる」と諦めませんでした。最終的には無事、東大に合格できましたが、英語に救われたと思います。
■グノーブルの数学
数学の授業の印象はどうだったでしょうか?
1回解いた問題を深く深く掘り下げていくグノのやり方の積み重ねで、「一番楽しく勉強できるのも、受験で武器にできるのも数学だ」という気持ちになりました
庄司:
数学は高2から受講しました。
僕は小学生の頃、パズルチックな算数はとても得意でした。でも、中学で数学の勉強をサボり続けたので、知識の活かし方がわからなくなりました。数学は嫌いではないし、「やればできるんだろう」と思っていましたが、実際には全然できませんでした。模試で問題を見ても最初のとっかかりが見つけられないんです。答えを見れば「ああ、そうか」となるんですけれど……。ですから、点数的にはどう見ても数学が「苦手科目」になっていました。
そんな壊滅的な状況でグノの数学に通い始めましたが、先生が褒め上手で、僕はすぐにやる気になりました。少人数制で先生が一人ひとりをよく見てくださるので、早い段階で点数もとれるようになって、クラスも上がりました。
上のクラスでも、先生が一人ひとりをしっかり見てくださるのは同じでした。僕が「こういう問題は、計算が多くてやる気が出ません」という甘えたことを訴えても、先生は僕に合わせて的確に導いてくれました。
数学の各単元を日本語で分析して、自覚的に道具の使い方を把握していくグノのスタイルは僕にはぴったりでした。問題を解きっぱなしにすることなく、1回解いた問題を深く深く掘り下げていくグノのやり方の積み重ねで、「一番楽しく勉強できるのも、受験で武器にできるのも数学だ」という気持ちになりました。
東大受験では、理系の場合は数学の比率が大きく、合格発表を見る前に、数学の出来不出来で合否がわかってしまいます。本番では数学が面白いように解けました。1日目でアドバンテージをとれたので、2日目は「ちょっとくらい失敗しても大丈夫」と、楽な気持ちで臨めました。
僕は小学生の頃、パズルチックな算数はとても得意でした。でも、中学で数学の勉強をサボり続けたので、知識の活かし方がわからなくなりました。数学は嫌いではないし、「やればできるんだろう」と思っていましたが、実際には全然できませんでした。模試で問題を見ても最初のとっかかりが見つけられないんです。答えを見れば「ああ、そうか」となるんですけれど……。ですから、点数的にはどう見ても数学が「苦手科目」になっていました。
そんな壊滅的な状況でグノの数学に通い始めましたが、先生が褒め上手で、僕はすぐにやる気になりました。少人数制で先生が一人ひとりをよく見てくださるので、早い段階で点数もとれるようになって、クラスも上がりました。
上のクラスでも、先生が一人ひとりをしっかり見てくださるのは同じでした。僕が「こういう問題は、計算が多くてやる気が出ません」という甘えたことを訴えても、先生は僕に合わせて的確に導いてくれました。
数学の各単元を日本語で分析して、自覚的に道具の使い方を把握していくグノのスタイルは僕にはぴったりでした。問題を解きっぱなしにすることなく、1回解いた問題を深く深く掘り下げていくグノのやり方の積み重ねで、「一番楽しく勉強できるのも、受験で武器にできるのも数学だ」という気持ちになりました。
東大受験では、理系の場合は数学の比率が大きく、合格発表を見る前に、数学の出来不出来で合否がわかってしまいます。本番では数学が面白いように解けました。1日目でアドバンテージをとれたので、2日目は「ちょっとくらい失敗しても大丈夫」と、楽な気持ちで臨めました。
■グノーブルの国語
国語の授業はどうだったのでしょうか?
グノで現代文を教わったあとは、文の読み方、楽しみ方がわかり、最終的に抵抗感もなくなりました
西:
中3のときは国語が全然できなくて、特に古文はわけがわかりませんでした。模試を受けても、古文は壊滅的でした。
でも、高1でグノの古文を受講したら、古文が得意になり、中3のとき偏差値35 くらいだった国語が、高1では偏差値70 にまでなりました。
でも、高1でグノの古文を受講したら、古文が得意になり、中3のとき偏差値35 くらいだった国語が、高1では偏差値70 にまでなりました。
宮本:
僕はもともと学校で古文・漢文にきちんと取り組んでいて得意でした。「もっと伸ばそう」という気持ちでグノの国語を受講したおかげで、国語に全く触れない時期があっても成績を維持できました。
西:
高1で古文の通常授業を受講したあとも、グノの講習で国語をとっていました。
私はもともと本を読むのが嫌いでした。日本語の長い文章を見るとウワッとなってしまうほどだったので、読む気にもなりませんでした。
でも、グノで現代文を教わったあとは、文の読み方、楽しみ方がわかり、最終的に抵抗もなくなりました。今ではちゃんと読書を楽しめます。中3までの状態のままだったらと思うとぞっとします。本当にグノの国語に通って良かったです。
私はもともと本を読むのが嫌いでした。日本語の長い文章を見るとウワッとなってしまうほどだったので、読む気にもなりませんでした。
でも、グノで現代文を教わったあとは、文の読み方、楽しみ方がわかり、最終的に抵抗もなくなりました。今ではちゃんと読書を楽しめます。中3までの状態のままだったらと思うとぞっとします。本当にグノの国語に通って良かったです。
■グノーブルの先生
先生方はどのように皆さんの勉強と関わってくれましたか?
先生が私たちの名前を呼んでくださるので、授業が一方的にならず、とても集中できました
庄司:
グノの先生は、生徒一人ひとりにちゃんと目を向けて話をしてくれます。だから解説のとき、ときどき先生と目が合います。先生の質問に対して「わかるよ」という顔をしているとちゃんとあてて答えさせてくれることもあります。
質問に答えられないときにも、「じゃあこれは?」と答えられる別の質問に切り替えて、僕たちが推測したり思い出したりできるようにしてくれます。
いつの間にかアクティブに参加している授業の場を先生がつくってくださるので、グノでは授業中に寝るなんてことが全くありません。
質問に答えられないときにも、「じゃあこれは?」と答えられる別の質問に切り替えて、僕たちが推測したり思い出したりできるようにしてくれます。
いつの間にかアクティブに参加している授業の場を先生がつくってくださるので、グノでは授業中に寝るなんてことが全くありません。
平山:
先生がすぐに生徒の名前を覚えてくださることだけでも感動しました。先生が私たちの名前を呼んでくださるので、授業が一方的にならず、とても集中できました。
それから高2のとき、たまたま塾に寄ったら、先生から「修学旅行どうだった?」と聞かれてびっくりしたのも覚えています。先生が私たちのことを見てくれていて、関心を持っていてくださると安心できるし、やる気もおきます。
それから高2のとき、たまたま塾に寄ったら、先生から「修学旅行どうだった?」と聞かれてびっくりしたのも覚えています。先生が私たちのことを見てくれていて、関心を持っていてくださると安心できるし、やる気もおきます。
西:
グノで初回の授業を受けたとき、先生がすぐにみんなの名前を覚えてくださったのには私も驚きました。先生に親近感を覚えました。
授業前も授業後も先生とよく世間話をしていましたが、会話を通して先生との信頼関係を築けたと思います。とても楽しかったです。
授業前も授業後も先生とよく世間話をしていましたが、会話を通して先生との信頼関係を築けたと思います。とても楽しかったです。
宮本:
グノの先生は、本当に名前をすぐに覚えてくれますよね。例えば、講習でお世話になっただけの先生でも、座席表にメモした名前を読み上げるだけでなく、次の日には全員の名前を完全に覚えてきてくださっていました。「親身になってくれているんだ」と実感しました。
庄司:
高3になって最初の授業で、僕は一番前の席に座っていて衝撃を受けました。
英語のクラスには30 人ぐらいの生徒がいて、先生はご自身が作った座席表の紙を机の上に置いていましたが、解説が始まったときにはその座席表を全然見ていないんです。それなのにどの生徒も名前で呼んでいて、本当に上から目線の言い方になりますが、「この人教師としての能力高すぎだろ!」と思いました。そして、「この先生の言うことを全部聞こう」という気持ちになりました。
英語のクラスには30 人ぐらいの生徒がいて、先生はご自身が作った座席表の紙を机の上に置いていましたが、解説が始まったときにはその座席表を全然見ていないんです。それなのにどの生徒も名前で呼んでいて、本当に上から目線の言い方になりますが、「この人教師としての能力高すぎだろ!」と思いました。そして、「この先生の言うことを全部聞こう」という気持ちになりました。
■グノーブルの環境
学習環境の面でグノーブルの良いところを教えてください
教室が綺麗ですよね。そのおかげで勉強にも集中できて快適でした
平山:
とにかく受付の方が優しくて、振替などの相談をしても、親切に丁寧に答えてくださるのが印象的でした。私は電話がとても苦手なのですが、電話でも受付の方がとても丁寧で怖さがなく、話しやすかったです。
西:
私も、受験直前期に振替が多くなってスケジュールがぐちゃぐちゃになりましたが、受付の方が1回で「わかりました」と対応してくださって助かりました。受付の方は全員、優しくてフレンドリーな雰囲気で良かったです。
それから、建物の入口にいつも立っている警備員さんも「こんにちは」と挨拶してくださって、そのおかげで「今日もがんばろう」と思えました。
それから、建物の入口にいつも立っている警備員さんも「こんにちは」と挨拶してくださって、そのおかげで「今日もがんばろう」と思えました。
宮本:
受付の方はいつも感じ良く僕たちを迎えてくださってうれしかったです。警備員さんは自習室を利用している人の様子を見に来てくださることもあって、塾生の安全を考えているのが伝わってきました。
庄司:
グノは教室がきれいですよね。そのおかげで勉強にも集中できて、快適でした。
■後輩へのアドバイス
これから受験する後輩に向けて一言お願いします
東大の入試問題には、グノっぽいところがあります
宮本:
グノの先生の言うことをきちんと聞いて、音読と音声教材にはしっかり取り組んでください。
平山:
東大は変な問題を出してこないので、基本を大事にしてください。
宮本君の言う通り、グノの先生の言うことをきちんと実行することが大事です。
どのタイミングでも、そのときにやるべきことがあるので、それを着実にこなしましょう。
宮本君の言う通り、グノの先生の言うことをきちんと実行することが大事です。
どのタイミングでも、そのときにやるべきことがあるので、それを着実にこなしましょう。
庄司:
東大の入試問題には、グノっぽいところがあります。
持っている知性が問われるというか、本質的な問題が多くて、知に対する誠意を東大は汲み取ってくれるのだと思います。
だから、グノで与えられる英語の音読や数学のセルフチェックシートに取り組むだけでなく、「先生はこの問題を出すことで何を求めているのかな?」ということを意識して勉強するといいですね。
持っている知性が問われるというか、本質的な問題が多くて、知に対する誠意を東大は汲み取ってくれるのだと思います。
だから、グノで与えられる英語の音読や数学のセルフチェックシートに取り組むだけでなく、「先生はこの問題を出すことで何を求めているのかな?」ということを意識して勉強するといいですね。
西:
最後まで絶対に諦めないでください。私はセンター試験も、東大入試1日目も、2日目の前半も出来があまり良くなくて、少し落ち込みました。でも、「絶対に諦めたくない」という気持ちで最後までやり切りました。
英語の読解の先生が何度も、「絶対に諦めないでね」とおっしゃっていました。そういう言葉を繰り返し聞いていたので、「少しくらい失敗しても大丈夫」と思えました。合格できたのは先生の言葉のおかげです。
英語の読解の先生が何度も、「絶対に諦めないでね」とおっしゃっていました。そういう言葉を繰り返し聞いていたので、「少しくらい失敗しても大丈夫」と思えました。合格できたのは先生の言葉のおかげです。