東京大学理系 Part 1
ホーム > Gno-let > Gno-let23 > 東京大学 理系 Part1
| 大村 幹さん(理Ⅱ・都立小石川中等教育) | 小坂 七海さん(理Ⅰ・駒場東邦) |
| 齋藤 勇真さん(理Ⅰ・開成) | 椎名 昭斗さん(理Ⅱ・駒場東邦) |
| 嶋田 遼祐さん(理Ⅰ・駒場東邦) | 辻 春樹さん(理Ⅰ・駒場東邦) |
| 中山 崇さん(理Ⅰ・早稲田) | |
■入塾のきっかけ
なぜグノーブルを選んだのでしょうか?
映像授業でも大教室の授業でもなく、先生が本当に熱心に授業をしてくれるのが気に入りました
中山:
高2の冬期講習から通い始めました。友人からは「グノは先生がフレンドリーに接してくれる」と聞いていました。
他塾との比較もしましたが、グノの方が英語のレベルが高く、受験勉強にとどまらないという点で好印象でした。
講習の授業が気に入り、数学も受講することにしました。
他塾との比較もしましたが、グノの方が英語のレベルが高く、受験勉強にとどまらないという点で好印象でした。
講習の授業が気に入り、数学も受講することにしました。
辻:
グノを熱烈に支持していた友人から「グノがいい」と何度も聞かされたことがきっかけで、高2のとき、とりあえず夏期講習を受けてみたら、友人の話通りに良くて入塾を決めました。
映像授業でも大教室の授業でもなく、先生が本当に熱心に授業をしてくださるのが気に入り、英語と数学に通い始めました。
映像授業でも大教室の授業でもなく、先生が本当に熱心に授業をしてくださるのが気に入り、英語と数学に通い始めました。
小坂:
高1のときに受けた模試で英語の偏差値が50 を割っていて、「英語を勉強しないと」と思い、塾を探しました。
他塾に通う友達は学校で塾の宿題をしている人が多く、それをやったら英語が嫌いになりそうな気がして、宿題の多い塾は避けました。ひたすら単語を覚えたり、構文の解析をするだけの授業も、言葉として死んでいるようで嫌でした。
友達が「グノでは英語を英語のまま読むし、単語を語源から推測する」と言っていたのに心惹かれました。実際にグノの授業を受けて、友達の言う通りだったので入塾を決めました。
高1の秋に英語で入塾して、高2から物理を受講しました。
他塾に通う友達は学校で塾の宿題をしている人が多く、それをやったら英語が嫌いになりそうな気がして、宿題の多い塾は避けました。ひたすら単語を覚えたり、構文の解析をするだけの授業も、言葉として死んでいるようで嫌でした。
友達が「グノでは英語を英語のまま読むし、単語を語源から推測する」と言っていたのに心惹かれました。実際にグノの授業を受けて、友達の言う通りだったので入塾を決めました。
高1の秋に英語で入塾して、高2から物理を受講しました。

大村:
高1の春に入塾し英語と数学を受講しました。漠然と「東大に行きたい」と考えていて、高校生になった段階で「塾に入ろう」と思っていましたが、大手予備校だと先生ではなくチューターとやり取りしなければなりません。僕はチューターと仲良くなるよりも、先生と親密になりたかったんです。
グノは先生との距離が近いと聞いていたのが決め手でした。
グノは先生との距離が近いと聞いていたのが決め手でした。
椎名:
中3の秋に入塾しました。バンド仲間が誘ってくれて、「とりあえず行ってみよう」となったのがきっかけです。
「グノの英語は受験が終わったあとでも使える」と聞いていて、そこにも魅力を感じました。
僕は部活を一生懸命やっていたので、塾の宿題で時間を費やされるのが嫌でした。だから、宿題が多い塾には絶対に通いたくありませんでした。
「グノの英語は受験が終わったあとでも使える」と聞いていて、そこにも魅力を感じました。
僕は部活を一生懸命やっていたので、塾の宿題で時間を費やされるのが嫌でした。だから、宿題が多い塾には絶対に通いたくありませんでした。
齋藤:
僕は中3の冬に入りました。
所属していたソフトテニス部の部長が、部活や学校行事と勉強を両立していて、模試でも良い成績でした。その部長が通っていたのがグノでした。
グノより歴史の長い他塾とどちらにしようか少しだけ悩みましたが、スケジュール的に厳しい塾に入るよりも、自分のペースで伸び伸び勉強できるグノの方が合っていると思いました。
所属していたソフトテニス部の部長が、部活や学校行事と勉強を両立していて、模試でも良い成績でした。その部長が通っていたのがグノでした。
グノより歴史の長い他塾とどちらにしようか少しだけ悩みましたが、スケジュール的に厳しい塾に入るよりも、自分のペースで伸び伸び勉強できるグノの方が合っていると思いました。
嶋田:
僕も中3の冬期講習の英語からグノに通い始めました。
東大や一橋大に合格した先輩全員がグノに通っていて、「グノはいい」と勧めてくれました。その下の先輩たちもグノ率が高くて、「グノは良い塾なんだろうな」とぼんやり思っていました。
他塾に通っている友達は塾中心の受験勉強ばかりになっていて、塾で教わっていない国語や社会が全然できないとか、学校の授業の実験をサボってレポートも出さないとか、学校生活がおろそかになっていました。
それを見ていた僕は「塾と学校の両立が大切だ」と思っていたので、グノに魅力を感じました。実際に講習を受けてみて雰囲気を確認して入塾しました。
東大や一橋大に合格した先輩全員がグノに通っていて、「グノはいい」と勧めてくれました。その下の先輩たちもグノ率が高くて、「グノは良い塾なんだろうな」とぼんやり思っていました。
他塾に通っている友達は塾中心の受験勉強ばかりになっていて、塾で教わっていない国語や社会が全然できないとか、学校の授業の実験をサボってレポートも出さないとか、学校生活がおろそかになっていました。
それを見ていた僕は「塾と学校の両立が大切だ」と思っていたので、グノに魅力を感じました。実際に講習を受けてみて雰囲気を確認して入塾しました。
■学校生活と塾の両立
忙しい日常の中で学校と塾を両立させるために、どんな工夫をしていましたか?
部活や行事を抱えてプレッシャーある中でも、グノの勉強は楽しかったし、効率良く力をつけられました。僕が知る限り、塾の中ではグノが一番両立しやすかったと思います
中山:
確かに他塾に通っている人の中には塾だけに追われている人もいて、自分はそうはなりたくありませんでした。
辻:
学校と受験勉強の両立は塾によっては難しいと思います。駒東は体育祭が盛り上がるので、2~3週間勉強できない時期があります。
グノはそういう学校の事情に配慮してくれるので両立できる環境でした。
グノはそういう学校の事情に配慮してくれるので両立できる環境でした。
嶋田:
中学受験を自分なりにがんばって、駒東に入ったので「高2の夏の引退までは部活をやりたい」と心に決めていました。真剣に何かに打ち込んだ人は、受験勉強にも打ち込めると思います。
グノには夜の7時過ぎから始まる授業の設定もあるし、振替制度もあります。先生方も学校生活に打ち込む人を応援してくれます。僕みたいに部活をやりたい人たちには一番合っている塾だと思います。
グノには夜の7時過ぎから始まる授業の設定もあるし、振替制度もあります。先生方も学校生活に打ち込む人を応援してくれます。僕みたいに部活をやりたい人たちには一番合っている塾だと思います。
椎名:
僕も部活を本気でやっていましたし、高2の秋に引退したあともバンド活動を続けていました。周りの人たちよりも時間がない状態で、受験勉強のスタートも遅れました。
そんな僕でも、グノに通っていたおかげで、バンドに打ち込みながらも英語の地力がつきました。本格的に勉強を始めた高3ですぐに英語の成績が上がったのは両立の成果です。
そんな僕でも、グノに通っていたおかげで、バンドに打ち込みながらも英語の地力がつきました。本格的に勉強を始めた高3ですぐに英語の成績が上がったのは両立の成果です。
大村:
僕も高3の5月まで部活をやっていました。高3の夏休みは、9月の行事のために毎日学校に通って準備をしていて、10 月の模試は壊滅的でした。必ずしも両立できていたとは言えないのかもしれませんが、グノには楽しく通っていたので結果として効率良く効果的な勉強ができたように思います。
小坂:
行事だけでなく、グノでは学校の授業とも両立できました。
グノで教わっていた英語と物理以外は全部自分で勉強していて、学校の宿題をすべて消化しつつ、グノの宿題を同時にこなしていました。
グノの宿題は量が少ないのでうまく消化できました。授業の復習もしていましたが、そもそもグノの英語の復習は音読なので楽しくて全然苦になりませんでした。
グノで教わっていた英語と物理以外は全部自分で勉強していて、学校の宿題をすべて消化しつつ、グノの宿題を同時にこなしていました。
グノの宿題は量が少ないのでうまく消化できました。授業の復習もしていましたが、そもそもグノの英語の復習は音読なので楽しくて全然苦になりませんでした。
齋藤:
僕はもともと勉強よりも部活や行事に時間を割きたかったんです。
でも、嫌々勉強に時間を割いたわけではなくて、部活や行事を抱えてプレッシャーがある中でも、グノの勉強は楽しかったし、効率良く力をつけられました。僕が知る限り、塾の中ではグノが一番両立しやすかったと思います。
でも、嫌々勉強に時間を割いたわけではなくて、部活や行事を抱えてプレッシャーがある中でも、グノの勉強は楽しかったし、効率良く力をつけられました。僕が知る限り、塾の中ではグノが一番両立しやすかったと思います。
■グノーブルの評判
学校ではグノーブルに通っていた生徒は多かったのでしょうか?
敬遠する人もいましたが、大学に進んでも必ず財産になるグノの授業こそが受験界の新しい標準だと思っています
大村:
「英語がとても強い」と評判でした。僕は「数学も強いんだよ」とプッシュしていました。

小坂:
駒東でも「英語がいい」という声が多いです。僕は「物理もすごいよ」と言っていました。
椎名:
「英語がいい」という評判はその通りですが、グノに通っていてもグノの勉強をしなければ成績は上がらないと思います。成績は下の方でスタートしても、グノの教材を全部吸収するくらいの気概がある人たちはトップレベルまでどんどん成績を上げていました。
嶋田:
「グノに通えば英語ができるようになる」ではなくて、「グノのやり方できちんと勉強をすれば英語ができるようになる」という点を強調しないと、勘違いする人が出てきますね。
中山:
早稲田の中では塾の話はあまりしないのですが、グノに通う人たちは、みんなグノが気に入っていて「良い塾だよね」と言い合っていました。グノの先生の話やグノの英文に関する話題で盛り上がることもしばしばありました。

齋藤:
英語も数学も受験常識にとらわれない授業をする。これが僕のグノに対する一番の印象です。
英語は音読での復習や単語帳を暗記しない単語の覚え方など独特です。数学の自分と向き合うセルフチェックシートは他では聞いたことがありません。どちらも、受験界の常識ではあり得ないことなのかもしれません。
グノを経験したことがない人の中には、グノのそういう特殊な部分に不安を感じて敬遠する人もいました。でも、飛び込んでみるとすごく面白い塾で、大事なことをたくさん学べました。大学に進学しても必ず財産になるグノの授業こそが受験界の新しい標準だと思っています。
英語は音読での復習や単語帳を暗記しない単語の覚え方など独特です。数学の自分と向き合うセルフチェックシートは他では聞いたことがありません。どちらも、受験界の常識ではあり得ないことなのかもしれません。
グノを経験したことがない人の中には、グノのそういう特殊な部分に不安を感じて敬遠する人もいました。でも、飛び込んでみるとすごく面白い塾で、大事なことをたくさん学べました。大学に進学しても必ず財産になるグノの授業こそが受験界の新しい標準だと思っています。
■グノーブルの英語
英語の授業はどんな雰囲気だったのか教えてください。
先生の熱意にも気持ちを動かされ「自分も勉強しよう」と思えて勉強に取り組んだので、英語の伸びがすさまじかったです
大村:
「素晴らしい!」のひと言です。
高1の春から入塾しましたが、初回に読んだのが宇宙人に関する英文で、本当に面白かったのをよく覚えています。グノの授業で扱う英文は、勉強のためのありきたりな英文ではなくて、僕たちが興味を持てる新鮮な英文を先生たちが探して用意してくださるんです。
英単語の説明も、初めて聞いたときは「これはすごい」と感動しました。難解な語も先生が語源に立ち返って説明してくださると、単なるアルファベットの羅列から顔なじみにどんどん変わっていきました。ある単語から同じ語根を持った派生語へと、黒板上でどんどん展開されていく様子はまるで手品でした。
先生の熱意にも気持ちを動かされました。「自分も勉強しよう」と思えたので、実際に取り組み始めてからの、英語の伸びはすさまじかったです。高1のときに受けた全国模試では英語は1桁の順位でした。もともと英語は好きでしたが、グノに入ってさらに面白くなりました。
高1の春から入塾しましたが、初回に読んだのが宇宙人に関する英文で、本当に面白かったのをよく覚えています。グノの授業で扱う英文は、勉強のためのありきたりな英文ではなくて、僕たちが興味を持てる新鮮な英文を先生たちが探して用意してくださるんです。
英単語の説明も、初めて聞いたときは「これはすごい」と感動しました。難解な語も先生が語源に立ち返って説明してくださると、単なるアルファベットの羅列から顔なじみにどんどん変わっていきました。ある単語から同じ語根を持った派生語へと、黒板上でどんどん展開されていく様子はまるで手品でした。
先生の熱意にも気持ちを動かされました。「自分も勉強しよう」と思えたので、実際に取り組み始めてからの、英語の伸びはすさまじかったです。高1のときに受けた全国模試では英語は1桁の順位でした。もともと英語は好きでしたが、グノに入ってさらに面白くなりました。
小坂:
グノは単語を語源で覚えるのを特徴にしています。その方針が先生たち全員で共有されていたので勉強しやすかったです。
僕は最初、あまりグノを信用していなくて市販の単語帳をやっていました。でも、グノの覚え方の方が圧倒的に楽しく単語を吸収できたので、途中から単語帳を使わなくなりました。
それから、先生が授業のために用意してくださる英文の中には、耳に残るフレーズや美しい文がいっぱいあって楽しく読めました。受験のための塾なので和訳もしますが、単語の並んでいる順番に訳していくので、英語を前から読んでいく習慣を確立するのに役立ちました。
毎週その場で添削もしてもらえるので、自分では気づかない間違いをすぐに自分の力に変えていくことができました。
僕は最初、あまりグノを信用していなくて市販の単語帳をやっていました。でも、グノの覚え方の方が圧倒的に楽しく単語を吸収できたので、途中から単語帳を使わなくなりました。
それから、先生が授業のために用意してくださる英文の中には、耳に残るフレーズや美しい文がいっぱいあって楽しく読めました。受験のための塾なので和訳もしますが、単語の並んでいる順番に訳していくので、英語を前から読んでいく習慣を確立するのに役立ちました。
毎週その場で添削もしてもらえるので、自分では気づかない間違いをすぐに自分の力に変えていくことができました。
中山:
毎回添削してもらえる授業システムは本当に良かったと思います。要約も作文もその場で添削してもらえるので、漠然と英文を読んで問題にあたり、ただ解説を聞きながらメモしていく勉強にならずにすみました。
それに、授業は先生と生徒がやり取りしながら進んでいくので、なおさら授業中の集中はとぎれることがありませんでした。だから、グノの教室の中で流れる時間はあっという間なんです。
僕は「英語ができる人の頭の中を理解したい」と思っていました。この点、グノの先生は英語が堪能だし、英語ができるようになるメソッドや意識の持ち方を言語化してくださるし、授業のいろいろな場面で態度で示してくださるので、とても参考になりました。
筆者がどういう気持ちで英文を書いたのかも、先生の解説で理解できることが多く、英文の内容に深く踏み込む習慣ができました。
単語に関しても、ネイティブが未知の単語を見て意味を推測できるのと同じように、語源から解説してもらえたのが印象的でした。
それに、授業は先生と生徒がやり取りしながら進んでいくので、なおさら授業中の集中はとぎれることがありませんでした。だから、グノの教室の中で流れる時間はあっという間なんです。
僕は「英語ができる人の頭の中を理解したい」と思っていました。この点、グノの先生は英語が堪能だし、英語ができるようになるメソッドや意識の持ち方を言語化してくださるし、授業のいろいろな場面で態度で示してくださるので、とても参考になりました。
筆者がどういう気持ちで英文を書いたのかも、先生の解説で理解できることが多く、英文の内容に深く踏み込む習慣ができました。
単語に関しても、ネイティブが未知の単語を見て意味を推測できるのと同じように、語源から解説してもらえたのが印象的でした。

椎名:
以前は「英語は覚えるだけの暗記科目で何が楽しいんだろう?」と思い、受験科目としての英語は嫌いでした。英文の筆者は一語一語を選んで工夫して書いているはずですが、他塾はそこに重きを置かず、「受験で勝つためにはこう解けばいい」という点ばかり強調しているように思います。僕は「それは違う」と感じていました。
グノの授業は、筆者の主張を理解し、筆者の表情が見えて息づかいがわかるぐらいまで深く読むことを大切にします。
しかも、いろいろな分野の英文が教材になっているから、いろいろな人の考えや気持ちを知ることができます。研究論文もあれば、勉強に対する基本姿勢について書かれたエッセイもあったし、経済に関するニュースもありました。
外国人が書いた文章には日本人の感性との違いが表れていて、それも面白かったです。「受験におさまらない英語はこんなに面白いんだ」と実感できて、英語が好きになりました。
こうした文章の読み方は、受験で重要なだけでなく、日本語でも大事です。グノの授業を通して、僕は生き方の方向性もつかめた気がしています。
グノの授業は、筆者の主張を理解し、筆者の表情が見えて息づかいがわかるぐらいまで深く読むことを大切にします。
しかも、いろいろな分野の英文が教材になっているから、いろいろな人の考えや気持ちを知ることができます。研究論文もあれば、勉強に対する基本姿勢について書かれたエッセイもあったし、経済に関するニュースもありました。
外国人が書いた文章には日本人の感性との違いが表れていて、それも面白かったです。「受験におさまらない英語はこんなに面白いんだ」と実感できて、英語が好きになりました。
こうした文章の読み方は、受験で重要なだけでなく、日本語でも大事です。グノの授業を通して、僕は生き方の方向性もつかめた気がしています。
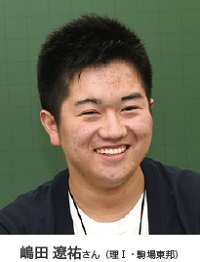
嶋田:
トピックがいっぱいあるのはその通りで、どんな英文に出会えるんだろうと毎週の授業が楽しみでした。
同じトピックでも真逆な内容が書かれている英文が授業で用意されることもあります。「こういう面から見ればこれは正しいけれど、こういう面から見ると正しくない」というのを意識するきっかけになりました。
例えば、アファーマティブ・アクションの話がありました。歴史的に差別されてきた性別や人種を優遇する制度がないと公平な社会は実現できません。でもそれが過剰になると逆差別になってしまいます。
このように対立する見解に触れることで、物事は一方的に見てはいけないと気づかされましたし、多面的な見方は、様々なトピックに応用できることにも気づけました。
深い教養や知の力が、身につくように促してくれるのがグノの授業です。
同じトピックでも真逆な内容が書かれている英文が授業で用意されることもあります。「こういう面から見ればこれは正しいけれど、こういう面から見ると正しくない」というのを意識するきっかけになりました。
例えば、アファーマティブ・アクションの話がありました。歴史的に差別されてきた性別や人種を優遇する制度がないと公平な社会は実現できません。でもそれが過剰になると逆差別になってしまいます。
このように対立する見解に触れることで、物事は一方的に見てはいけないと気づかされましたし、多面的な見方は、様々なトピックに応用できることにも気づけました。
深い教養や知の力が、身につくように促してくれるのがグノの授業です。
齋藤:
グノの授業で扱う英文のジャンルは幅広くて、クオリティも高く、時事ネタもよく扱われて新鮮です。そういう英文を骨に刻み込むまで読み込むのがグノの一番の特徴だと思います。
分厚いテキストはありません。毎週、授業ごとに英文が配られて、それを徹底的に味わいます。英語が並んでいるだけの教材は見た目はとてもシンプルですが、先生の解説がものすごく詳細でいろいろな発見があって楽しめます。冠詞が“a”なのか“the”なのかという指摘だけでも「おぉ!」と感動することがあります。英文の背景についての解説を聞いていると面白みがどんどん増します。
それを思い出しながら音読して復習していると理解が定着し、「完全に自分のものになった」と確信できるようになります。それを積み重ねれば、東大の入試に出てくる英文でも「大したことない」と思えるくらいまでレベルアップできました。
分厚いテキストはありません。毎週、授業ごとに英文が配られて、それを徹底的に味わいます。英語が並んでいるだけの教材は見た目はとてもシンプルですが、先生の解説がものすごく詳細でいろいろな発見があって楽しめます。冠詞が“a”なのか“the”なのかという指摘だけでも「おぉ!」と感動することがあります。英文の背景についての解説を聞いていると面白みがどんどん増します。
それを思い出しながら音読して復習していると理解が定着し、「完全に自分のものになった」と確信できるようになります。それを積み重ねれば、東大の入試に出てくる英文でも「大したことない」と思えるくらいまでレベルアップできました。
■グノーブルの音読
英語の指導では音読が重視されていますが、皆さんはどのように取り組みましたか?
理解するのが目的の黙読よりも、理解して人に伝えるまでが目標の音読の方が、より高度なトレーニングになります

辻:
音読が復習の中心にあるのもグノの特徴です。
他にも音読を勧めているところもありますが、「とにかく音読しろ」だけでノウハウがありません。
グノでは、音読するのは授業で扱った英文です。演習して添削を受けて解説もすぐにしてもらっていますから、深く理解できている英文で音読ができます。
その英文にはGSL*もありますからネイティブの発音で耳と口も鍛えられます。
その上でプレゼンをイメージしながら意味を意識して音読するようにと、やり方も細かく説明されています。
そういう音読をしていれば英語を語順のまま解釈できるようにもなるし、英語のリズムや流れも身につきます。単語も文章との関連で覚えられるので本当に単語帳要らずでした。
* GSL(Gnoble Sound Laboratory):中1から高3までの6学年すべてに毎週用意されているオリジナルの英語音声教材。
他にも音読を勧めているところもありますが、「とにかく音読しろ」だけでノウハウがありません。
グノでは、音読するのは授業で扱った英文です。演習して添削を受けて解説もすぐにしてもらっていますから、深く理解できている英文で音読ができます。
その英文にはGSL*もありますからネイティブの発音で耳と口も鍛えられます。
その上でプレゼンをイメージしながら意味を意識して音読するようにと、やり方も細かく説明されています。
そういう音読をしていれば英語を語順のまま解釈できるようにもなるし、英語のリズムや流れも身につきます。単語も文章との関連で覚えられるので本当に単語帳要らずでした。
* GSL(Gnoble Sound Laboratory):中1から高3までの6学年すべてに毎週用意されているオリジナルの英語音声教材。
嶋田:
グノのように復習として音読するという仕組みは他にはないと思います。
他塾だと毎週宿題をやっていき、授業で解説を聞くのが勉強の中心になりがちです。
そういう塾に通っている人たちに、「こういう英文を扱って面白かった」と言ってもなかなか伝わりません。そもそも授業で扱う英文が興味深いと思っている人がどれくらいいるのか疑問だし、先生もその英文や英文の背景の面白さを熱を込めて話すことはないようです。
グノだと「あの話面白かったよね」「そうだよね」と仲間内でも盛り上がれる楽しさがあります。そんなふうに、深く味わっている英文を音読するからこそ効果が高いのだと思います。
他塾だと毎週宿題をやっていき、授業で解説を聞くのが勉強の中心になりがちです。
そういう塾に通っている人たちに、「こういう英文を扱って面白かった」と言ってもなかなか伝わりません。そもそも授業で扱う英文が興味深いと思っている人がどれくらいいるのか疑問だし、先生もその英文や英文の背景の面白さを熱を込めて話すことはないようです。
グノだと「あの話面白かったよね」「そうだよね」と仲間内でも盛り上がれる楽しさがあります。そんなふうに、深く味わっている英文を音読するからこそ効果が高いのだと思います。
齋藤:
例えば「音読を1日30 分やりなさい」と言われてただ読んでいるだけだと、音読する意味がありません。単なる発音練習程度の効果しかないかもしれません。
グノの教材を使ってグノのやり方で音読を続けると、最終的には、目を左から右に動かせば一度で英文の内容が頭に入ってくる状態になります。
グノの教材を使ってグノのやり方で音読を続けると、最終的には、目を左から右に動かせば一度で英文の内容が頭に入ってくる状態になります。
小坂:
僕も毎日音読していて、「日本語を使わずに理解できた」という瞬間が段々と増えていきました。その積み重ねで英文を読むスピードも速くなりました。
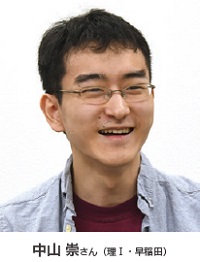
中山:
僕の場合、演習のときに難しさを感じた英文や、解説を受けて、自分が誤解して読んでいたことに気づかされた英文を選んで、1か月くらい連続で音読していました。課題の多かった英文の音読に絞ることで、自分がより成長できたように思います。
グノの先生は「プレゼンする気で音読しなさい」とおっしゃっていて、英文の意味と著者の気持ちの両方を把握するための音読という点を強調されていました。
ただ「音読しなさい」と言うのとは違って、音読のメソッドをきちんと教えていただけたので、機械的な音読にはなりませんでした。
グノの先生は「プレゼンする気で音読しなさい」とおっしゃっていて、英文の意味と著者の気持ちの両方を把握するための音読という点を強調されていました。
ただ「音読しなさい」と言うのとは違って、音読のメソッドをきちんと教えていただけたので、機械的な音読にはなりませんでした。
椎名:
僕も著者の気持ちになって毎日音読していました。「著者はどこを強調したかったのか?」を考えながら音読を続けていると、初めて読む英文でも「多分ここを強調したいんだろうな」という感覚が培われます。
辻:
音読をしていると黙読とは違う気づきがあります。授業の解説を聞いて理解していたつもりの英文が、実は理解していなかったことが判明する場合もあります。5回目の音読でわかっていたつもりのことが、10 回目でわかっていなかったことに気づくときもありました。
繰り返し読むことで自分の理解の範囲を把握して、その浅さを補っていけるのが、僕にとっては音読のメリットでした。
繰り返し読むことで自分の理解の範囲を把握して、その浅さを補っていけるのが、僕にとっては音読のメリットでした。
嶋田:
授業中に解説を聞いて、そのときはわかった気になっているけれど、著者の気持ちにまではなかなか踏み込めません。
音読を繰り返すと、「この人は、こういうことを言いたいから、この表現を使ったんだ」などとわかってきて、自分が著者になった気分で読めるようになります。
その結果、英文を読んで理解するのが速くなりました。読解のスピードだけでなく、リスニングの力も伸びました。僕はリスニング対策をしていませんでしたが、GSL を使って毎日音読していたら、音が自分の中に染みつきました。他の人がリスニングで聞き取れなかった単語でも、僕は聞き取れることが多くなりました。
音読を繰り返すと、「この人は、こういうことを言いたいから、この表現を使ったんだ」などとわかってきて、自分が著者になった気分で読めるようになります。
その結果、英文を読んで理解するのが速くなりました。読解のスピードだけでなく、リスニングの力も伸びました。僕はリスニング対策をしていませんでしたが、GSL を使って毎日音読していたら、音が自分の中に染みつきました。他の人がリスニングで聞き取れなかった単語でも、僕は聞き取れることが多くなりました。
大村:
黙読は「書かれている文章を吸収しよう」という姿勢で読むけれど、音読は「書かれている内容を人に伝えよう」という姿勢で読むことになると思います。理解するのが目的の黙読よりも、理解して人に伝えるまでが目標の音読の方が、より高度なトレーニングになります。
■英語の力が伸びた時期
普段の努力が成績の向上として実感できたのはいつ頃からだったのでしょうか?
入試本番です。プレッシャーがかかっている状態で最後に残っている問題に突撃したのですが、今まで感じたことに無いスピードで英語を読めたんです
大村:
グノに入ってから数か月後にガーッと成績が上がりました。それまでは、英語が好きでも標準的な成績でしたが、一気に伸びてグノの効果を実感しました。
グノの英語は面白いから、何回も目を通しているうちに自然と定着します。ネイティブが英文を作るときの考え方や単語の意味もいつの間にか覚えていて、必死になって勉強したわけでもないのに伸びていました。
グノの英語は面白いから、何回も目を通しているうちに自然と定着します。ネイティブが英文を作るときの考え方や単語の意味もいつの間にか覚えていて、必死になって勉強したわけでもないのに伸びていました。
小坂:
伸びた時期は2回ありました。
1回目は僕も大村君と同じで、高1の秋に入塾して数か月後に、試験の成績がアップしました。それまで英語が嫌いで苦手でしたが、英語で点をとれるようになり、英語が主戦力になってくれました。
英語が嫌いだったときは英語に向き合うのが嫌で目を背けていました。でも、グノに入ってからは、毎日英語と対話するようになって、着実に結果がついてきました。そして、英語の成績が上がれば上がるほど自分から英語と向き合いたくなって、自然と大好きになっていました。
もう1回が高3の12 月です。「椅子の上に立ってプレゼンしているつもりで音読してみよう。そうすれば全体が見えてくるよ」と先生がおっしゃっていて、それをやってみたら、本当に英文の全体を見渡せるようになったんです。人に効果的に伝えられる読み方になって、成績の伸びにもつながりました。
1回目は僕も大村君と同じで、高1の秋に入塾して数か月後に、試験の成績がアップしました。それまで英語が嫌いで苦手でしたが、英語で点をとれるようになり、英語が主戦力になってくれました。
英語が嫌いだったときは英語に向き合うのが嫌で目を背けていました。でも、グノに入ってからは、毎日英語と対話するようになって、着実に結果がついてきました。そして、英語の成績が上がれば上がるほど自分から英語と向き合いたくなって、自然と大好きになっていました。
もう1回が高3の12 月です。「椅子の上に立ってプレゼンしているつもりで音読してみよう。そうすれば全体が見えてくるよ」と先生がおっしゃっていて、それをやってみたら、本当に英文の全体を見渡せるようになったんです。人に効果的に伝えられる読み方になって、成績の伸びにもつながりました。
齋藤:
僕も2回伸びを実感しました。
1回目が高1です。中3の夏休みに他の予備校でセンター試験レベルの模試を受けて全然解き終わらず、「ヤバイ」と危機感を抱いて猛勉強しました。高1の夏休みにも同じ模試を受けたら、50 分で終わって30 分も余りました。「来たな、コレ!」という手応えがあってとてもうれしかったです。
2回目は東大入試本番です。当日の僕は、英作文に時間をかけすぎてピンチに陥りました。プレッシャーがかかっている状況で最後に残っている問題に突入したのですが、それは3ページにも及ぶ長い英文を読まなくてはいけない空所補充の問題でした。このとき、日本語は脳のどこにもない状態で、今まで感じたことがないスピードで英語を読めたんです。
他の人に聞いたら、自分の倍くらい時間をかけて解いた人もいて、ここで一番の成長を感じました。
グノは問題を解くのではなく英語をきっちり読むことに誠実に向き合う塾なので、それが成果として表れたんだと思います。
1回目が高1です。中3の夏休みに他の予備校でセンター試験レベルの模試を受けて全然解き終わらず、「ヤバイ」と危機感を抱いて猛勉強しました。高1の夏休みにも同じ模試を受けたら、50 分で終わって30 分も余りました。「来たな、コレ!」という手応えがあってとてもうれしかったです。
2回目は東大入試本番です。当日の僕は、英作文に時間をかけすぎてピンチに陥りました。プレッシャーがかかっている状況で最後に残っている問題に突入したのですが、それは3ページにも及ぶ長い英文を読まなくてはいけない空所補充の問題でした。このとき、日本語は脳のどこにもない状態で、今まで感じたことがないスピードで英語を読めたんです。
他の人に聞いたら、自分の倍くらい時間をかけて解いた人もいて、ここで一番の成長を感じました。
グノは問題を解くのではなく英語をきっちり読むことに誠実に向き合う塾なので、それが成果として表れたんだと思います。
椎名:
伸びたのは遅い方でした。
高2まではあまり勉強していなくて、高3の模試でも、英語がずっと足を引っ張っていました。
「英語は結構、面白いんだ」と思い始めたのは高3の初めの頃で、それから苦ではない英語の勉強が始められました。苦ではないからコツコツ積み重ねられて、成果が出始めたのは秋くらいからです。
ちなみに、同じクラスにいた嶋田君が毎回マウントをとってきました(笑)。それも悔しくて、最初は嫌々でしたが音読していくうちに、英文の楽しさに気づいていったのです。
高2まではあまり勉強していなくて、高3の模試でも、英語がずっと足を引っ張っていました。
「英語は結構、面白いんだ」と思い始めたのは高3の初めの頃で、それから苦ではない英語の勉強が始められました。苦ではないからコツコツ積み重ねられて、成果が出始めたのは秋くらいからです。
ちなみに、同じクラスにいた嶋田君が毎回マウントをとってきました(笑)。それも悔しくて、最初は嫌々でしたが音読していくうちに、英文の楽しさに気づいていったのです。
嶋田:
中3の冬にグノに入ったときはEGGS*からのスタートでした。その当時は中1レベルの英語力しかありませんでしたが、担当の先生に、いろいろと質問させていただいたり、相談に乗っていただいたりして、「先生がこれだけやってくれるんだから、がんばろう」と思いました。
グノで扱う英文のトピックは面白いんだと気づいたのは高1で、高1の秋にはαに上がれました。ところが、高2の冬にはまたα2に落ちてしまいました。椎名君に要約の点数で自慢していたのにクラスが落ちてしまい、次のクラス分けテストで絶対にαに戻りたいという思いで、このときは英語を全力で勉強してαに戻りました。
最後に伸びを実感できたのは受験直前です。センター前にセンター試験の過去問をパッと見たら一瞬で読み終わって、「この感覚でいけるかも?」と思って東大の英文を読んだらこれも読めて、「簡単じゃん!」となりました。このときにガーッと伸びて、受験本番も勢いで乗り切りました。
* EGGS(English Grammar Green Session for newcomers):英語が苦手になってしまった一般生のための、通常クラスに入る前に英文法の基礎を補完する講座。
グノで扱う英文のトピックは面白いんだと気づいたのは高1で、高1の秋にはαに上がれました。ところが、高2の冬にはまたα2に落ちてしまいました。椎名君に要約の点数で自慢していたのにクラスが落ちてしまい、次のクラス分けテストで絶対にαに戻りたいという思いで、このときは英語を全力で勉強してαに戻りました。
最後に伸びを実感できたのは受験直前です。センター前にセンター試験の過去問をパッと見たら一瞬で読み終わって、「この感覚でいけるかも?」と思って東大の英文を読んだらこれも読めて、「簡単じゃん!」となりました。このときにガーッと伸びて、受験本番も勢いで乗り切りました。
* EGGS(English Grammar Green Session for newcomers):英語が苦手になってしまった一般生のための、通常クラスに入る前に英文法の基礎を補完する講座。
辻:
僕も音読していくうちに、文章の深さや懐の広さやトピックの良さに段々気づいていきました。
夏休みくらいから知的な楽しさに目覚めて、「英語が楽しいから勉強する。伸びるからもっと楽しい」という良いサイクルが確立されました。
特定の時期に伸びたというわけではありませんが、これが僕の伸びだったと思います。
夏休みくらいから知的な楽しさに目覚めて、「英語が楽しいから勉強する。伸びるからもっと楽しい」という良いサイクルが確立されました。
特定の時期に伸びたというわけではありませんが、これが僕の伸びだったと思います。
中山:
僕の場合は、成績が上がったというよりも、意識が変わる瞬間を何度か経験しました。
入塾した当初は、面倒くさくて音読をしていなかったのですが、添削してもらえる要約でひどい点数を何度もとり、「音読でもしてみるか」と思って始めてみて、しばらくしたら満点がとれました。英文が楽に読めるようになったので、頭を筆者の主張に向ける余裕が生まれたからだと思います。
クラス分けテストでひとつクラスが上がったら、また要約の点数がとれなくなりました。英文の難度が上がって、当時の自分では論理を追いかけられなくなっていたのだと思います。
でも、どう考えればいいのかを先生がきちんと指導してくださったので、改めて誠実に英文に向き合おうと意識が変わり、さらにひとつ上のクラスに入れました。
高3の終わり頃に、また伸び悩んでいたので先生のところに相談にいきました。このときは、先生に向かって話している最中に、「英語を読めても、それを日本語にきちんと変換する力が足りない」という自分の弱点に自分で気がつけました。そのとき受けた先生からのアドバイスを意識したら最後にまた伸びました。
入塾した当初は、面倒くさくて音読をしていなかったのですが、添削してもらえる要約でひどい点数を何度もとり、「音読でもしてみるか」と思って始めてみて、しばらくしたら満点がとれました。英文が楽に読めるようになったので、頭を筆者の主張に向ける余裕が生まれたからだと思います。
クラス分けテストでひとつクラスが上がったら、また要約の点数がとれなくなりました。英文の難度が上がって、当時の自分では論理を追いかけられなくなっていたのだと思います。
でも、どう考えればいいのかを先生がきちんと指導してくださったので、改めて誠実に英文に向き合おうと意識が変わり、さらにひとつ上のクラスに入れました。
高3の終わり頃に、また伸び悩んでいたので先生のところに相談にいきました。このときは、先生に向かって話している最中に、「英語を読めても、それを日本語にきちんと変換する力が足りない」という自分の弱点に自分で気がつけました。そのとき受けた先生からのアドバイスを意識したら最後にまた伸びました。
■グノーブルの数学
数学の授業の印象はどうだったでしょうか?
過去の天才的なグノ生が残してくれた解答が取り上げられていて、「ぜひそれを自分の中に取り込みたい。これは勉強するしかない」とやる気になりました
中山:
グノの数学は「どうしてその問題に対してこのアプローチをするのか?」を先生がきちんと言語化してくださるのが特徴です。
そういう教え方をしている先生は他にもいるのでしょうが、グノの先生は独善的ではありません。「こういう問題にはこういうアプローチがこういう理由で有効だ」と理屈を教えてくださる一方で、人間らしさがあって接しやすい雰囲気でした。
「どうしてこういうことをすると解けないの?」という生徒の疑問に対して、先生は真摯に答えて、生徒の気持ちを理解してくださいます。
そういう教え方をしている先生は他にもいるのでしょうが、グノの先生は独善的ではありません。「こういう問題にはこういうアプローチがこういう理由で有効だ」と理屈を教えてくださる一方で、人間らしさがあって接しやすい雰囲気でした。
「どうしてこういうことをすると解けないの?」という生徒の疑問に対して、先生は真摯に答えて、生徒の気持ちを理解してくださいます。
大村:
数Ⅲの授業は衝撃的でとても楽しかったです。
プリントは配色まで工夫されていて、言葉遣いもかっこいいし、内容面でも別解が豊富でした。過去の天才的なグノ生が残してくれた解答が取り上げられていて、「ぜひそれを自分の中に取り込みたい。これは勉強するしかない」とやる気になりました。
直前期のテスト演習では成績優秀者の実名が載るので、「載りたい」と思ってがんばりました。
プリントは配色まで工夫されていて、言葉遣いもかっこいいし、内容面でも別解が豊富でした。過去の天才的なグノ生が残してくれた解答が取り上げられていて、「ぜひそれを自分の中に取り込みたい。これは勉強するしかない」とやる気になりました。
直前期のテスト演習では成績優秀者の実名が載るので、「載りたい」と思ってがんばりました。
辻:
受験学年後期のテスト演習が素晴らしかったです。
前期の問題が後期のテスト演習のための下準備になっていて、前期と後期が一体となって完成するのが特徴です。数Ⅰ A Ⅱ B はどうしても使う道具が多くなりますが、それをどういうタイミングで使うのかをグノでは教えてくれます。「こうしたいからこうする」「これが邪魔で消したいからこれを使う」など、一つひとつの道具について意味づけがはっきりしているので、どの道具を使えばいいかが明確化されました。
前期の問題が後期のテスト演習のための下準備になっていて、前期と後期が一体となって完成するのが特徴です。数Ⅰ A Ⅱ B はどうしても使う道具が多くなりますが、それをどういうタイミングで使うのかをグノでは教えてくれます。「こうしたいからこうする」「これが邪魔で消したいからこれを使う」など、一つひとつの道具について意味づけがはっきりしているので、どの道具を使えばいいかが明確化されました。
中山:
テスト演習はものすごく手をかけて作られています。「この4問を出すために、前期でこの問題とこの問題を入れていたんだよ」と先生から言われて実際に前期の内容を見返してみると、しっかりリンクしていました。大局的な視点に立って効果が上がるように整備された、完璧な問題選びが随所に見受けられるんです。
先生は生徒一人ひとりのことを考えて、真摯に教材を用意してくださっています。英語にも共通しているグノの良さだと思います。
先生は生徒一人ひとりのことを考えて、真摯に教材を用意してくださっています。英語にも共通しているグノの良さだと思います。
齋藤:
数学は、問題と一対一対応で解答を教えられることが多い科目です。その結果として「数学は運だ、センスだ」と言われます。予備校の解答の講評でも、「数学的センスを問われている」などと書かれていて、僕は「どうして?」と疑問でした。
その点、グノの数学は、運やセンスに頼らないで論理的に解けるように授業が構築されています。グノの授業が世間一般とは違っていることを実感していましたが、それを自分なりに吸収して数学の底力を養いました。
本番は自分の得意分野が全然出ませんでした。でも、運やセンスに頼らない勉強をしていたからこそ、しっかり部分点を稼いで合格できたと思っています。
その点、グノの数学は、運やセンスに頼らないで論理的に解けるように授業が構築されています。グノの授業が世間一般とは違っていることを実感していましたが、それを自分なりに吸収して数学の底力を養いました。
本番は自分の得意分野が全然出ませんでした。でも、運やセンスに頼らない勉強をしていたからこそ、しっかり部分点を稼いで合格できたと思っています。
大村:
授業内テストでは、自分が犯した間違いをセルフチェックシートに綴りました。最初は面倒だと思っていたセルフチェックシートですが、自分のミスの傾向や足りない分野が明白になるにつれて、その良さを実感できるようになりました。
数学は量が膨大なので、受験直前期に何をするかが大事です。そんな時期にセルフチェックシートを眺めることで自己分析することができ、役立ちました。
数学は量が膨大なので、受験直前期に何をするかが大事です。そんな時期にセルフチェックシートを眺めることで自己分析することができ、役立ちました。
辻:
セルフチェックシートを通して、間違うということに対して敏感になりました。「こういうミスをして自分は間違えるんだ」と記憶に残るので、間違いを次に活かせます。
僕は時々、感情的なことをバーッとシートに書くことで記憶の結びつきを強めていました。感情的なことに対しても先生のコメントが返ってきて、先生が一人ひとりをきちんと見てくださっているのが伝わってきました。それがとてもうれしかったです。
僕は時々、感情的なことをバーッとシートに書くことで記憶の結びつきを強めていました。感情的なことに対しても先生のコメントが返ってきて、先生が一人ひとりをきちんと見てくださっているのが伝わってきました。それがとてもうれしかったです。
齋藤:
セルフチェックシートはダラダラ書くのではなく、自分がつまずいたところに潜んでいた原因を端的に書いて蓄積していきました。自分のエラーや至らないところをひとつずつ着実に潰すのに使っていました。
先生は、問題や単元にとらわれず全分野を横断的に、僕の悪いくせを見抜いて指摘してくださいました。そのくせは自分では見えづらいので、本当にありがたかったです。
先生は、問題や単元にとらわれず全分野を横断的に、僕の悪いくせを見抜いて指摘してくださいました。そのくせは自分では見えづらいので、本当にありがたかったです。
■グノーブルの物理
物理の授業の特色を教えてください
僕はもともと物理が死ぬほど嫌いでしたが、グノの授業に通い始めたらとても楽しくて、「大学で物理を勉強したい」と思うほどになりました
小坂:
グノの物理は、グノ独自のまさに唯一無二の授業でした。
歴史の順番に沿って、「この物理学者はどういう考え方をしてこの法則を発見したのか?」を学びます。「定数をここに置いたらこの現象をうまく理解できる」とか、「こういう考えからこういう理論が発生するのは自然だ」とか、そういう歴代の科学者の考え方を順番に追っていくのはわくわくしました。
物理的な思考力を自然と習得できて、物理の問題を解く力も伸びました。
僕はもともと物理が死ぬほど嫌いでした。「どうしてこんな学問があるんだろう? 二度と勉強したくない」と嫌悪感を抱いていましたが、グノの授業に通い始めたらとても楽しくて、「大学で物理を勉強したい」と思うほどになりました。
先生の人柄が良く、話の幅も広いのでいつも聞き惚れていました。面白い話に引き込まれていくうちに、物理が大好きになりました。
歴史の順番に沿って、「この物理学者はどういう考え方をしてこの法則を発見したのか?」を学びます。「定数をここに置いたらこの現象をうまく理解できる」とか、「こういう考えからこういう理論が発生するのは自然だ」とか、そういう歴代の科学者の考え方を順番に追っていくのはわくわくしました。
物理的な思考力を自然と習得できて、物理の問題を解く力も伸びました。
僕はもともと物理が死ぬほど嫌いでした。「どうしてこんな学問があるんだろう? 二度と勉強したくない」と嫌悪感を抱いていましたが、グノの授業に通い始めたらとても楽しくて、「大学で物理を勉強したい」と思うほどになりました。
先生の人柄が良く、話の幅も広いのでいつも聞き惚れていました。面白い話に引き込まれていくうちに、物理が大好きになりました。
■グノーブルの先生
先生方はどのように皆さんの勉強と関わってくれましたか?
先生はご自身もリアルタイムで勉強されているのも印象的でした。「先生みたいな大人になりたい」と思いながら授業を受けていました
大村:
大手予備校だと、先生が君臨して、指示を与えて、集団に何かをやらせる雰囲気が正直あります。
グノの先生は、本当に生徒を見てくださいます。その分野を極めた先生が親身になって僕たちの弱点をフォローして、強みを伸ばしてくださるのが、グノの最大の特徴です。
先生に熱意があるので、自分も先生の熱意に自然についていけたし、いつの間にか成績が上がっていました。
グノの先生は、本当に生徒を見てくださいます。その分野を極めた先生が親身になって僕たちの弱点をフォローして、強みを伸ばしてくださるのが、グノの最大の特徴です。
先生に熱意があるので、自分も先生の熱意に自然についていけたし、いつの間にか成績が上がっていました。
小坂:
先生が熱意を持って接してくださるのはその通りです。
特に毎週の添削で先生ががんばっていらっしゃるのが伝わってきました。僕も「この人についていこう」と思えましたし、実際についていけば大丈夫なので安心感がありました。
困ったときはいつでも先生が助けてくださるのもありがたかったです。
特に毎週の添削で先生ががんばっていらっしゃるのが伝わってきました。僕も「この人についていこう」と思えましたし、実際についていけば大丈夫なので安心感がありました。
困ったときはいつでも先生が助けてくださるのもありがたかったです。
中山:
僕は、勉強するからには「できる人」になりたくて、その「できる」理由を感覚的につかみたいとずっと思っていました。
グノの先生は、英語でも数学でも、僕の求めていたものを示してくださいました。小手先のテクニックを駆使するのではなく、それぞれ経験に裏打ちされた確固たる考えをもって教えてくださいます。「できる人」が「どうしてできるのか?」を教えていただける環境でした。
さらに、先生はご自身もリアルタイムで勉強されていて、新しいものを取り入れていらっしゃるのも印象的でした。「先生みたいな大人になりたい」と思いながら授業を受けていました。
グノの先生は、英語でも数学でも、僕の求めていたものを示してくださいました。小手先のテクニックを駆使するのではなく、それぞれ経験に裏打ちされた確固たる考えをもって教えてくださいます。「できる人」が「どうしてできるのか?」を教えていただける環境でした。
さらに、先生はご自身もリアルタイムで勉強されていて、新しいものを取り入れていらっしゃるのも印象的でした。「先生みたいな大人になりたい」と思いながら授業を受けていました。
椎名:
中学と高校の間ずっと教わっていた先生は、仲の良いお兄ちゃんみたいな存在でした。その先生は文化祭にも来てくださって、僕はとても感謝していますし、本当に好きでした。
高3になってからは、全員カリスマ性があるすごい先生たちでした。「先生のためにがんばろう」というよりも「先生に失望されないためにがんばらなければ」という気持ちになっていましたが、そういう先生たちが全員、謙虚であることにも驚いていました。
高3になってからは、全員カリスマ性があるすごい先生たちでした。「先生のためにがんばろう」というよりも「先生に失望されないためにがんばらなければ」という気持ちになっていましたが、そういう先生たちが全員、謙虚であることにも驚いていました。
嶋田:
いろいろ個性的な先生方との思い出が記憶に残っていますが、科目の指導方針には通底するものがしっかりあること、それと生徒思いだということは共通していました。
それから、僕たちはグノで伸び伸びと勉強できましたが、先生方も伸び伸びと個性的に授業をされているんだろうということも言えると思います。
それから、僕たちはグノで伸び伸びと勉強できましたが、先生方も伸び伸びと個性的に授業をされているんだろうということも言えると思います。
辻:
グノの先生の分析力と的確な指摘にとても感謝しています。
例えば、数学でテスト演習に入ってから僕はケアレスミスが多く、問題文を読めていなかったり、途中で計算ミスをしたりして、点数を落としていました。
でも、そういうことを自覚して注意できるようになったのは、セルフチェックシートに「辻君は初動のミスが多いんですね」と先生がひと言コメントをしてくださったからです。それを見てから自分の傾向に意識を向けて問題に当たることができるようになったんです。
先生の的確なコメントのおかげで僕は変わることができました。
例えば、数学でテスト演習に入ってから僕はケアレスミスが多く、問題文を読めていなかったり、途中で計算ミスをしたりして、点数を落としていました。
でも、そういうことを自覚して注意できるようになったのは、セルフチェックシートに「辻君は初動のミスが多いんですね」と先生がひと言コメントをしてくださったからです。それを見てから自分の傾向に意識を向けて問題に当たることができるようになったんです。
先生の的確なコメントのおかげで僕は変わることができました。
齋藤:
グノの先生は、受験にとらわれていないのも印象的でした。一般的な塾だと受験が終わって合格すれば、それまで必死に積み上げてきたものでも、もう過去のものというイメージです。
でも、グノで培ったものは違います。グノの英語の授業で扱った英文はかけがえのないものに感じられます。捨てる気になんてなれません。単語帳の丸暗記をしないなど大学受験に縛られないグノの指導のおかげで、大学受験を超えたレベルまで対応できる力がついたと思っています。
数学でも先生は、「目標に対して論理的に攻めていく方法を学んでほしい」ということを常におっしゃっていて、この指摘からも使える思考力が身についたと思います。
でも、グノで培ったものは違います。グノの英語の授業で扱った英文はかけがえのないものに感じられます。捨てる気になんてなれません。単語帳の丸暗記をしないなど大学受験に縛られないグノの指導のおかげで、大学受験を超えたレベルまで対応できる力がついたと思っています。
数学でも先生は、「目標に対して論理的に攻めていく方法を学んでほしい」ということを常におっしゃっていて、この指摘からも使える思考力が身についたと思います。
■後輩へのアドバイス
これから受験する後輩に向けて一言お願いします
勉強が楽しくなることと、それに伴って成績が上がってくれば「グノのやり方が正しかったんだ」と実感することになります
大村:
勉強は「楽しい」が原動力なので、好奇心を刺激してくれるグノに通っていれば大丈夫です。
数学のセルフチェックシートなど、「回り道」と思うものもあるでしょうが、手を抜かずに続けていけば、最後の最後でその価値が体感できます。
グノの先生を信じてしっかり積み上げていってください。受験直前で自分の積み上げてきたものの高さに気づいてそれが自信になると思います。
数学のセルフチェックシートなど、「回り道」と思うものもあるでしょうが、手を抜かずに続けていけば、最後の最後でその価値が体感できます。
グノの先生を信じてしっかり積み上げていってください。受験直前で自分の積み上げてきたものの高さに気づいてそれが自信になると思います。
辻:
大村君と同意見です。グノのすごさはあとになって実感できます。
最初は、英語の語源や音読、数学の膨大な板書をノートに写す作業など、これは普通の受験勉強と違うという印象を受けるかもしれません。
それでもグノは間違いありません。グノの指導法こそ本質をついています。あとになってから本質が間違いなく見えてきます。
最初は、英語の語源や音読、数学の膨大な板書をノートに写す作業など、これは普通の受験勉強と違うという印象を受けるかもしれません。
それでもグノは間違いありません。グノの指導法こそ本質をついています。あとになってから本質が間違いなく見えてきます。
小坂:
僕も先生を信じることに尽きると思います。
グノに入った直後は、他塾と違いすぎることに戸惑って、「本当にこれでいいの?」と疑問を持つこともあるでしょう。
でも、勉強が楽しくなることと、それに伴って成績が上がってくれば、「グノのやり方が正しかったんだ」と実感することになります。
グノに入った直後は、他塾と違いすぎることに戸惑って、「本当にこれでいいの?」と疑問を持つこともあるでしょう。
でも、勉強が楽しくなることと、それに伴って成績が上がってくれば、「グノのやり方が正しかったんだ」と実感することになります。
齋藤:
グノの勉強法はけっして突飛なものではありません。むしろ、今までの受験の常識にこそ疑問にさえ思われずに踏襲されてきたものが多いのだと思います。
気になることがあったらグノの先生のところに質問にいってみるといいと思います。明快な答えが返ってきて、自分でも「この勉強法にこういう効果があるんだ」とか「この勉強法ではこの能力が伸びるんだ」とわかって、とても前向きな気持ちで勉強に向かえるようになります。
少しやり続けてみれば成績もついてくるので安心できます。高3の大事な時期に入ったときには、自分なりの工夫を入れつつグノの勉強を活かせるようになります。
気になることがあったらグノの先生のところに質問にいってみるといいと思います。明快な答えが返ってきて、自分でも「この勉強法にこういう効果があるんだ」とか「この勉強法ではこの能力が伸びるんだ」とわかって、とても前向きな気持ちで勉強に向かえるようになります。
少しやり続けてみれば成績もついてくるので安心できます。高3の大事な時期に入ったときには、自分なりの工夫を入れつつグノの勉強を活かせるようになります。
椎名:
グノの英語は、言語を学ぶ本質がわかるような授業です。先生のおっしゃることを聞きながら、本質を考えつつ、受験にとらわれないで楽しみながら勉強しましょう。そうすれば、英語が得意になるはずです。
中山:
皆さんと同意見です。疑問点があれば迷わず先生に相談することが大切です。
グノはメソッドがしっかりしている分、自分の意識を高めていくことも求められますが、それは当然だと思います。受け身でも授業を受けてさえいれば成績が上がるとか、大量の問題を解いていれば思考力が伸ばせるということの方が変なのだと思います。
グノの勉強を主体的に楽しんでいくことが成功の秘訣です。
グノはメソッドがしっかりしている分、自分の意識を高めていくことも求められますが、それは当然だと思います。受け身でも授業を受けてさえいれば成績が上がるとか、大量の問題を解いていれば思考力が伸ばせるということの方が変なのだと思います。
グノの勉強を主体的に楽しんでいくことが成功の秘訣です。
嶋田:
グノのすごさを実感できるのは、きちんと積み上げてきた人です。先生を信じて努力し続けることが大切です。そうすれば勉強そのものが楽しくなります。
直前期になればなるほど、ピンポイントで伸ばしたいところが出てきますが、このときにグノで教わったことの意味がわかっていると、それを使ってさらにひと伸びできます。
直前期になればなるほど、ピンポイントで伸ばしたいところが出てきますが、このときにグノで教わったことの意味がわかっていると、それを使ってさらにひと伸びできます。