国立大学医学部 Part 2
ホーム > Gno-let > Gno-let23 > 国立大学 医学部 Part2
| 恩田 健吾さん(東京医科歯科・筑波大学附属駒場) | 蒲田 文和さん(東大理Ⅲ・開成) |
| 北脇 優斗さん(東京医科歯科・筑波大学附属駒場) | 今野 諒也さん(筑波・海城) |
| 東海林 睦さん(横浜市立・淑徳) | 中川 就迪さん(慶應義塾・開成) |
| 牧山 優香さん(信州・早稲田実業) | |
■医学部志望の動機
皆さんが医学部を志望した動機を教えてください。
患者さんとご家族の笑顔が輝いているのを見て、「こういう仕事をしたい」と強く思い医師を目指しました
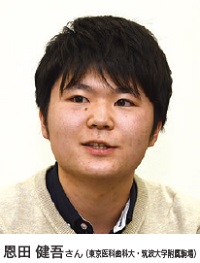
恩田:
姉も医学部生ですが、その影響はあまりなくて、僕の場合は、学校のプログラムに参加したことが医学部に興味を持ったきっかけです。高1のとき学校のプログラムで筑波大学医学医療系見学に参加しました。そこで医学は工学などの様々な分野と結びついていることを実感して興味を持ちました。
高3のときには、高大連携プロジェクトで医科歯科大に行って話を聞き、そこで最終的に志望を決定しました。
高3のときには、高大連携プロジェクトで医科歯科大に行って話を聞き、そこで最終的に志望を決定しました。
今野:
父が医師なので、医師の仕事に興味はありました。でも、自分が医師になりたいかどうかは曖昧でしたが、高校生のとき親族のお見舞いで病院に行き、「医師は人を笑顔にできる仕事だ」と実感しました。
医師は、人を助ける仕事の中でも、特に高い知識と技能をもって患者さんと向き合う仕事です。生涯誇りを持ってできる仕事だと思って臨床医を志望しました。
医師は、人を助ける仕事の中でも、特に高い知識と技能をもって患者さんと向き合う仕事です。生涯誇りを持ってできる仕事だと思って臨床医を志望しました。
北脇:
僕の場合は、身近に医師がいるわけではありません。影響を受けたのは、親がよく見ていた医学のドキュメンタリーです。幼い頃から一緒に見ているうちに、尊い人の命を直接助けたり、患者さんを安心させたりする姿に憧れを抱くようになって、医師を志望しました。

蒲田:
漠然と「人の役に立ちたい」と思っていたのがきっかけです。テレビで脳外科の先生が手術したあと、患者さんとご家族の笑顔が輝いているのを見て、「こういう仕事をしたい」と強く思い医師を目指しました。
中川:
僕は、もともと「理系の研究者になりたい」と思っていましたが、部活を引退する高2の冬まであまり将来のことを考えていませんでした。部活が終わって時間ができて、「何をしたいか?」を改めて考えたとき、患者さんを治療してその人の人生を新しくスタートさせられる医師の仕事に興味を持ちました。
東海林:
高2の2学期、体育の時間に意識を失うけがをして病院に搬送され、人生で初めて入院しました。何が起こるかわからなくて、とても不安でとにかく怖かったのを覚えています。このとき、担当の脳外科の先生の説明が理路整然としていて、その話し方に僕は安心できました。
医師は、正しい知識と確かな技能をもとに患者を安心させられる仕事です。入院を通してこのことを実感した僕は、それまでは本当に何も考えていませんでしたが、「医師の仕事をしたい」と志望が固まりました。
医師は、正しい知識と確かな技能をもとに患者を安心させられる仕事です。入院を通してこのことを実感した僕は、それまでは本当に何も考えていませんでしたが、「医師の仕事をしたい」と志望が固まりました。
牧山:
兄が重度の自閉症で言語障害があり、自分の症状を伝えられなくて苦労している姿を幼い頃から見てきました。だから、「発達障害の子どもを助けられる医者になりたい」と思っていました。
早稲田実業は、ほぼ全員、早稲田大学に進学する学校です。その中で高1から「がんばるぞ」と心に決め、高校に上がると同時にテニスをやめて受験勉強に専念することにしました。
早稲田実業は、ほぼ全員、早稲田大学に進学する学校です。その中で高1から「がんばるぞ」と心に決め、高校に上がると同時にテニスをやめて受験勉強に専念することにしました。
■入塾のきっかけ
なぜグノーブルを選んだのでしょうか?
「これなら授業を楽しめる」と思ったのが決め手になりました
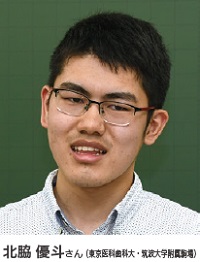
北脇:
英語と数学は中1になる前のスタートダッシュ講座*から続けています。
僕の学校では、土曜日は数学や国語などの勉学系の授業をやらず、課題研究などの行事に近いことをやっていて、他の学校に比べて授業のコマ数が少ないんです。それで「塾でも勉強した方がいいんじゃないか?」という判断がありました。母が塾探しをして、勉強を楽しめそうで、宿題が少なめのグノが候補に上がりました。
*新中1対象の講座(2~3月に開講)。
僕の学校では、土曜日は数学や国語などの勉学系の授業をやらず、課題研究などの行事に近いことをやっていて、他の学校に比べて授業のコマ数が少ないんです。それで「塾でも勉強した方がいいんじゃないか?」という判断がありました。母が塾探しをして、勉強を楽しめそうで、宿題が少なめのグノが候補に上がりました。
*新中1対象の講座(2~3月に開講)。
今野:
僕もスタートダッシュ講座からグノに通っています。スタートダッシュ講座を受けて、教え方がすっかり気に入って、「この塾がいい!」と思い、そのまま英語・数学を続けました。
牧山:
私はふたりより遅くて、中2のとき英語に入塾しました。中1までは別の塾に通っていましたが、何を暗記させられているのかもよくわからないまま覚える勉強がつまらなくて、私が「塾を辞めたい」と言ったら、親が「グノに変えてみれば?」と勧めてくれました。
授業を受けてみたら、英単語を語源から覚える方法や、面白い英文を読めること、宿題が少ないところなどが気に入って、「これなら授業を楽しめる」と思ったのが決め手になりました。
授業を受けてみたら、英単語を語源から覚える方法や、面白い英文を読めること、宿題が少ないところなどが気に入って、「これなら授業を楽しめる」と思ったのが決め手になりました。
中川:
僕は高1になるタイミングでの入塾です。中学では、みんなと一緒に他塾に入っていましたが、その頃は惰性で英語を勉強していました。改めて「英語をきちんと勉強したい」と思い、友人から「グノが良い」と聞いていたこともあってグノに決めました。
グノは、受験勉強として英語とつき合うというよりも、英語と仲良くなれる塾で、「ここで勉強してみたい」と強く思いました。英語に対する苦手意識をなくしてくれた塾です。
グノは、受験勉強として英語とつき合うというよりも、英語と仲良くなれる塾で、「ここで勉強してみたい」と強く思いました。英語に対する苦手意識をなくしてくれた塾です。
恩田:
僕は高1の終わりに英語で入塾しましたが、きっかけは母や友達からの話です。
姉の高校で「グノは英語が伸びる」と評判だったのを母は聞いていました。それと、僕の学校でグノに通っている人が、みんな楽しそうに勉強しているのも見ていました。実際に授業を受けたら、本当に楽しくて高3までずっと続けました。
高2で古文もとりました。古文は周りの影響が大きかったです。高1で古文をとっている友達がいて、先輩方もたくさん受講していて、評判が良かったんです。当時古文がさっぱりだったので、「何もやっていない人でも読めるようになるよ」「文法から教えてくれるよ」といった話に心惹かれました。
姉の高校で「グノは英語が伸びる」と評判だったのを母は聞いていました。それと、僕の学校でグノに通っている人が、みんな楽しそうに勉強しているのも見ていました。実際に授業を受けたら、本当に楽しくて高3までずっと続けました。
高2で古文もとりました。古文は周りの影響が大きかったです。高1で古文をとっている友達がいて、先輩方もたくさん受講していて、評判が良かったんです。当時古文がさっぱりだったので、「何もやっていない人でも読めるようになるよ」「文法から教えてくれるよ」といった話に心惹かれました。
蒲田:
僕も同時期にグノに入塾しました。友人から「そろそろ塾に入らない?」という誘いがあって、主体的というよりも友人につられて高1の冬期講習に参加しました。
グノは生徒と先生の距離の近さが魅力でした。僕は「ザ・予備校」みたいな雰囲気が嫌で、中学受験みたいに楽しい雰囲気で勉強したかったんです。それまでは、学校行事がとても好きで楽しんでいたので、塾に行くよりも学校行事に参加したくて、塾に全く通っていませんでした。
グノは生徒と先生の距離の近さが魅力でした。僕は「ザ・予備校」みたいな雰囲気が嫌で、中学受験みたいに楽しい雰囲気で勉強したかったんです。それまでは、学校行事がとても好きで楽しんでいたので、塾に行くよりも学校行事に参加したくて、塾に全く通っていませんでした。
東海林:
高2の3月ギリギリまで部活があって、終わるのを見越して2月ぐらいから「そろそろ塾を考えないといけない」と思っていました。このとき、友人に「グノがとにかくすごい! お前、英語好きだろ?」と言われ、実際にグノの春期講習を受けてみて入塾を決めました。
当時「単語帳をやらないといけない」と思っていたのに、「単語帳を覚えない」というグノの方針に驚きました。音読もそれまでしていませんでしたが、音読すると楽しくて、英語のリズムから単語の知識、英文らしい文の組み立てなど、あらゆることが入ってくるのを実感して、こちらも驚きでした。授業も楽しくて「ここしかない」という気持ちになりました。
当時「単語帳をやらないといけない」と思っていたのに、「単語帳を覚えない」というグノの方針に驚きました。音読もそれまでしていませんでしたが、音読すると楽しくて、英語のリズムから単語の知識、英文らしい文の組み立てなど、あらゆることが入ってくるのを実感して、こちらも驚きでした。授業も楽しくて「ここしかない」という気持ちになりました。
■グノーブルの英語
英語の授業はどんな雰囲気だったのか教えてください。
過去問ばかりではなく、生きている英文をたくさん読めるグノの授業で、英文の内容自体に興味を持てました
牧山:
英単語の意味をたくさん暗記しているのに長文読解に苦手意識を持っている人が周りにいましたが、グノだと中学の頃から長い英文に親しめました。
グノの取り組み方は普通とは逆というか、単語を覚えて文章を読むというよりも、文章を読みながら、その中に出てくる単語の意味を語源から説明してもらえます。文脈の中でしっくりくる意味を教えてもらえるので、英単語に日本語の意味をあてても英文の流れがとぎれることがありません。
解説のときに、同じ語源の他の単語がどんどん展開していくこともあります。語源で単語の説明をしてもらえると推測力もつきます。このような授業のおかげで長文読解に強くなれたのだと思います。
グノの取り組み方は普通とは逆というか、単語を覚えて文章を読むというよりも、文章を読みながら、その中に出てくる単語の意味を語源から説明してもらえます。文脈の中でしっくりくる意味を教えてもらえるので、英単語に日本語の意味をあてても英文の流れがとぎれることがありません。
解説のときに、同じ語源の他の単語がどんどん展開していくこともあります。語源で単語の説明をしてもらえると推測力もつきます。このような授業のおかげで長文読解に強くなれたのだと思います。
中川:
英語と楽しくつき合えるという印象の授業でした。僕は「この単語は受験に必須だ」とか「この英文は頻出構文だ」という受験の型にはめる英文読解が苦手でした。本を読むのが好きだったので、文章の意味をそのまま読んで楽しみたかったんです。
だから、興味深い英文が用意され、内容の解釈が主となるグノの授業は楽しめました。
それに、過去問ばかりを引っ張ってくるのではなく、生きている英文をたくさん読めるグノの授業では、英文の内容自体に興味を持てました。
だから、興味深い英文が用意され、内容の解釈が主となるグノの授業は楽しめました。
それに、過去問ばかりを引っ張ってくるのではなく、生きている英文をたくさん読めるグノの授業では、英文の内容自体に興味を持てました。
東海林:
中川君の言う通り、文章が本当に面白かったし、グノでは文章を楽しんで読むことが大切にされます。だから、問題を解いていても楽しいんです。
先生からも「ここではどんな意味?」といった質問が投げかけられ、文脈をしっかり踏まえることが求められました。丸暗記した意味が問われているのではないので、質問に答えられたときには、特別なうれしさがあります。
授業でのこういう経験は初めてでした。僕はそれまで、情報処理として英文を読んでいましたし、単語や文法は必死で覚えるものだと思っていました。
でも、グノに入ってからは、英文を味わう楽しみがわかるようになったし、初見の単語でも意味が推測できるようになりました。英文が記憶にも残りやすくなり、自然に頭の中に残っているフレーズを英作文で使えるようになっていたときは、自分の成長を実感しました。
先生からも「ここではどんな意味?」といった質問が投げかけられ、文脈をしっかり踏まえることが求められました。丸暗記した意味が問われているのではないので、質問に答えられたときには、特別なうれしさがあります。
授業でのこういう経験は初めてでした。僕はそれまで、情報処理として英文を読んでいましたし、単語や文法は必死で覚えるものだと思っていました。
でも、グノに入ってからは、英文を味わう楽しみがわかるようになったし、初見の単語でも意味が推測できるようになりました。英文が記憶にも残りやすくなり、自然に頭の中に残っているフレーズを英作文で使えるようになっていたときは、自分の成長を実感しました。
■英単語の覚え方
受験では数多くの英単語を暗記しなければならないと思いますが、どのように乗り越えたのでしょうか?
グノで英語を身につけた僕は、一度も単語帳を開けることはありませんでした

今野:
単語帳を使わないアプローチは、グノの特筆すべきところだと思います。文章の中で出合った単語について、語源や関連語も一緒に教えてもらえます。
先生が基本動詞の意味を、体を使って表現してくださったときはびっくりしました。動詞なんだから具体的な動作ができるのはあたりまえなのに、今までそんな授業を受けたことがありませんでした。
前置詞のイメージを先生が黒板に描いたときにも驚きました。英単語の意味を日本語の意味に置き換えて覚えようとしていたそれまでの常識が覆り、単語の覚え方が自分の中で180 度変わりました。
「単語帳の暗記は必要だ」と思っていましたし、学校でも単語帳で覚えるのがあたりまえの雰囲気です。友達も単語帳をやっていました。
でも、グノで英語を身につけた僕は、一度も単語帳を開けることはありませんでした。単語帳の暗記に時間を使うのはもったいないと思います。
先生が基本動詞の意味を、体を使って表現してくださったときはびっくりしました。動詞なんだから具体的な動作ができるのはあたりまえなのに、今までそんな授業を受けたことがありませんでした。
前置詞のイメージを先生が黒板に描いたときにも驚きました。英単語の意味を日本語の意味に置き換えて覚えようとしていたそれまでの常識が覆り、単語の覚え方が自分の中で180 度変わりました。
「単語帳の暗記は必要だ」と思っていましたし、学校でも単語帳で覚えるのがあたりまえの雰囲気です。友達も単語帳をやっていました。
でも、グノで英語を身につけた僕は、一度も単語帳を開けることはありませんでした。単語帳の暗記に時間を使うのはもったいないと思います。
蒲田:
単語帳だと、日本語で書いてある意味しか覚えられません。でも、語源を踏まえて単語を解釈していくと、単語が持つふくよかなイメージがわかります。文章中で単語を覚えていくと的確な使い方が身につきます。和訳する必要があるときは、その場に最も適した訳し方が浮かぶようになるし、英作文をするときには適した単語が選べるようになります。
グノは、読解の授業でも作文の授業でも、単語と日本語の一対一対応ではなく、日本語では表せないイメージをつかみやすいような解説がなされていて、それは先生が僕たちに、受験だけで終わらない英語を伝えようとしてくれているからだと思います。
グノは、読解の授業でも作文の授業でも、単語と日本語の一対一対応ではなく、日本語では表せないイメージをつかみやすいような解説がなされていて、それは先生が僕たちに、受験だけで終わらない英語を伝えようとしてくれているからだと思います。
北脇:
同感です。パッと単語を見たとき、「あの文章にあった単語だ」と、英文ごと、内容と一緒に単語が思い出せるようになって楽しかったです。
■グノーブルの音読
英語の指導では音読が重視されていますが、皆さんはどのように取り組みましたか?
最初のうちは、「生き生きと読むというのは、どういう意味なんだろう?」と思っていました
恩田:
先生方の英語の知識はもちろん素晴らしいのですが、そこにとどまりません。いろいろな分野にも先生方は精通されていて、英文の背景知識まで詳しく説明してくださいます。だから、自分で読んでいるときには面白さが理解できなかった英文でも、授業の解説を受けると興味深いものに変わります。
興味の持てる英文は、そこに書かれている知識や考え方自体を学びたくなるので一生懸命に復習したくなります。授業で扱った英文を音読で復習するのが大好きでした。勉強の苦しさはまるでありませんでした。
興味の持てる英文は、そこに書かれている知識や考え方自体を学びたくなるので一生懸命に復習したくなります。授業で扱った英文を音読で復習するのが大好きでした。勉強の苦しさはまるでありませんでした。
北脇:
自宅学習は授業後の復習がメインで、その復習の中心は、誰かに語りかけるようにする音読というのが、グノの際だった特徴です。
授業で十分に理解して、その面白さがわかっている英文を、誰かに伝えるように音読するのは、単純に楽しいです。英語の実力も上がりました。
英文を前から語順のまま読む力が身について、単語を文章の内容と一緒に思い出せるようにもなりました。僕は他の教材を使わずにグノの教材一筋でした。
新しい英文を読むときも口パクしていました。口パクしているとスラスラ意味がとれます。入試本番でも口パクしたおかげでスラスラ理解できました。
授業で十分に理解して、その面白さがわかっている英文を、誰かに伝えるように音読するのは、単純に楽しいです。英語の実力も上がりました。
英文を前から語順のまま読む力が身について、単語を文章の内容と一緒に思い出せるようにもなりました。僕は他の教材を使わずにグノの教材一筋でした。
新しい英文を読むときも口パクしていました。口パクしているとスラスラ意味がとれます。入試本番でも口パクしたおかげでスラスラ理解できました。
恩田:
先生の「演説するように音読するんだよ」という言葉に共感して、演説のつもりでの音読を心掛けていました。授業の解説でよく理解している英文を「演説」していると、筆者の言いたいことや、英文の組み立てがよく見えてきます。
英語に関しては、話すこと・聞くこと・読むこと・書くことの4つのうち、一番進度が遅いものに引きずられるので、4つのどれもおろそかにしてはいけません。だから、毎日音読を欠かしたことはありませんし、寝るときはGSL*を流して寝ることもありました。
直前期には問題を解くとき、問題文を音読していました。医科歯科大の入試問題は超長文なので、できるだけ集中力を切らさずに前からパパッと解釈できれば有利になります。本番ではそれがしっかりできて、音読の真価を身をもって感じました。
* GSL(Gnoble Sound Laboratory):中1から高3までの6学年すべてに毎週用意されているオリジナルの英語音声教材。
英語に関しては、話すこと・聞くこと・読むこと・書くことの4つのうち、一番進度が遅いものに引きずられるので、4つのどれもおろそかにしてはいけません。だから、毎日音読を欠かしたことはありませんし、寝るときはGSL*を流して寝ることもありました。
直前期には問題を解くとき、問題文を音読していました。医科歯科大の入試問題は超長文なので、できるだけ集中力を切らさずに前からパパッと解釈できれば有利になります。本番ではそれがしっかりできて、音読の真価を身をもって感じました。
* GSL(Gnoble Sound Laboratory):中1から高3までの6学年すべてに毎週用意されているオリジナルの英語音声教材。
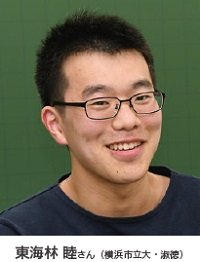
東海林:
授業を受けた次の日に学校でも家でも音読をするようにしていました。好きな英文は10 回か20 回は読んでいましたね。気に入った英文だとつい読んでいて楽しくなってしまうことがあって、「このぐらいでやめないとまずい」と思うくらい読み込んでいました。
何度も読んでいると、解説を聞いてメモしたことがパッとわかる瞬間があります。「こういうことだったんだ」と解説されたことを実感できるのはとてもうれしくて、「別の発見があるかもしれない」と思うと、また読んでしまうんです。
何度も読んでいると、解説を聞いてメモしたことがパッとわかる瞬間があります。「こういうことだったんだ」と解説されたことを実感できるのはとてもうれしくて、「別の発見があるかもしれない」と思うと、また読んでしまうんです。
牧山:
私は、音読は高3になるまではあまりしていませんでした。そもそも復習もクラス分けテストの前にバーッとするくらいでした。高3になってからは、家で音読して、行き帰りの電車の中でも、マスクをしてバレないように口を動かして心の中で読んでいました。
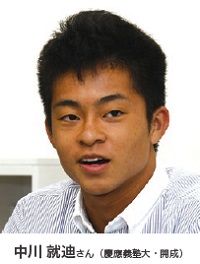
中川:
グノの音読は、いろいろなところで気軽にできるのが魅力です。移動時間中も口パクで読み込みができます。
音読がうまくなるとそれだけで英語の学習効果は大きいので、スキマ時間が英語の勉強時間に当てられます。授業の前後の5分間休みや時間の余ったときに取り組むだけでなく、他科目で疲れたときに、気分転換として英語を読みました。
音読すると、演習のときに読めなかった部分などがパッとフラッシュバックして記憶に刻まれます。
自分で新しい英文を用意して読んだこともありました。このときは、構文などが自然とわかるくらいまで、授業以上に読み込みました。僕は音読だけを信じてやってきて結果も出たので、音読というスタイルは自分に合っていたのだと思います。
音読がうまくなるとそれだけで英語の学習効果は大きいので、スキマ時間が英語の勉強時間に当てられます。授業の前後の5分間休みや時間の余ったときに取り組むだけでなく、他科目で疲れたときに、気分転換として英語を読みました。
音読すると、演習のときに読めなかった部分などがパッとフラッシュバックして記憶に刻まれます。
自分で新しい英文を用意して読んだこともありました。このときは、構文などが自然とわかるくらいまで、授業以上に読み込みました。僕は音読だけを信じてやってきて結果も出たので、音読というスタイルは自分に合っていたのだと思います。
蒲田:
僕も同じで、家に帰るのに1時間かかるので、電車の中でその日の復習と音読をやるようにしました。音読が習慣になるにつれて、英語は段々伸びました。
直前期までは数学や理科をやらなければならないことが多くて、夜遅くまでこれらの科目を勉強していると、「これから英語をやるよりも早く寝たい」となりがちでした。でも、直前期にはそれを我慢して、音読だけはするようにしたら、最後は英語が一番伸びました。
音読は、1日2日空けてやるのと毎日やるのとでは全然違います。毎日しっかり音読してこそ効果があります。
直前期までは数学や理科をやらなければならないことが多くて、夜遅くまでこれらの科目を勉強していると、「これから英語をやるよりも早く寝たい」となりがちでした。でも、直前期にはそれを我慢して、音読だけはするようにしたら、最後は英語が一番伸びました。
音読は、1日2日空けてやるのと毎日やるのとでは全然違います。毎日しっかり音読してこそ効果があります。
今野:
僕も高2までは音読していませんでした。音読は体を使うので疲れるし、部活もあって面倒くさかったからです。音読を始めたのは高3になってからで、読解の授業で毎回取り組む要約演習が全然できなかったことがきっかけです。
先生からは「英文は生き生きと読めなくてはいけない」と強調されていましたが、最初のうちは、「生き生きと読むというのは、どういう意味なんだろう?」と思っていました。
音読には半信半疑だったものの、要約演習で点がとれないので、とにかく先生に言われたままにやりました。電車の中ではGSL を聞き、学校の休み時間には音読し、家に帰ってからは椅子の上に立ってプレゼンする気持ちで音読しました。
そのうちわかったことは、「音読していると体が反応する」ということです。わかっていない単語があると自然と読めなくなって止まってしまいます。伝える気持ちを忘れて声を出すだけになっているときもすぐに気づきます。うまい読み方ができるときは頭も体も気持ち良くなります。
音読に真剣に向き合い始めてから、先生に以前から言われていた、「耳や口を鍛えないで英語の勉強をするのは、ボールを使わずに野球の練習をするようなものだ」という言葉の意味がわかるようになりました。「生き生き読む」ことも実感できるようになって音読の素晴らしさに気づきました。
先生からは「英文は生き生きと読めなくてはいけない」と強調されていましたが、最初のうちは、「生き生きと読むというのは、どういう意味なんだろう?」と思っていました。
音読には半信半疑だったものの、要約演習で点がとれないので、とにかく先生に言われたままにやりました。電車の中ではGSL を聞き、学校の休み時間には音読し、家に帰ってからは椅子の上に立ってプレゼンする気持ちで音読しました。
そのうちわかったことは、「音読していると体が反応する」ということです。わかっていない単語があると自然と読めなくなって止まってしまいます。伝える気持ちを忘れて声を出すだけになっているときもすぐに気づきます。うまい読み方ができるときは頭も体も気持ち良くなります。
音読に真剣に向き合い始めてから、先生に以前から言われていた、「耳や口を鍛えないで英語の勉強をするのは、ボールを使わずに野球の練習をするようなものだ」という言葉の意味がわかるようになりました。「生き生き読む」ことも実感できるようになって音読の素晴らしさに気づきました。
■グノーブルの数学
数学の授業の印象はどうだったでしょうか?
センスに頼ると限界になってしまう部分を戦略的に考えられるようになり、数学が伸びました
今野:
中1から高1までのグノの数学では、競うように楽しく問題を解けました。担当の先生が生徒一人ひとりを見回って、ちゃんと気を配ってくださいました。進度が速い人はプリントが追加で配られ、いくらでも楽しめて盛り上がっていました。問題に手間取っている人には先生が「大丈夫?」と声をかけてくださるし、必要ならば一から丁寧に説明してくださいます。
数学は好きでしたが必ずしも得意ではなかったので、先生の配慮と授業の雰囲気に助けられました。
数学は好きでしたが必ずしも得意ではなかったので、先生の配慮と授業の雰囲気に助けられました。
北脇:
僕も中1から数学を受けていて、授業で数学を楽しませてもらえました。先生は一人ひとりにプリントをくださったりといつも配慮してくださりました。
高2高3でも引き続き一人ひとりに目を配る点は変わりませんでした。僕は数学が得意でしたが、独学では理解できないこともあって、それを教えていただくために授業に通っていました。すんなり理解が進む授業でした。
セルフチェックシートも書きました。基本的には、授業内演習について振り返って書きました。
僕の場合、セルフチェックシートは書くこと自体に大いに意味がありました。書くことで自分の弱点を炙り出して自分の解法を見直すきっかけにしていました。答案の形で書くのとは違って、自分で言葉にして文章にするので、論理的にまとめることができたと思います。
書いているうちにいろいろな解法が身について、自分が成長するのを実感できたのが一番大きかったです。
高2高3でも引き続き一人ひとりに目を配る点は変わりませんでした。僕は数学が得意でしたが、独学では理解できないこともあって、それを教えていただくために授業に通っていました。すんなり理解が進む授業でした。
セルフチェックシートも書きました。基本的には、授業内演習について振り返って書きました。
僕の場合、セルフチェックシートは書くこと自体に大いに意味がありました。書くことで自分の弱点を炙り出して自分の解法を見直すきっかけにしていました。答案の形で書くのとは違って、自分で言葉にして文章にするので、論理的にまとめることができたと思います。
書いているうちにいろいろな解法が身について、自分が成長するのを実感できたのが一番大きかったです。
蒲田:
高1から高2までは受験勉強の意識もなく、グノには数学を楽しみに通っていました。当時は、「微積は難しい」というイメージがあって、特に積分に苦手意識がありました。でも、授業の解説がわかりやすく、最終的には微積が味方になってくれました。
高3の数Ⅰ A Ⅱ B には、僕が苦手な発想を要求される問題がありました。そういう問題に対して、そのときのコンディションやひらめきなどに頼るのではなく、「こういう問題はこう解く」という方法論を示してくださったのがグノの授業でした。センスに頼ると限界になってしまう部分を戦略的に考えられるようになって、数学の力が伸びました。戦略的な方法論が身についたのは数Ⅲでも同様でした。
セルフチェックシートは毎週書きました。自分が正解した問題でも「ここでショートカットできたな」とか「ここは必要なかったな」とかを考えて、間違えた問題だけでなく、正解した問題でも時間短縮などの反省をするのに役立ちました。
高3の数Ⅰ A Ⅱ B には、僕が苦手な発想を要求される問題がありました。そういう問題に対して、そのときのコンディションやひらめきなどに頼るのではなく、「こういう問題はこう解く」という方法論を示してくださったのがグノの授業でした。センスに頼ると限界になってしまう部分を戦略的に考えられるようになって、数学の力が伸びました。戦略的な方法論が身についたのは数Ⅲでも同様でした。
セルフチェックシートは毎週書きました。自分が正解した問題でも「ここでショートカットできたな」とか「ここは必要なかったな」とかを考えて、間違えた問題だけでなく、正解した問題でも時間短縮などの反省をするのに役立ちました。
■グノーブルの古文
医学部志望の皆さんにとって国語の授業はどうだったのでしょうか?
とにかく授業が楽しくて、楽しいから学びたくなって、という感じでした
北脇:
グノの古文は1年間だけ受ければ受験対策が完成します。「高1からだと早いかな?」とも思いましたが、僕は高1の春期講習から古文を受講しました。
受けてみるととにかく授業が楽しくて、楽しいから学びたくなって、という感じでした。古文が得意というわけではありませんでしたが、楽しいからモチベーションが上がって、単語や文法の知識も面白いように頭に入りました。学ぶのも問題を解くのも苦でなく、復習していてもさらにモチベーションが上がりました。
高1で学んだことは、高3でセンター試験を解くときも記憶に残っていました。楽しんで覚えたことは、1年のブランクがあっても定着しているものです。古文の参考書などを読まなくても、授業に出ていれば助動詞の識別などが印象に残って、「どうして識別ができないのかわからない」というレベルにまで到達しました。
受けてみるととにかく授業が楽しくて、楽しいから学びたくなって、という感じでした。古文が得意というわけではありませんでしたが、楽しいからモチベーションが上がって、単語や文法の知識も面白いように頭に入りました。学ぶのも問題を解くのも苦でなく、復習していてもさらにモチベーションが上がりました。
高1で学んだことは、高3でセンター試験を解くときも記憶に残っていました。楽しんで覚えたことは、1年のブランクがあっても定着しているものです。古文の参考書などを読まなくても、授業に出ていれば助動詞の識別などが印象に残って、「どうして識別ができないのかわからない」というレベルにまで到達しました。
恩田:
僕が古文を受講したのは高2の1年間でした。春期講習でひと通りの文法が頭に入った状態になり、あとは授業を楽しむために通っていたところがあります。
担当の先生は知識が豊富で話が上手でした。内容が的確でわかりやすい上に、ジョークやユーモアを交えた小話があって、その流れで知識も確認してくださったので、関連知識も含めて古文単語を覚えられました。
知識の確認では、答えられないと恥ずかしいですが、答えられると話が弾んで深い話まで聞けます。だから、「しっかり答えて、先生から深い話を聞きたい」というのが毎回復習するときのモチベーションになりました。
担当の先生は知識が豊富で話が上手でした。内容が的確でわかりやすい上に、ジョークやユーモアを交えた小話があって、その流れで知識も確認してくださったので、関連知識も含めて古文単語を覚えられました。
知識の確認では、答えられないと恥ずかしいですが、答えられると話が弾んで深い話まで聞けます。だから、「しっかり答えて、先生から深い話を聞きたい」というのが毎回復習するときのモチベーションになりました。
■グノーブルの先生
先生方はどのように皆さんの勉強と関わってくれましたか?
グノの授業が楽しかったのは、知ることの喜び、考えることの喜びを、先生たちに伝えてもらえたからです
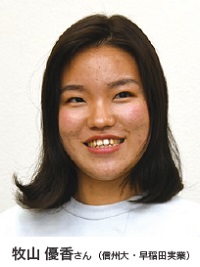
牧山:
グノの先生は全員、2回くらいで生徒の顔と名前を覚えてくださいます。名前を知ってもらえてあててもらえるので、やる気も出るし、「答えないといけない」という使命感も生まれます。
私の英単語力のほとんどは、中3からずっとお世話になった先生のおかげです。大切な単語に関しては何度も語源から教えていただき、あまり面白くないギャグと一緒に記憶に残っています(笑)。英文を前から読む読解力が身についたのもその先生のおかげです。
その先生とは長いおつき合いでしたから、私のことをよくわかってもらえているという安心感がありました。弱いところや課題を何度も指摘していただいたり、個人的にアドバイスをいただいたりしました。直前期には英作文の添削もたくさん対応していただきました。本当に感謝しています。
私の英単語力のほとんどは、中3からずっとお世話になった先生のおかげです。大切な単語に関しては何度も語源から教えていただき、あまり面白くないギャグと一緒に記憶に残っています(笑)。英文を前から読む読解力が身についたのもその先生のおかげです。
その先生とは長いおつき合いでしたから、私のことをよくわかってもらえているという安心感がありました。弱いところや課題を何度も指摘していただいたり、個人的にアドバイスをいただいたりしました。直前期には英作文の添削もたくさん対応していただきました。本当に感謝しています。
北脇:
確かに、先生が僕たちの名前を覚えてくれて、初回の授業から名前であててもらえるのは良かったです。先生が生徒一人ひとりを見ようとしてくださる姿勢を感じられて、すごいと思うと同時に、感謝の気持ちも生じました。
英語も数学も古文も、先生が面白い話やジョークを言ってくださって、授業が楽しくなる工夫がちりばめられていました。苦痛の少ない大学受験ができたのは、グノの先生方のおかげです。
英語も数学も古文も、先生が面白い話やジョークを言ってくださって、授業が楽しくなる工夫がちりばめられていました。苦痛の少ない大学受験ができたのは、グノの先生方のおかげです。
恩田:
グノの授業が楽しかったのは、知ることの喜び、考えることの喜びを、先生方に伝えてもらえたからです。
大学受験に必要だから勉強するという面もありますが、英語から得られるいろいろな知識や情報は日本語で獲得できるものよりも断然多くて、しかも、思わぬ視点や考え方と出合えます。そういうことは、グノで扱った英文から十分に感じとれました。
将来英語を駆使していろいろな人と交流して、いろいろな知見を増やしたいと思っています。グノの先生から、英語を通して見える世界がどんなものかを教えてもらえましたが、僕は、そういう授業をしてくださった先生を本当に尊敬しています。
先生方の熱意もすごいんです。高3の頃は延長があたりまえの授業スタイルでしたが、面白い授業を受けていると、いつの間にか「えっ、もうこんな時間?」となっていることが多かったです。先生が本当に熱心なので、「僕もがんばるぞ」とも思っていました。
大学受験に必要だから勉強するという面もありますが、英語から得られるいろいろな知識や情報は日本語で獲得できるものよりも断然多くて、しかも、思わぬ視点や考え方と出合えます。そういうことは、グノで扱った英文から十分に感じとれました。
将来英語を駆使していろいろな人と交流して、いろいろな知見を増やしたいと思っています。グノの先生から、英語を通して見える世界がどんなものかを教えてもらえましたが、僕は、そういう授業をしてくださった先生を本当に尊敬しています。
先生方の熱意もすごいんです。高3の頃は延長があたりまえの授業スタイルでしたが、面白い授業を受けていると、いつの間にか「えっ、もうこんな時間?」となっていることが多かったです。先生が本当に熱心なので、「僕もがんばるぞ」とも思っていました。
中川:
どの先生の授業からも本当に熱意が伝わってきました。「その熱意に自分も応えないといけない」と思って、がんばり続けられました。
東海林:
グノの授業は空気が引き締まっています。教室の雰囲気をつくるのはどんな先生がどれほど熱意を持っていらっしゃるかによるところが多いように感じます。
グノの英語の授業はずっと集中して、ものすごく頭の冴えた状態で受けられました。ですから、受動的に授業を受けていただけでは得られないものをものすごく学びました。そういう環境をつくってくださった先生に本当に感謝しています。
グノの英語の授業はずっと集中して、ものすごく頭の冴えた状態で受けられました。ですから、受動的に授業を受けていただけでは得られないものをものすごく学びました。そういう環境をつくってくださった先生に本当に感謝しています。
蒲田:
一番感謝しているのは個別対応していただいたことです。グノは他塾に比べて少人数なので面倒見が良かったと思います。僕は毎回質問しにいって、飲み込めない部分が消化できるまで粘りました。それでも先生は嫌な顔をせず、一つひとつ丁寧に教えてくださいました。
しかも先生は、僕たち一人ひとりの状況をしっかり把握して、それに合わせた的確なアドバイスをくださいます。おかげで英語でも数学でも、穴のない受験準備ができたと思います。
しかも先生は、僕たち一人ひとりの状況をしっかり把握して、それに合わせた的確なアドバイスをくださいます。おかげで英語でも数学でも、穴のない受験準備ができたと思います。
今野:
僕も授業前や後でいつも質問していました。メールでもたくさん質問していましたが、先生からはすぐに丁寧な返信が届きました。それには本当に感謝しています。
それから高3のカリキュラムに入った高2の1月から、急に英語の成績が落ち始めてしまいました。最初のクラス分けテストでαからα1に落ち、2回目のテストでα3まで落ちてしまいました。それまでずっと英語が得意科目だと思っていたのに頼みの綱が切れてしまい、絶望的な気持ちにもなりました。
そんなときに支えてくださったのがグノの先生方でした。
ある先生は直接電話で「いつでも頼っていいよ」と声をかけてくださいました。もうひとりの先生はresilience *という言葉を教えてくださいました。「ここで諦めたら何もかも終わってしまう」と思い直し、「粘り強く」努力を続けようと思えました。そして、8月末の最後のクラス分けテストではα1に戻ることができました。
これからの人生も粘り強く、resilience をもって進んでいこうと思っています。
* Gno-let vol.20「巻頭特集」
それから高3のカリキュラムに入った高2の1月から、急に英語の成績が落ち始めてしまいました。最初のクラス分けテストでαからα1に落ち、2回目のテストでα3まで落ちてしまいました。それまでずっと英語が得意科目だと思っていたのに頼みの綱が切れてしまい、絶望的な気持ちにもなりました。
そんなときに支えてくださったのがグノの先生方でした。
ある先生は直接電話で「いつでも頼っていいよ」と声をかけてくださいました。もうひとりの先生はresilience *という言葉を教えてくださいました。「ここで諦めたら何もかも終わってしまう」と思い直し、「粘り強く」努力を続けようと思えました。そして、8月末の最後のクラス分けテストではα1に戻ることができました。
これからの人生も粘り強く、resilience をもって進んでいこうと思っています。
* Gno-let vol.20「巻頭特集」
■医学部の面接
医学部受験の際の面接についてはどんな準備をしましたか?
何かを覚えておいて答えるというよりも、面接官の質問に対して的確に答えるのが大事だと思います
牧山:
信州大は8人の受験生と3人の面接官で行うグループ面接でした。「最初の質問はA さん、次の質問はB さん……」みたいな感じで進みました。
医師を目指す理由とか、印象に残った本とか、自分の強みとか、一般的なことを聞かれました。私は人と喋るのが苦手なわけではなかったので、面接対策はほとんどしませんでした。ただ医師を志望する理由とこの大学を志望する理由だけはしっかり言えるように準備しました。
医師を目指す理由とか、印象に残った本とか、自分の強みとか、一般的なことを聞かれました。私は人と喋るのが苦手なわけではなかったので、面接対策はほとんどしませんでした。ただ医師を志望する理由とこの大学を志望する理由だけはしっかり言えるように準備しました。
中川:
慶應は面接がそれほど重視されていないようだったので、受験勉強では一次試験のために力を注いで、二次の対策は面接の日程発表後から始めました。そうはいってもある程度準備しておかないと緊張するので、学校の先生に頼んで1回模擬面接をしてもらいました。
実際の面接は、調査書に関連することを聞かれたあとは世間話をする程度で、フレンドリーな雰囲気でした。
小論文は、誰もが耳にしたことがあるような問題について問われます。今年は「虐待をどう解決するか?」というテーマでした。小論文もそれほど対策をしていたわけではなく、最近問題になっていることを調べておいたくらいです。
実際の面接は、調査書に関連することを聞かれたあとは世間話をする程度で、フレンドリーな雰囲気でした。
小論文は、誰もが耳にしたことがあるような問題について問われます。今年は「虐待をどう解決するか?」というテーマでした。小論文もそれほど対策をしていたわけではなく、最近問題になっていることを調べておいたくらいです。
東海林:
志望理由書を学校の先生に見てもらって、それを読み込んで口で説明できるようにしました。実際に人と話す練習はあまりしませんでした。
実際、横浜市立大の面接では、「なぜ医師になりたいか?」とか「あなたの長所と短所は何か?」とか「どうしたら短所を改善できるか?」とか、典型的な質問ばかりで、対処には困りませんでした。
ただ、調査書の内容で自分の知らないことを聞かれたのには、少し戸惑いました。僕が通っていた高校が仏教系なので、調査書に仏教について書いてあったらしいんです。でも、面接官が助け舟を出してくれました。誠実に伝えようという姿勢があれば、コミュニケーションが十分に成立すると思います。
実際、横浜市立大の面接では、「なぜ医師になりたいか?」とか「あなたの長所と短所は何か?」とか「どうしたら短所を改善できるか?」とか、典型的な質問ばかりで、対処には困りませんでした。
ただ、調査書の内容で自分の知らないことを聞かれたのには、少し戸惑いました。僕が通っていた高校が仏教系なので、調査書に仏教について書いてあったらしいんです。でも、面接官が助け舟を出してくれました。誠実に伝えようという姿勢があれば、コミュニケーションが十分に成立すると思います。
今野:
僕は推薦で筑波大に受かったので一般入試の面接とは違っています。とはいえ、特殊なわけではなく、面接官ふたりと小さい部屋で面接する形式でした。
面接官の質問は、自分が事前に書いた志望理由書や学校の調査書に基づいたものでした。質問に沿うように答えることだけを心掛けました。
学校の先生に、場を設けていただいて3回面接練習をしました。それと、医師である父が本番前日の夜にも練習を行ってくれました。実際の面接官に年齢も立場も近い父は「きっとこういうことを聞いてくるよ」とアドバイスをくれて、それが本当に役立ったし、安心にもつながりました。
面接官の質問は、自分が事前に書いた志望理由書や学校の調査書に基づいたものでした。質問に沿うように答えることだけを心掛けました。
学校の先生に、場を設けていただいて3回面接練習をしました。それと、医師である父が本番前日の夜にも練習を行ってくれました。実際の面接官に年齢も立場も近い父は「きっとこういうことを聞いてくるよ」とアドバイスをくれて、それが本当に役立ったし、安心にもつながりました。
北脇:
面接の練習として、予備校の面接講座に参加しました。医科歯科大は基本的に面接が点数化されません。だから、特に対策はしないつもりでしたが、親に行った方がいいと言われて講座に参加しました。その講座で医師を志望した動機と医科歯科大を志望した動機はしっかり固めました。
本番は、僕ひとりに対して面接官が3人で、ひとりずつ質問してくる形式でした。最初に自己PR をしましたが、その中で話したことについて聞かれたり、志望動機について聞かれたりしました。何かを覚えておいて答えるというよりも、面接官の質問に対して的確に答えるのが大事だと思います。
本番は、僕ひとりに対して面接官が3人で、ひとりずつ質問してくる形式でした。最初に自己PR をしましたが、その中で話したことについて聞かれたり、志望動機について聞かれたりしました。何かを覚えておいて答えるというよりも、面接官の質問に対して的確に答えるのが大事だと思います。
恩田:
僕も同じく医科歯科大を受験し、準備としては、医師の志望理由と大学の志望理由、高校3年間の経験を事前に文章にしてまとめ、それをうまく話せるようにしました。「第一印象が大事」と言われたので、親と練習したり、自分の姿をビデオに撮って良くない点を矯正したりしました。
北脇君の言う通り、医科歯科大は1対3で最初に自己PR の時間があります。その後いろいろ話すんですが、僕の場合は筑駒の文化祭について踏み込んだ話が始まったので、その場で考えて苦労話やがんばったことなどを話しました。
北脇君の言う通り、医科歯科大は1対3で最初に自己PR の時間があります。その後いろいろ話すんですが、僕の場合は筑駒の文化祭について踏み込んだ話が始まったので、その場で考えて苦労話やがんばったことなどを話しました。
蒲田:
東大の面接はきつくないと聞いていました。なので志望理由など一般的に想定される質問を準備しておいたくらいです。本番では、僕が「感染症の研究をしたい」と言ったら、東大の先生からは、「感染症研究は地味な分野だけれど、やり続ける自信はありますか?」とか「他の分野をやる気はありますか?」といった質問をされました。自分のできる範囲で誠実に答えることを心掛けました。
■後輩へのアドバイス
これから受験する後輩に向けて一言お願いします
グノでは英文の内容も、自分の成長も、楽しみながら勉強できます。その経験があれば受験も乗り切れます
恩田:
グノは音読の大切さを教えてくれますし、実際にその通りに音読すると大きな武器になります。グノで学ぶ英語は将来にも活かせると思います。大学受験だけでなく、背景知識などにもアンテナを張りながら、いろいろなものに興味を持って学んでください。
蒲田:
グノは数学も英語もきちんと教えてくれる塾です。少人数で生徒一人ひとりと向き合ってくれるので、その環境を利用しましょう。授業内容の80%、90%が自分のものになるように、納得するまで質問することを積み重ねれば、確実に実力がつきます。
北脇:
グノに通ってきちんと授業を聞くことに加えて、自主的な姿勢を忘れないことが大切だと思います。英語の学習に関しては、グノのやり方での音読をすれば、絶対に力が伸びます。医学部だからといって医学部受験の勉強に特化しなくても、グノを信じてがんばれば楽しく実力を伸ばせて、どこの問題にでも太刀打ちできるようになります。
今野:
高3になると、既卒生も模試に参入してきて一気に成績が落ちる可能性があります。僕自身はグノのクラス分けテストでも落ちてメンタルがどん底になりました。そんなときはひとりでがんばろうとしすぎない方がいいと思います。グノの先生はしっかり支えてくださいます。心が救われるような、本当に素晴らしい対応をしてくださって、僕は感謝の気持ちでいっぱいです。
先生方は、僕たち生徒が思っているよりも、生徒一人ひとりのことを考え、しっかり見ていてくださいます。グノに通っている後輩たちにも、先生方に普段から質問や相談をして、積極的に頼って、最後には自分のやってきたことを信じて試験に臨んでもらいたいと思います。
先生方は、僕たち生徒が思っているよりも、生徒一人ひとりのことを考え、しっかり見ていてくださいます。グノに通っている後輩たちにも、先生方に普段から質問や相談をして、積極的に頼って、最後には自分のやってきたことを信じて試験に臨んでもらいたいと思います。
東海林:
グノはとても楽しい塾です。授業が楽しくて、音読しているうちに英語の力がついてきて、さらに授業でいろいろなことを吸収できるようになって、というサイクルを繰り返しているうちに、英語が自分の中にしっかり根づいていきます。
英語が自分の中に根づいて、英文を英語のまま読めるようになってくると、知らない単語も文脈の中で推測できるようになってスラスラ内容が入ってきます。そのうちに今度は文章の内容に対して深く考えられるようにもなれます。
グノでは英文の内容も、自分の成長も、楽しみながら勉強できますし、その経験があれば受験勉強も乗り切れます。がんばってください。
英語が自分の中に根づいて、英文を英語のまま読めるようになってくると、知らない単語も文脈の中で推測できるようになってスラスラ内容が入ってきます。そのうちに今度は文章の内容に対して深く考えられるようにもなれます。
グノでは英文の内容も、自分の成長も、楽しみながら勉強できますし、その経験があれば受験勉強も乗り切れます。がんばってください。
牧山:
特に女子は数学が最初から最後まで苦手なことが多いです。でも、医学部は数学と理科と英語の配点が1対1対1であることが多いので、数学が苦手だからといって諦めないでください。実際、私は数学で失点してしまいましたが、英語がずっと安定していたので穴埋めできました。特に英語は、できるようになると落ちにくい科目なので、英語を安定させれば受かると思います。
グノでしっかり復習していけば、英語は力がついて安定し、自分の強みになってくれます。グノの環境をしっかり利用して、復習もしっかりして、英語を伸ばしていってください。
グノでしっかり復習していけば、英語は力がついて安定し、自分の強みになってくれます。グノの環境をしっかり利用して、復習もしっかりして、英語を伸ばしていってください。
中川:
英語を受験勉強と捉えるとつまらないし続きません。一方、グノは、受験のための勉強というより、英語が楽しくなるような勉強をさせてくれる塾です。だから、授業時間が長くても、面白いから長く感じないし、楽しく通い続けられるはずです。
僕の場合、高3の冬の模試で慶應がE 判定で、「ヤバイ」と思いましたが、最終的には合格しました。医学部に限らず、最後まで努力すれば、大学は入学を認めてくれます。逆に、合格できる実力があっても、最後まで努力しないと結果はついてきません。周りを見ても、真面目に勉強を続けていた人は受かっているし、途中で油断した人は結果が出ていませんでした。
最後まで努力できるかできないかで結果が変わってくると思います。そしてそれをし続けるコツは、勉強の中にいつも楽しみを見いだすことだと思います。
僕の場合、高3の冬の模試で慶應がE 判定で、「ヤバイ」と思いましたが、最終的には合格しました。医学部に限らず、最後まで努力すれば、大学は入学を認めてくれます。逆に、合格できる実力があっても、最後まで努力しないと結果はついてきません。周りを見ても、真面目に勉強を続けていた人は受かっているし、途中で油断した人は結果が出ていませんでした。
最後まで努力できるかできないかで結果が変わってくると思います。そしてそれをし続けるコツは、勉強の中にいつも楽しみを見いだすことだと思います。