国立大学医学部 Part 1
ホーム > Gno-let > Gno-let23 > 国立大学 医学部 Part1
| 網谷 史人さん(北海道・開成) | 岡本 昌大さん(千葉・攻玉社) |
| 黒田 南帆さん(筑波[公募制推薦]・都立小石川中等教育) | 藤田 悠佑さん(富山・サレジオ学院) |
| 藤田 理彩子さん(東北[AO入試Ⅱ期]・立教女学院) | 宮﨑 壮さん(千葉・開成) |
| 渡辺 藍子さん(東北・白百合学園) | |
■医学部志望の動機
皆さんが医学部を志望した動機を教えてください。
ドキュメンタリーを見て「自分もこういう医師になりたい」と思いました
宮﨑:
父が医師で、物心ついたときから父にずっと憧れていました。父の背中を追って、当然「自分も医師になる」と思っていました。
岡本:
僕の親も医師なので、幼い頃から医師に憧れていました。ずっと「医師になりたい」と思っていたんです。
藤田(悠):
僕はふたりと違って、家族や親戚に医師はいません。テレビのドキュメンタリー番組で、珍しい病気でなかなか診断してもらえなかった患者さんが、名医によって病気の原因を突き止めてもらった、という話がありました。これを見て「かっこいい」「自分もこういう医師になりたい」と思ったのが医学部志望の動機です。
藤田(理):
私も「人の役に立ちたい」という思いから医学部を志望しました。人の役に立つ仕事はいろいろありますが、目の前で苦しんでいる人を直接助けられるのは医師です。
小学生の頃からぼんやりと医師に憧れていました。
小学生の頃からぼんやりと医師に憧れていました。

黒田:
同じ女性の立場から女性の患者さんの役に立ちたいと思っています。だから、小児科や婦人科の医師を目指しています。
網谷:
僕は理系でしたが、文系科目の方が得意でした。「文系の要素が使えて、人の役に立つ仕事に就きたい」と思い、医学部が志望先になりました。現役時代は東大を目指していました。でも、浪人中に病気になったことがきっかけで医師の素晴らしさを知り、進路を変えました。
渡辺:
私も自分の病気がきっかけです。5歳のときから難聴で耳鼻科に通っていたので、「耳鼻科の医師になりたい」と強く思っていました。
■入塾のきっかけ
なぜグノーブルを選ばれたのでしょうか?
大量の宿題を辛そうにやっている人たちを見て、そういう塾でなくてよかったと思っていました
黒田:
スタートダッシュ講座*から続けています。小6の3月に親がグノに決めました。英語が有名なので英語だけ入る予定でしたが、説明会での数学の先生のお話がとても面白くて、「数学も!」と思いました。
英語と数学はスタートダッシュ講座からずっと続けていて、途中で他の科目も追加受講しました。
グノにない科目を大手予備校で受けたことがありましたが、「黒板が遠い授業を受け続ける必要はない」と感じました。生徒を見下ろすような先生の態度にも反感を持ってしまって、授業に集中できなかったのもあります。
グノの授業は少人数制です。先生と生徒のやり取りで授業は進むし、添削もしてもらえて、勉強に集中できる環境です。それに、先生は生徒と同じ目線でいてくださって、親しみやすかったです。
*新中1生対象の講座(2~3月に開講)。
英語と数学はスタートダッシュ講座からずっと続けていて、途中で他の科目も追加受講しました。
グノにない科目を大手予備校で受けたことがありましたが、「黒板が遠い授業を受け続ける必要はない」と感じました。生徒を見下ろすような先生の態度にも反感を持ってしまって、授業に集中できなかったのもあります。
グノの授業は少人数制です。先生と生徒のやり取りで授業は進むし、添削もしてもらえて、勉強に集中できる環境です。それに、先生は生徒と同じ目線でいてくださって、親しみやすかったです。
*新中1生対象の講座(2~3月に開講)。
渡辺:
私も黒田さんと同じでスタートダッシュ講座で数学と英語を受講しました。グノに通っていた中学の先輩から教えてもらったことを踏まえて、母が持ってきた資料の中から選びました。
もともと「数学を補強したい」と思っていて、通常授業は数学だけとりました。英語と古文の受講をスタートしたのは高1からです。中1から通っていてグノがとても好きだったので、他塾と比べることはしませんでした。
もともと「数学を補強したい」と思っていて、通常授業は数学だけとりました。英語と古文の受講をスタートしたのは高1からです。中1から通っていてグノがとても好きだったので、他塾と比べることはしませんでした。
藤田(理):
姉の勧めで私は中1からグノの季節講習を受けていました。「自分に合っている」と思って、中2から英語の通常授業、続いて数学も受けることにしました。
英語に関しては、勉強好きではない姉が「楽しい」と言っていたので、「この塾で間違いない」と思いました。
数学は他塾の授業も受けてみましたが、受け終わったあとに何も残っていなくて「合っていない」と感じ、グノに統一しました。グノは不明点があるときの個別対応がとても良かったです。
英語に関しては、勉強好きではない姉が「楽しい」と言っていたので、「この塾で間違いない」と思いました。
数学は他塾の授業も受けてみましたが、受け終わったあとに何も残っていなくて「合っていない」と感じ、グノに統一しました。グノは不明点があるときの個別対応がとても良かったです。

岡本:
僕の場合、勧めてくれたのは兄でした。兄は4歳上でしたが、グノに通って英語の力が伸びていたので、塾選びに迷いはありませんでした。
学校の授業に慣れてきた中1の夏から英語で入りました。
学校の授業に慣れてきた中1の夏から英語で入りました。
宮﨑:
僕は中3の夏期講習から英語を受講し始めました。学校の英語をあまりにもサボっていたら何もできなくなって、母からグノを勧められました。
ついでに数学も受講してみたら、授業がとても楽しくて、そのまま続けました。高2からは物理もとりました。
グノに入ったあとは、「グノしかない」と気に入って通うことができました。特に大量の宿題をつらそうにやっている人たちを見て、そういう塾でなくて良かったと思っていました。
ついでに数学も受講してみたら、授業がとても楽しくて、そのまま続けました。高2からは物理もとりました。
グノに入ったあとは、「グノしかない」と気に入って通うことができました。特に大量の宿題をつらそうにやっている人たちを見て、そういう塾でなくて良かったと思っていました。
藤田(悠):
僕の場合はグノに通っていた姉から勧められて、高1のときに季節講習を受け、グノの方針が自分に合っていることを確認した上で、高2の春から英数で入塾しました。
網谷:
高3のときに友人の紹介で入りました。6月まで国語の受験勉強を何もせずにいて、「ヤバイ」と思って、「駆け込み古文・漢文」という短期の基礎講座を受けました。それで実際に力が伸びたので、秋から東大国語のお世話になりました。結局、現役のときには合格できませんでしたが、グノの環境が気に入ったので、浪人してからもグノに通い続けることにしました。
グノには学校の友人が何人も通っていて受験の成果を上げていましたし、「英語はα5(基礎クラス)でも楽しい」と評判も良かったので英語、数学もグノに通うことにしました。
グノには学校の友人が何人も通っていて受験の成果を上げていましたし、「英語はα5(基礎クラス)でも楽しい」と評判も良かったので英語、数学もグノに通うことにしました。
■グノーブルの英語
英語の授業はどんな雰囲気だったのか教えてください。
答案はその場で添削、すぐに解説。記憶が新鮮なので解説を聞くときにも集中できました
渡辺:
高1で入塾したときのクラスはα3*でしたが、その頃は、前回の復習をしていれば授業中の先生の質問にも答えられましたし、クラスも少しずつ上がっていきました。ところが高2の冬から要約演習が入ってくると、上位のクラスにいる周りの人との差がはっきりわかって泣けてくることもありました。
要約は英文が読めているだけではまとめられません。背景的な知識が欠けていたり、英語の論理展開の仕方がわかっていなかったりすると、がんばって答案を書いてもほとんど点数にならないのです。
でも、その悔しさをばねに、毎回解説をしっかり理解した上での復習をして、次の演習にまた全力を注いでいました。それでも点数が上がらないという週がしばらく続きました。
点数にならないことは苦しいのですが、グノの授業は興味深い英文をたくさん読めるし、先生には熱意があって解説も面白いので通うこと自体はずっと楽しかったです。それに、問題は厳しくても先生は優しくて、「解説が理解できるなら、いつかそのレベルまでは必ず登れる」という先生の言葉を励みに努力を続けていました。
*この学年の高1時の英語は、α(最上位)から、α1、α2、α3、α4の設定。その後の学年でα5も追加設定されました。
要約は英文が読めているだけではまとめられません。背景的な知識が欠けていたり、英語の論理展開の仕方がわかっていなかったりすると、がんばって答案を書いてもほとんど点数にならないのです。
でも、その悔しさをばねに、毎回解説をしっかり理解した上での復習をして、次の演習にまた全力を注いでいました。それでも点数が上がらないという週がしばらく続きました。
点数にならないことは苦しいのですが、グノの授業は興味深い英文をたくさん読めるし、先生には熱意があって解説も面白いので通うこと自体はずっと楽しかったです。それに、問題は厳しくても先生は優しくて、「解説が理解できるなら、いつかそのレベルまでは必ず登れる」という先生の言葉を励みに努力を続けていました。
*この学年の高1時の英語は、α(最上位)から、α1、α2、α3、α4の設定。その後の学年でα5も追加設定されました。
宮﨑:
僕は英語が苦手で、授業中にあてられても答えられないことが多かったんですが、グノの授業は基本的に楽しく受けていました。
先生がどんどん生徒を授業に巻き込んでくれるし、難しい問題にもたまに答えられるとうれしいので、もっと授業を楽しみたくて念入りに復習をしました。徐々に英語力も上がってきて、最後の方は質問にも普通に答えられるようになりました。
先生がどんどん生徒を授業に巻き込んでくれるし、難しい問題にもたまに答えられるとうれしいので、もっと授業を楽しみたくて念入りに復習をしました。徐々に英語力も上がってきて、最後の方は質問にも普通に答えられるようになりました。

黒田:
先生方は私たちをあてることで、どんどん授業に参加させてくださるので、グノの授業はとても集中できるし、質問に答えられるとうれしくなります。添削してもらって点数が高かったり、いいコメントをいただけたりするときの喜びもありました。
中学の頃は、受験はまだまだ先でしたが、授業の雰囲気が好きで、それが「英語を勉強しよう」という活力になっていました。
高校生になってから一度、α3くらいまでクラスが落ちたことがありました。スタートダッシュ講座から通っていた友達はαやα1にいて、「みんなできているのに」とショックでした。
でも、グノの場合クラスが落ちても、先生が違うだけでとても良い授業だし、先生が親身になってくださるのは同じなのでがんばれて、上のクラスに戻ることができました。
中学の頃は、受験はまだまだ先でしたが、授業の雰囲気が好きで、それが「英語を勉強しよう」という活力になっていました。
高校生になってから一度、α3くらいまでクラスが落ちたことがありました。スタートダッシュ講座から通っていた友達はαやα1にいて、「みんなできているのに」とショックでした。
でも、グノの場合クラスが落ちても、先生が違うだけでとても良い授業だし、先生が親身になってくださるのは同じなのでがんばれて、上のクラスに戻ることができました。
岡本:
グノには授業の開始前からだらけた雰囲気がありません。それに、いったん授業が始まるとさっと引き締まります。授業の最初に演習をして、その答案は授業時間内に添削してもらえるし、すぐに解説もしてもらえます。記憶が新鮮なので解説を聞くときにも集中できました。解説は先生と生徒のやり取りで進んでいきますから集中はとぎれません。
グノの授業が楽しいというのは、参加しているという意識が持てて、ずっと集中できるからです。
グノの授業が楽しいというのは、参加しているという意識が持てて、ずっと集中できるからです。
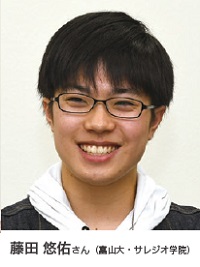
藤田(悠):
グノでは周りの雰囲気で、こっちの気も引き締まりました。
僕の場合、英語が比較的得意で数学が苦手だったため、英語の勉強時間を数学にまわすこともありました。それでも、周りの様子がよくわかるので、授業中は常に真剣になれました。演習しているときに、自分はまだ解き終わっていないけど周りの人たちは終わっているらしいとか、周りの人が先生の問いかけにどんどん答えていくとか、いい刺激がいつもありました。
僕の場合、英語が比較的得意で数学が苦手だったため、英語の勉強時間を数学にまわすこともありました。それでも、周りの様子がよくわかるので、授業中は常に真剣になれました。演習しているときに、自分はまだ解き終わっていないけど周りの人たちは終わっているらしいとか、周りの人が先生の問いかけにどんどん答えていくとか、いい刺激がいつもありました。
網谷:
復習に集中できる点もグノの特徴です。
グノでは毎回の教材はその日に配られ、それを授業内で演習して解説を聞きます。持って帰った教材は、復習して1週間で自分のものにすることに集中できます。
予備校の英語は文法理解に寄りすぎていて、長文を1週間にひとつだけというのがほとんどです。レベルが高くて面白い英文を毎週一定量提供してくれるのはグノくらいです。グノでは解説が英文の背景にまで及びます。英文の内容にこれだけ焦点を当てるのもグノの特徴です。本当に楽しめる授業でした。
あと、グノの先生の板書が好きでした。写すのに時間がかかる丁寧すぎる板書ではなく、簡潔だけれどわかりやすい板書だったと思います。
グノでは毎回の教材はその日に配られ、それを授業内で演習して解説を聞きます。持って帰った教材は、復習して1週間で自分のものにすることに集中できます。
予備校の英語は文法理解に寄りすぎていて、長文を1週間にひとつだけというのがほとんどです。レベルが高くて面白い英文を毎週一定量提供してくれるのはグノくらいです。グノでは解説が英文の背景にまで及びます。英文の内容にこれだけ焦点を当てるのもグノの特徴です。本当に楽しめる授業でした。
あと、グノの先生の板書が好きでした。写すのに時間がかかる丁寧すぎる板書ではなく、簡潔だけれどわかりやすい板書だったと思います。
■グノーブルの音読
英語の指導では音読が重視されていますが、皆さんはどのように取り組みましたか?
最初は音読の効果を信じていませんでしたが、実際にスピードが一段速くなって驚きました
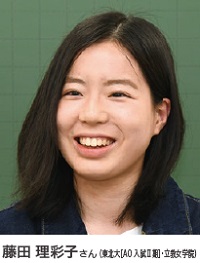
藤田(理):
授業で扱う英文は毎回いろいろあって、内容が面白くていつも楽しみでした。ジャンルも、つい最近の出来事から文学的なもの、科学的なものなど様々でした。
ただ、要約演習で扱われる英文には難しいものが多くて毎回苦労していました。私は「英語ができる」と思っていましたが、深い内容の英文を正確に読むという点には大きな課題があるんだとわかって落ち込んだ時期もあります。先生に「音読を続けていれば伸びる」と何度もおっしゃっていただいて、その言葉を信じてがんばりました。
ただ、要約演習で扱われる英文には難しいものが多くて毎回苦労していました。私は「英語ができる」と思っていましたが、深い内容の英文を正確に読むという点には大きな課題があるんだとわかって落ち込んだ時期もあります。先生に「音読を続けていれば伸びる」と何度もおっしゃっていただいて、その言葉を信じてがんばりました。
宮﨑:
他塾の人たちに「音読している?」と聞くと、「何言っているの?」という顔をされます。音読はグノの特徴です。そして、グノの音読を続けると着実に英語の力を伸ばせます。入試本番でもかなりのスピードで速読できて、音読の効果を実感していました。
藤田(悠):
僕は高3の夏から毎日欠かさず音読をしました。音読をしていると、「英語を英語のまま読む」ことができるようになって、読むスピードと精読力が上がっていきました。英文を速く読めれば、問題を解くことに時間を当てられて、結果的に試験の点数もアップします。
岡本:
僕も高3になってから、毎日欠かさず音読していました。英文を書いた本人の気持ちになって音読し、英文全体の主張や、その主張をするためにどんな組み立てをして、どんな具体例を挙げているかなどを意識するようにしていました。
自分が成長できているかどうかは、毎週の要約演習で確認できるのが良かったです。
自分が成長できているかどうかは、毎週の要約演習で確認できるのが良かったです。
藤田(理):
私も以前から音読していましたが、パーッと読んでいるだけでした。でも、言葉の使い方や内容の組み立てなどを意識しながら音読しないと効果が薄いんです。
このことに気づいて音読の方法を改めたら、確かに読むスピードが速くなるだけではなくて、正確な読み方もできるようになりました。黙読だと読み飛ばしてしまうことでも、声を出す音読では、複数形のs とか前置詞などの細かなことまで意識できるし、抑揚や強弱などを変えられるので深い読み方もできるようになります。
このことに気づいて音読の方法を改めたら、確かに読むスピードが速くなるだけではなくて、正確な読み方もできるようになりました。黙読だと読み飛ばしてしまうことでも、声を出す音読では、複数形のs とか前置詞などの細かなことまで意識できるし、抑揚や強弱などを変えられるので深い読み方もできるようになります。
渡辺:
音読は続けているとやった分だけ効果が出て、サボってしまうとサボった分だけ英語力が下がって読めなくなります。よく先生が「語学はスポーツや楽器の練習に似ている」とおっしゃっていましたが、サボれば下がるし、やれば上がるという面でも似ています。
音読するとき、授業の解説を思い出しながらやっていると、それが効率的な復習になりますが、さらに、GSL*はネイティブが読み上げているので、その抑揚や強弱も参考にできます。「こういうときにここを強調する」というのがわかって、英語で伝えるコツにも気づきます。
* GSL(Gnoble Sound Laboratory):中1から高3までの6学年すべてに毎週用意されているオリジナルの英語音声教材。
音読するとき、授業の解説を思い出しながらやっていると、それが効率的な復習になりますが、さらに、GSL*はネイティブが読み上げているので、その抑揚や強弱も参考にできます。「こういうときにここを強調する」というのがわかって、英語で伝えるコツにも気づきます。
* GSL(Gnoble Sound Laboratory):中1から高3までの6学年すべてに毎週用意されているオリジナルの英語音声教材。
黒田:
私は音読をずっとやっていませんでした。高3でα1に戻ったとき、要約の添削でクラスでビリくらいの点数を叩き出し続けて、「さすがにまずい」と思って音読に初めて取り組みました。
音読をしたからといってすぐに成績が上がるものではなく、9~ 10 月の受験ギリギリになって、要約や模試の点数も上がっていきました。読むのも速くなって、「もっと早くから音読をやっておけば良かった」と後悔しました。
音読をしたからといってすぐに成績が上がるものではなく、9~ 10 月の受験ギリギリになって、要約や模試の点数も上がっていきました。読むのも速くなって、「もっと早くから音読をやっておけば良かった」と後悔しました。
網谷:
僕の場合、音読を始めて3か月くらいで、グッと読みのスピードが上がる瞬間がありました。音読の効果を最初は信じていませんでしたが、実際にスピードが一段速くなって驚きました。
それに、音読をしていると気づけることがたくさんあります。例えば知っている単語でも「こういう使い方をするんだ」と、その言葉の生きた意味を吸収できます。
それに、音読をしていると気づけることがたくさんあります。例えば知っている単語でも「こういう使い方をするんだ」と、その言葉の生きた意味を吸収できます。
■英単語の覚え方
受験では数多くの英単語を暗記しなければならないと思いますが、どのように乗り越えたのでしょうか?
「役に立たない」と思って「単語帳」をやめました
藤田(悠):
音読をしていれば単語も覚えられます。しかも、英文の中で自然に使われている単語に触れているので生きた使い方が身につきます。
音読では同じ英文を繰り返し読むので、いくつもの英文が自然に頭に入ってしまいます。記憶した言い回しは英作文でも応用できるようになります。
受験が終わってから市販の単語帳を見てみたら、わかっている単語ばかりでした。単語帳を使わないで受験を突破できたのはありがたかったです。
音読では同じ英文を繰り返し読むので、いくつもの英文が自然に頭に入ってしまいます。記憶した言い回しは英作文でも応用できるようになります。
受験が終わってから市販の単語帳を見てみたら、わかっている単語ばかりでした。単語帳を使わないで受験を突破できたのはありがたかったです。
岡本:
同感です。音読中に文章内の単語を覚えてしまうので、単語帳なしでも英語ができるようになります。
授業では語源から単語の説明を受けているので、その単語の派生的な意味や関連語も覚えやすいし、音読していると授業中のそういう解説も頭をよぎって、いい復習になりました。
授業では語源から単語の説明を受けているので、その単語の派生的な意味や関連語も覚えやすいし、音読していると授業中のそういう解説も頭をよぎって、いい復習になりました。
網谷:
グノに入る前は単語帳を使っていましたが、何しろ1周するだけでもものすごく時間がかかります。それなのに2周目に入ると、忘れている単語の多さに愕然とします。単語帳の暗記はやっていてもつまらない上に、効率の悪い覚え方です。
グノに入ってからは単語帳を使わなくなりました。授業での語根を使った単語の解説は驚きでした。ひとつの語根から仲間の単語がどんどん黒板上で展開されていく様子は手品のように面白かったです。興味が持てるものは印象にも残りやすく、毎晩寝る前に授業の英文を音読しているうちに単語も無理なく覚えられるようになりました。
グノに入ってからは単語帳を使わなくなりました。授業での語根を使った単語の解説は驚きでした。ひとつの語根から仲間の単語がどんどん黒板上で展開されていく様子は手品のように面白かったです。興味が持てるものは印象にも残りやすく、毎晩寝る前に授業の英文を音読しているうちに単語も無理なく覚えられるようになりました。

宮﨑:
僕も以前は単語帳をやっていましたが、単語帳に書かれている日本語の意味が実際の英文の中ではうまく当てはまらないことが多く、結局、辞書で改めて確認しなければなりませんでした。語源の知識が増えてくれば文脈の中で推測できるようになるし、音読した英文との関連があると意味を思い出しやすくもなります。
藤田(理):
単語帳に載っている意味は限られています。実際の長文では、単語帳に書かれている意味と全然違うことがよくあって、途中で「役に立たない」と思い単語帳をやめました。
学校では強制的に単語帳を暗記させられていましたが、それでスラスラ英文が読めるようになったとはとても言えません。結局は、グノのやり方で、つまり単語帳を使わずに受験を終えたに等しいです。
学校では強制的に単語帳を暗記させられていましたが、それでスラスラ英文が読めるようになったとはとても言えません。結局は、グノのやり方で、つまり単語帳を使わずに受験を終えたに等しいです。
渡辺:
私の学校では単語帳が配られて、毎週テストがありました。でも私はその単語帳はほとんど使わず、グノで教わった語源を中心に、自分で小さなノートに出てきた単語をまとめていきました。「これは前にもやったよね」と先生に言われたときにさっと見返しやすいようにしていて、それがとても役立ちました。
黒田:
私の学校も単語帳のテストが毎週あって、一応単語帳をやりましたが、テストの直前に頭に叩き込んだだけです。結局、グノで作った語源ノートで覚えた単語がほとんどでした。
グノの授業では、前の週に出た単語が次の週にもまた出るので、2~3週間同じ単語を見続けることになります。それで確実に定着しました。
グノの授業では、前の週に出た単語が次の週にもまた出るので、2~3週間同じ単語を見続けることになります。それで確実に定着しました。
■英語の力が伸びた時期
普段の努力が成績の向上として実感できたのはいつ頃からだったのでしょうか?
高3で英検準一級をぶっつけ本番で受験。余裕を持って合格し、改めてグノのすごさを実感しました
黒田:
もともと英語の点数が他の科目と比べて極端に低いわけではありませんでした。でも、グノの生徒はみんな英語ができて、同じ学校のグノ生も英語はとても偏差値が高かったので、「自分は英語ができないのかな」と思っていました。
それが変化したのは高3の10 月頃でした。英語を読むのが速くなって、要約演習でも筆者の主張や文の構成がきれいにわかるようになりました。「英語ができるようになったんだ」という自信を持てる状態で受験に臨めました。
それが変化したのは高3の10 月頃でした。英語を読むのが速くなって、要約演習でも筆者の主張や文の構成がきれいにわかるようになりました。「英語ができるようになったんだ」という自信を持てる状態で受験に臨めました。
渡辺:
グノに通う前は、学校の勉強だけをしていました。周りの人たちは塾に通っていて、その差を意識せざるを得なくて、英語があまり好きではありませんでした。
グノに入って授業を受け始めたら、少しずつ成績が上がって、学校でも上のクラスに入れるようになりました。得意になると好きになってくるものです。グノに入っただけで英語ができるようになったわけではなくて、きちんと復習したり音読したりするようになったので、英語力が上がったのだと思います。
グノに入って授業を受け始めたら、少しずつ成績が上がって、学校でも上のクラスに入れるようになりました。得意になると好きになってくるものです。グノに入っただけで英語ができるようになったわけではなくて、きちんと復習したり音読したりするようになったので、英語力が上がったのだと思います。
宮﨑:
渡辺さんの言葉が身に染みます。僕は、高2までグノに通っているだけで、真剣に取り組んでいませんでした。だから、全国模試の結果も悪くて、偏差値は50 いけばいいくらいでした。高3で真剣に取り組むようになってから、10 月の模試で偏差値が60 を超えてきて、ようやくグノの成果が表れてきました。
岡本:
僕も同じです。中学からずっとグノに通っていましたが、復習として音読するようになったのは高3からです。最初はなかなか結果が出なくて、英文が楽に読めるようになってきたと感じられたのは夏過ぎからです。要約演習でも点数が上がってきて自信になりました。
藤田(悠):
僕の場合、伸びを実感したのはもっと遅くて、高3の秋でした。夏から毎日欠かさず音読するようになったら、それまで「時間が足りない」と思っていた模試の英語で時間に余裕が出てきて、英文の内容も頭の中に滞りなく入るようになりました。
大学別のいわゆる冠模試では、英語だけ1桁の順位に入りました。
大学別のいわゆる冠模試では、英語だけ1桁の順位に入りました。
藤田(理):
学校の定期考査が高2からいきなり応用力を問うものに変わって、英文の量もかなり増えました。それでも、私だけは早めに解き終わるので、グノの成果を実感できました。
高3で英検準1級をぶっつけ本番で受験したときも、余裕を持って合格できたので、改めてグノのすごさを実感しました。
高3で英検準1級をぶっつけ本番で受験したときも、余裕を持って合格できたので、改めてグノのすごさを実感しました。
網谷:
高3のときは文法の理解はできていたのに、周りの人と比べて長文を読むスピードが遅く、どうしたらいいのかわからないままでした。
浪人してグノの英語を受講してみて、ようやく英文の読み方がわかりました。音読という英語力を鍛える方法も教えてもらえたので成長できました。
浪人してグノの英語を受講してみて、ようやく英文の読み方がわかりました。音読という英語力を鍛える方法も教えてもらえたので成長できました。
■グノーブルの数学
数学の授業の印象はどうだったでしようか?
グノの授業が楽しいのは、授業をしている先生が一番授業を楽しんでいらっしゃって、その楽しさが伝わってくるからだと思います

渡辺:
グノの数学には中1から通っていて、高1の頃には数学がとても好きになっていました。
私は小学校から付属の一貫校に通っていて中学受験をしていません。ですから、αに上がったときに中学受験組の強さに圧倒され、「あの人たちに負けている」と思いました。でも、グノの授業は本当に楽しくて、劣等感よりも「がんばりたい」という前向きな気持ちで続けられました。
高2から担当していただいた先生の授業を初めて受けたとき、「大学受験までこの先生についていきたい」と思い、数学にさらに一生懸命になれました。その先生には、メンタル面でも支えていただいたことがたくさんありました。
グノの数学はずっと楽しくて、おかげで学校でも好成績を維持できました。数学は受験科目の中で一番安定していて、安心材料になりました。
私は小学校から付属の一貫校に通っていて中学受験をしていません。ですから、αに上がったときに中学受験組の強さに圧倒され、「あの人たちに負けている」と思いました。でも、グノの授業は本当に楽しくて、劣等感よりも「がんばりたい」という前向きな気持ちで続けられました。
高2から担当していただいた先生の授業を初めて受けたとき、「大学受験までこの先生についていきたい」と思い、数学にさらに一生懸命になれました。その先生には、メンタル面でも支えていただいたことがたくさんありました。
グノの数学はずっと楽しくて、おかげで学校でも好成績を維持できました。数学は受験科目の中で一番安定していて、安心材料になりました。
黒田:
私も高1まで渡辺さんと同じクラスで楽しい数学を受けていました。クラスのメンバーは毎回同じなので、その中で切磋琢磨する雰囲気がありました。私が一番で解き終わったらうれしいし、他の人たちが私より先に解き終わったら悔しいという感じで、「勉強しよう」というモチベーションになりました。
高2以降の先生には問題をたくさんいただけたので、他塾の人たちがやっていたような問題集を一冊もやらずにすみました。先生がくださった授業プリントを復習して、さらにプラスアルファでいただけるプリントにも取り組んでいました。
グノの数学の特徴といえばセルフチェックシートです。セルフチェックシートでは、自分と向き合うことになるので、自分の傾向をつかめるという効果もある一方で、分野によっては、いかに自分がダメなのかをつきつけられることにもなります。
疲れたときや他科目の勉強ばかりしていて数学がおろそかになりがちなときに、セルフチェックシートを見て、「きちんとやらないといけない」と自分を奮い立たせていました。
高2以降の先生には問題をたくさんいただけたので、他塾の人たちがやっていたような問題集を一冊もやらずにすみました。先生がくださった授業プリントを復習して、さらにプラスアルファでいただけるプリントにも取り組んでいました。
グノの数学の特徴といえばセルフチェックシートです。セルフチェックシートでは、自分と向き合うことになるので、自分の傾向をつかめるという効果もある一方で、分野によっては、いかに自分がダメなのかをつきつけられることにもなります。
疲れたときや他科目の勉強ばかりしていて数学がおろそかになりがちなときに、セルフチェックシートを見て、「きちんとやらないといけない」と自分を奮い立たせていました。
宮﨑:
確かにセルフチェックシートでは、自分がどんな分野のどういう計算でミスをするのかがわかります。先生も僕たちが書いた内容に目を通して「この問題に対しては、基本的にこれをやろう」といったコメントをつけて返してくださいます。こうした個人的なやり取りができると、「それは絶対にやろう」という気持ちになりました。
先生との距離が特別に近いのはグノの数学の特徴でもあります。クラスによっては人数が英語より随分と少なく、授業中でも先生と仲良く話せました。解説中にも「ここはどうしてそうなるんですか?」と質問できて、その場でいろいろ吸収できました。数学はそれなりに得意でしたが、グノでさらに力を伸ばせました。
先生との距離が特別に近いのはグノの数学の特徴でもあります。クラスによっては人数が英語より随分と少なく、授業中でも先生と仲良く話せました。解説中にも「ここはどうしてそうなるんですか?」と質問できて、その場でいろいろ吸収できました。数学はそれなりに得意でしたが、グノでさらに力を伸ばせました。
藤田(理):
セルフチェックシートでは自分ができないところを細かく分析していくことになって、その効果の大きさを実感しました。問題の解き方やミスしたところなどを実際にセルフチェックシートに書いて残すと、その問題に対する印象が強くなって思い出しやすくなります。模試や入試のときも、「こういう問題をやったな」と思い出され、頭の中にストックした記憶が役立ちました。
私は、学校では「数学がそれなりに得意だ」と思っていましたが、グノだとできなくて、クラス落ちも経験して落ち込みました。でも、先生が親身になって授業や進路の相談に乗ってくださって、それに救われました。
私は、学校では「数学がそれなりに得意だ」と思っていましたが、グノだとできなくて、クラス落ちも経験して落ち込みました。でも、先生が親身になって授業や進路の相談に乗ってくださって、それに救われました。
藤田(悠):
僕は、「全くダメ」という表現がぴったりなくらい数学が苦手でした。でも、グノの授業が楽しかったので、苦手なときにも数学を好きでいられました。
グノの授業が楽しいのは、授業をしている先生が一番授業を楽しんでいらっしゃって、その楽しさが伝わってくるからだと思います。どんなに疲れている日でも一秒も眠くなりませんでした。
グノに入る前は、問題の解説は理解できても、そもそも問題に対する方針の立て方がわからず、どうやったら数学ができるようになるのかをずっと悩んでいました。
グノの解説では、「どうしてその解法を選ぶのか?」に重点が置かれます。道具を自覚的に選んで使うことができるように導いてもらえるのです。グノで解法を学んだら、初見の問題でも「自分にもできる」と徐々に思えるようになりました。
それから、改善点を具体的に捉えられるセルフチェックシートは有意義でした。僕は計算ミスがものすごく多いんですが、「計算ミスが多い」という大まかな捉え方だと、ひたすら計算演習するくらいしか解決策がありませんし、あまり改善につながりません。
でも、セルフチェックシートに細かくびっしり書いていたら、ミスをしやすいときと多少複雑でもミスをしない場合があることが判明しました。具体的な傾向がはっきりすれば、実際そういう場面に出くわしたときに、「いつもミスっている問題だ」と意識してミスを減らせます。
グノの授業が楽しいのは、授業をしている先生が一番授業を楽しんでいらっしゃって、その楽しさが伝わってくるからだと思います。どんなに疲れている日でも一秒も眠くなりませんでした。
グノに入る前は、問題の解説は理解できても、そもそも問題に対する方針の立て方がわからず、どうやったら数学ができるようになるのかをずっと悩んでいました。
グノの解説では、「どうしてその解法を選ぶのか?」に重点が置かれます。道具を自覚的に選んで使うことができるように導いてもらえるのです。グノで解法を学んだら、初見の問題でも「自分にもできる」と徐々に思えるようになりました。
それから、改善点を具体的に捉えられるセルフチェックシートは有意義でした。僕は計算ミスがものすごく多いんですが、「計算ミスが多い」という大まかな捉え方だと、ひたすら計算演習するくらいしか解決策がありませんし、あまり改善につながりません。
でも、セルフチェックシートに細かくびっしり書いていたら、ミスをしやすいときと多少複雑でもミスをしない場合があることが判明しました。具体的な傾向がはっきりすれば、実際そういう場面に出くわしたときに、「いつもミスっている問題だ」と意識してミスを減らせます。
網谷:
僕は浪人時に後期のテスト演習だけ受けました。解法や公式を覚えるだけなら自分でもできますが、自分の答案の良し悪しをプロの方に見てもらいたかったのが受講理由です。
グノのセルフチェックシートは良かったですね。テスト演習が始まる時期は秋で、本番まで時間が限られています。新たに問題集をやるよりも、目の前の一問からどれだけ学べるかが大事な時期なので、そういう意味でセルフチェックシートが有意義でした。
「シートに何を書こうかな?」と意識しながら解説を聞くようになったので、解説を聞いている最中にも自分の中でいろいろなことが整理されました。僕は過去問や模試の復習をするときもセルフチェックシートを書いていて、応用の利く勉強法でした。
グノのセルフチェックシートは良かったですね。テスト演習が始まる時期は秋で、本番まで時間が限られています。新たに問題集をやるよりも、目の前の一問からどれだけ学べるかが大事な時期なので、そういう意味でセルフチェックシートが有意義でした。
「シートに何を書こうかな?」と意識しながら解説を聞くようになったので、解説を聞いている最中にも自分の中でいろいろなことが整理されました。僕は過去問や模試の復習をするときもセルフチェックシートを書いていて、応用の利く勉強法でした。
■グノーブルの物理・化学
物理・化学の授業の特色を教えてください
先生とも距離が近く、学校とは違った角度から考える形式で楽しくて勉強できました
黒田:
物理は少人数クラスで、先生とも距離が近いので、「問題を一緒に解こう」という雰囲気でした。学校では公式を覚えて問題を解くだけですが、グノは現象を発見した人の視点から公式を見るとか、自分で公式を導き出して自分のものにするとか、学校とは違った角度から物理を考える形式で、楽しく勉強できました。受験勉強をしているというよりも、物理の歴史を学んでいるという感覚でした。
化学は、実験が受験勉強の息抜きになって、勉強しているけれども楽しい時間になりました。実験は机上で学ぶよりも実際に見る方が記憶に残りやすいので、勉強効率が良かったです。生で見た実験器具を知らない間に覚えていることも多かったです。学校では高3になると実験をやらなくなりましたが、グノでは直前まで実験をやっていました。後半は1か月に1回くらい、問題演習の合間に小さめな実験を見せていただきました。
化学は、実験が受験勉強の息抜きになって、勉強しているけれども楽しい時間になりました。実験は机上で学ぶよりも実際に見る方が記憶に残りやすいので、勉強効率が良かったです。生で見た実験器具を知らない間に覚えていることも多かったです。学校では高3になると実験をやらなくなりましたが、グノでは直前まで実験をやっていました。後半は1か月に1回くらい、問題演習の合間に小さめな実験を見せていただきました。
宮﨑:
化学は、演習の合間に見せてもらった実験動画もすごく面白かったです。
物理は黒田さんと同じクラスでしたが、先生がとてもフレンドリーでした。僕は周りの存在を忘れるくらい夢中になっていましたが、先生も一緒になって楽しんでくれたので、授業に行くのが毎回楽しみでした。
グノの物理は特殊で、高度な概念を扱うことも結構ありました。でも、それをしっかり復習して、他塾に通う人たちに「この内容を知ってる?」とどや顔で説明することもモチベーションになっていました。おかげで、物理の成績はかなり伸びました。
物理は黒田さんと同じクラスでしたが、先生がとてもフレンドリーでした。僕は周りの存在を忘れるくらい夢中になっていましたが、先生も一緒になって楽しんでくれたので、授業に行くのが毎回楽しみでした。
グノの物理は特殊で、高度な概念を扱うことも結構ありました。でも、それをしっかり復習して、他塾に通う人たちに「この内容を知ってる?」とどや顔で説明することもモチベーションになっていました。おかげで、物理の成績はかなり伸びました。
■グノーブルの国語
医学部志望の皆さんにとって国語の授業はどうだったのでしょうか?
添削も丁寧で、直前の過去問添削も熱心にしてくださいました
渡辺:
高1のときに古文の通常授業を受けました。もともと国語は苦手でしたが、グノの古文は1年だけ受講すれば受験まで勉強の必要がないという方針でしたから、他科目で忙しくなる前にとりました。
パワフルな先生と、優しくていつもニコニコしていらっしゃる先生に習いましたが、英単語と同じで、古文単語も言葉の成り立ちや本来の動作などと関連づけて教えていただいて、とても覚えやすかったです。先生がおふたりとも熱心で「この先生のためにもがんばろう」と思えたこともあって、苦手だった国語も、センター試験本番では9割を超えました。
パワフルな先生と、優しくていつもニコニコしていらっしゃる先生に習いましたが、英単語と同じで、古文単語も言葉の成り立ちや本来の動作などと関連づけて教えていただいて、とても覚えやすかったです。先生がおふたりとも熱心で「この先生のためにもがんばろう」と思えたこともあって、苦手だった国語も、センター試験本番では9割を超えました。
黒田:
高2で古文、高3の季節講習ではセンター国語を2回受けました。古文は苦手ではありませんでしたが、周りの子たちが申し込むのにつられてとったら、授業がとても楽しかったんです。
昔のことを「これは浮気しているわ」などと現代風に先生が表現してくださる生き生きとした授業で、古文がさらに得意になりました。
高3になってから先生に志望動機も見ていただきました。そのときには授業を受けていたわけでもないのに、快く引き受けてくださって本当に助かりました。
センター国語も面白かったです。漢文は自分では全然勉強していませんでしたが、「これだけ押さえておけば、センターは大丈夫」というのを示していただいて、それが本番の武器になりました。
昔のことを「これは浮気しているわ」などと現代風に先生が表現してくださる生き生きとした授業で、古文がさらに得意になりました。
高3になってから先生に志望動機も見ていただきました。そのときには授業を受けていたわけでもないのに、快く引き受けてくださって本当に助かりました。
センター国語も面白かったです。漢文は自分では全然勉強していませんでしたが、「これだけ押さえておけば、センターは大丈夫」というのを示していただいて、それが本番の武器になりました。
網谷:
高3で古文と漢文、東大国語を受けました。
「駆け込み古文・漢文」では、先生の「君たち本当にヤバイ!」から授業が始まりました。そんなヤバイ僕でしたが(笑)、短期間の授業でかなり伸びました。
「ヤバイ」から始まったので、最初は担当の先生を厳しい先生かと思いましたが、実はとても親身な方でした。古文の助動詞を全くわかっていなかった僕を、毎回の授業後に1時間くらい指導してくださって、本当に救われました。日本の古い言葉に造詣が深い先生で教養も深まりました。
東大国語の先生はパワフルで、授業に出席していると、国語力だけでなく、エネルギーまで充電できて、「来週まで勉強がんばるぞ!」と思えました。演習時間があって解説もがっつりという充実した2時間でした。
何よりも僕らが試験会場で書けそうな答案を板書で提示してくださるのが良かったです。予備校の答案は「こんな言葉はとても使いこなせない」という高尚なものが多いですが、グノでは「こういう点のとり方もある」とおっしゃって、受験生が書けそうないろいろなバリエーションの解答を示してくださいました。
添削も丁寧で、直前の過去問添削も熱心にしてくださいました。現役のときに国語だけは本当に実力を伸ばせました。
「駆け込み古文・漢文」では、先生の「君たち本当にヤバイ!」から授業が始まりました。そんなヤバイ僕でしたが(笑)、短期間の授業でかなり伸びました。
「ヤバイ」から始まったので、最初は担当の先生を厳しい先生かと思いましたが、実はとても親身な方でした。古文の助動詞を全くわかっていなかった僕を、毎回の授業後に1時間くらい指導してくださって、本当に救われました。日本の古い言葉に造詣が深い先生で教養も深まりました。
東大国語の先生はパワフルで、授業に出席していると、国語力だけでなく、エネルギーまで充電できて、「来週まで勉強がんばるぞ!」と思えました。演習時間があって解説もがっつりという充実した2時間でした。
何よりも僕らが試験会場で書けそうな答案を板書で提示してくださるのが良かったです。予備校の答案は「こんな言葉はとても使いこなせない」という高尚なものが多いですが、グノでは「こういう点のとり方もある」とおっしゃって、受験生が書けそうないろいろなバリエーションの解答を示してくださいました。
添削も丁寧で、直前の過去問添削も熱心にしてくださいました。現役のときに国語だけは本当に実力を伸ばせました。
■グノーブルの先生
先生方はどのように皆さんの勉強と関わってくれましたか?
グノ生は積極的に質問し、先生方も楽しそうに質問を受けてくださいます。居残っての質問対応も気になさっていないところなんて、他塾ではありえないことですし、ありがたかったです
黒田:
グノの先生は親身になってくださるので、相談や質問も気軽にできました。要望にもいつもすぐに対応していただけました。
授業では、科目の内容だけでなく、例えば扱った英文の背景とか、先生の教養がにじみ出てくる話だったり、先生がその科目のことを大好きなのが伝わってくるような話もしてくださいます。ずっと張り詰めた雰囲気ではなく、息抜きみたいに聞ける話がところどころに入るおかげで、授業にも集中できました。
授業では、科目の内容だけでなく、例えば扱った英文の背景とか、先生の教養がにじみ出てくる話だったり、先生がその科目のことを大好きなのが伝わってくるような話もしてくださいます。ずっと張り詰めた雰囲気ではなく、息抜きみたいに聞ける話がところどころに入るおかげで、授業にも集中できました。
渡辺:
元気で刺激的な先生が多いので、授業を飽きずに聞いていられます。
個人的な質問や相談に対しては、先生が一人ひとりの性格まで理解した上でアドバイスをくださいます。どの先生もきちんと生徒一人ひとりを見てくださるのはグノだけです。
個人的な質問や相談に対しては、先生が一人ひとりの性格まで理解した上でアドバイスをくださいます。どの先生もきちんと生徒一人ひとりを見てくださるのはグノだけです。
藤田(理):
グノの先生は本当に親身になってくださるし、生徒一人ひとりの顔と名前が一致していて、それぞれにどういうところが得意で、どんな弱点があるのかまで把握していらっしゃいます。
AO 入試で宮城に行ったときは授業に出席できず、振替もできなかったのですが、数学の先生が個別に対応してくださいました。うれしかったしありがたかったです。
AO 入試で宮城に行ったときは授業に出席できず、振替もできなかったのですが、数学の先生が個別に対応してくださいました。うれしかったしありがたかったです。
宮﨑:
グノの先生はみんな優しいですね。先生が生徒一人ひとりの答案を添削して、いろいろアドバイスをしてくださるので、「よく見ているな」と思っていました。
それから、授業後のどうでもいい話にまで先生たちはつき合ってくださいました。こういう時間がとても楽しく、受験でピリピリした中でも、会話が弾んで本当に元気が出ました。
それから、授業後のどうでもいい話にまで先生たちはつき合ってくださいました。こういう時間がとても楽しく、受験でピリピリした中でも、会話が弾んで本当に元気が出ました。
藤田(悠):
英語のように比較的人数が多めのクラスでも、先生は一人ひとりをよく見てくださっています。解説の最中も僕たちの表情を見ながら話してくださって、納得できていないときはすぐに気づいてくださり、詳しく説明し直してもらえました。
つまり、それは、わかっていないときにもすぐにバレるということですが(笑)。
つまり、それは、わかっていないときにもすぐにバレるということですが(笑)。
岡本:
初回の授業で顔と名前を覚えてくださるのにはびっくりします。
毎回の添削や授業中のやり取りのことも先生はちゃんと覚えていて、あとになってから「あの頃はまだあんな答案だったけど、今はここまで書けるようになったね」といったお褒めの言葉をいただけたこともあります。本当によく見てくださいます。
中学のときにお世話になった先生と高校になってからお会いしても、先生の方から声をかけてくださいました。
毎回の添削や授業中のやり取りのことも先生はちゃんと覚えていて、あとになってから「あの頃はまだあんな答案だったけど、今はここまで書けるようになったね」といったお褒めの言葉をいただけたこともあります。本当によく見てくださいます。
中学のときにお世話になった先生と高校になってからお会いしても、先生の方から声をかけてくださいました。
網谷:
先生方は1回目の授業で顔と名前だけでなく、志望校まで覚えてくださいます。化学のテスト演習を受けたとき、僕は先生と全然話したことがありませんでしたが、それでも、授業の最終日に相談にいったら、僕の志望校もご存じでしたし、僕が苦手としている分野も把握されていて的確なアドバイスをいただけました。「一人ひとりを見る力がすごいな」と感動しました。
僕は学校でも予備校でも質問するのがとても苦手でした。わざわざ人を呼び止めて聞くのに躊躇してしまうからです。でも、グノ生の皆さんは積極的に質問しているし、先生方も楽しそうに質問を受け付けてくださいます。居残っての質問対応も気になさっていないところなんて、他塾ではありえないことですし、ありがたかったです。
僕は学校でも予備校でも質問するのがとても苦手でした。わざわざ人を呼び止めて聞くのに躊躇してしまうからです。でも、グノ生の皆さんは積極的に質問しているし、先生方も楽しそうに質問を受け付けてくださいます。居残っての質問対応も気になさっていないところなんて、他塾ではありえないことですし、ありがたかったです。
■医学部の面接
医学部受験の際の面接についてはどんな準備をしましたか?
過去に出た質問を踏まえて自分なりの解答を作るという対策をしました
黒田:
筑波大の面接は10 分間と短めです。志望動機や高校での活動、自分の長所など、面接での質問で特に変わったことはありませんでした。
緊張感がある雰囲気の中で、学校の先生が面接の練習をしてくださいました。
緊張感がある雰囲気の中で、学校の先生が面接の練習をしてくださいました。
渡辺:
東北大は2日間試験があって、前日に小作文を3題、A4 の真っ白な紙に書きました。2日目の面接では、小作文で書いた内容をもう一回聞かれ、「つけ足したいことはありますか?」と質問されました。小作文のことを面接で聞かれると知っていたので、私は1日目、小作文で何を書いたかを覚えておいて、あとで復習をしていました。そうしたら、2日目の面接官が「よく覚えているね」と言ってくださいました。面接官がそうおっしゃったことを考えると、小作文の内容を覚えている受験生は毎年それほど多くないのかもしれません。
4つ受けた私大の対策としては、過去に何を聞かれたのかを調べてメモを作りました。
4つ受けた私大の対策としては、過去に何を聞かれたのかを調べてメモを作りました。
藤田(理):
私は東北大のAO 入試Ⅱ期を受けました。先に60 分間で小作文をA4 の紙に2本書いて、面接ではそれについて聞かれました。他にも控室に資料が置いてあって、それに関しても質問されます。高校時代の研究を発表する時間がありましたが、私は何も研究していなかったので、自己PR の時間みたいになりました。学校で勧められて参加したプログラムに行ってきたことを話しました。
対策としては、学校の先生からいろいろアドバイスをいただいて、志望理由書も添削してもらいました。
対策としては、学校の先生からいろいろアドバイスをいただいて、志望理由書も添削してもらいました。
宮﨑:
千葉大では、初日に45 分間で面接資料を作成します。1枚目に自分の経歴を書いて、もう1枚には「医者になるためにあなたはどういうことをするべきか?」の答えを書きます。それを踏まえて2日目に面接があります。
ひとりの面接官と7、8分で面接し、それを3回行いました。最初に「こういうケースがあったとき、それに対する問題点と解決法を自由に言いなさい」という内容の面接カードを渡されて、話し終わったあとは、初日に作成した面接資料に基づいて面接官と話しました。
父が医師で面接官をした経験もあったので相談してみたら、「患者に寄り添う」とか「患者の意見を尊重する」とかの方針で答えれば間違いないとアドバイスされました。
ひとりの面接官と7、8分で面接し、それを3回行いました。最初に「こういうケースがあったとき、それに対する問題点と解決法を自由に言いなさい」という内容の面接カードを渡されて、話し終わったあとは、初日に作成した面接資料に基づいて面接官と話しました。
父が医師で面接官をした経験もあったので相談してみたら、「患者に寄り添う」とか「患者の意見を尊重する」とかの方針で答えれば間違いないとアドバイスされました。
岡本:
僕も千葉大で、宮﨑君と同じく、1日目に面接資料作成、2日目に1対1の面接が3回ありました。与えられたケースで問題点を見抜き、改善策をどうするかを答える内容です。過去に出た質問を踏まえて自分なりの解答を作るという対策をしました。
網谷:
北海道大は面接が点数化されて、理科1科目分の配点です。対策としては、別の予備校の『医学部面接ノート』に基づいて取り組みました。この『医学部面接ノート』には、何が聞かれるのかが詳しく書かれています。
僕のように時間がある浪人生は、医学部専門予備校の面接の講座を夏休みに受講するといいかもしれません。現役生は時間がないので、ニュースをなるべく見るようにして、北大の傾向を知っておくだけでいいと思います。
僕のように時間がある浪人生は、医学部専門予備校の面接の講座を夏休みに受講するといいかもしれません。現役生は時間がないので、ニュースをなるべく見るようにして、北大の傾向を知っておくだけでいいと思います。
藤田(悠):
富山大は集団面接で、面接は点数化されます。二次を少しでも楽にするため、面接をとりにいくつもりでしっかり対策しました。予備校の『医学部面接ノート』にはほぼ全大学の質問事項が載っているので、自分の志望する大学で過去に出題された質問と似た質問をピックアップして、それらへの解答をキーワード化しノートにまとめました。
学校の先生との面接練習では、本番の雰囲気を再現できません。そのため、練習の場として私大を複数受けました。
学校の先生との面接練習では、本番の雰囲気を再現できません。そのため、練習の場として私大を複数受けました。
■後輩へのアドバイス
これから受験を向かえる後輩に向けて一言お願いします
疑問に思ったり、精神的に苦しいと思ったりしたら、すぐにグノの先生に相談してください
網谷:
グノで受講している科目については、グノのやり方を信じてついていけば大丈夫です。
医学部は高得点勝負です。他学部だと数学や物理などの一部の科目ができれば受かることもありますが、医学部は苦手科目を他の科目で取り返すのが難しいです。早くから苦手科目と上手くおつき合いするのが大切です。
それから、センター試験はけっして舐めてかかってはいけません。センターはなるべく高得点を狙いましょう。
医学部は高得点勝負です。他学部だと数学や物理などの一部の科目ができれば受かることもありますが、医学部は苦手科目を他の科目で取り返すのが難しいです。早くから苦手科目と上手くおつき合いするのが大切です。
それから、センター試験はけっして舐めてかかってはいけません。センターはなるべく高得点を狙いましょう。
黒田:
グノの先生に言われたことをきちんとやれば、自然と成績が伸びるし、合格もできます。自分なりの工夫も大事ですが、まずは言われた通りにやることが大切です。
勉強や進路に悩んだり、精神的に疲れたりしたときは、先生に相談してください。授業に関係ないことでも先生は親身に相談に乗ってくださいます。
勉強や進路に悩んだり、精神的に疲れたりしたときは、先生に相談してください。授業に関係ないことでも先生は親身に相談に乗ってくださいます。
渡辺:
黒田さんに同感です。疑問に思ったり、精神的に苦しいと思ったりしたら、すぐにグノの先生に相談してください。グノの先生は私たちの性格も弱点も理解してくださっているので、質問することで、授業では得られないことが得られるはずです。
授業中は、ただ授業を聞くだけでなく、積極的に参加して、「すべて吸収しよう」という姿勢で取り組むことが大切です。
授業中は、ただ授業を聞くだけでなく、積極的に参加して、「すべて吸収しよう」という姿勢で取り組むことが大切です。
藤田(理):
先生のおっしゃることをきちんと実践していれば結果はついてきます。音読をきちんとするとか、セルフチェックシートを書くとか、そういうのを確実に行いましょう。
付属校の人の場合、受験がしんどくて諦めたくなることもあるでしょうが、グノの先生に相談して助けていただきながら、努力し続けることが大切です。
付属校の人の場合、受験がしんどくて諦めたくなることもあるでしょうが、グノの先生に相談して助けていただきながら、努力し続けることが大切です。
岡本:
グノの先生に聞きにいけば、先生はちゃんと目の前の生徒に向かって、話す内容も話し方も工夫して伝えようとしてくださいます。復習の方法ひとつでも1対1で直接話してもらえるとやり方がより明確にわかります。それを忠実に守って勉強していくことで合格を勝ちとれます。
藤田(悠):
グノの授業を信じれば国公立医学部に合格できます。僕は、英語のクラスがEGGS*からでしたが、楽しくて役に立つ授業でした。授業内容もクラスで大きく変わるものではありません。自分のクラスレベルを気にせず、「しっかり復習していれば力がつく」と信じて勉強してください。
* EGGS(English Grammar Green Session for newcomers):英語が苦手になってしまった一般生のための、通常クラスに入る前に英文法の基礎を補完する講座。
* EGGS(English Grammar Green Session for newcomers):英語が苦手になってしまった一般生のための、通常クラスに入る前に英文法の基礎を補完する講座。
宮﨑:
僕は最後まで英語のクラスはα2でしたが、先生は生徒の志望校を踏まえた上でレベルに合った授業をしてくださいますので、どのクラスでも諦めずに勉強してください。
数学も、先生に言われた通りにしっかりやっていれば大丈夫です。グノの先生を信頼していれば絶対に合格できると思います。
数学も、先生に言われた通りにしっかりやっていれば大丈夫です。グノの先生を信頼していれば絶対に合格できると思います。