東京大学文系 Part 1
ホーム > Gno-let > Gno-let23 > 東京大学 文系 Part1
| 伊東 希々さん(文Ⅰ・田園調布雙葉) | 小田切 文さん(文Ⅰ・桜蔭) |
| 芝 崇汰さん(文Ⅱ・麻布) | 清水 瞭さん(文Ⅰ・開成) |
| 鈴木 友貴さん(文Ⅱ・筑波大学附属駒場) | 鈴木 悠太さん(文Ⅰ・麻布) |
| 松下 慧輝さん(文Ⅰ・芝) | |
■入塾のきっかけ
なぜグノーブルを選んだのでしょうか?
塾に学校生活を捧げるのはもったいないと思っていたので、宿題が少ないけれど授業の密度が高いグノに魅力を感じました。
芝:
僕は中3の冬から通いました。高校に進学したら「ちゃんと勉強しよう」と思い、とりあえず英語だけでも塾に入るつもりでした。友達に話を聞いたら「英語ならグノだよ」と言われて、冬期講習を受けてみました。
グノの授業には楽しい雰囲気があって、文法的な解説ばかりしている授業よりも自分に合っていると感じました。
グノの授業には楽しい雰囲気があって、文法的な解説ばかりしている授業よりも自分に合っていると感じました。
清水:
僕は中1から他塾で英語を受講していましたが、文法面に不安があったのでそれを補うために別の塾を探しました。小さい頃に少しだけ海外に住んでいて英語に親しんだ経験があったので、文法ばかり教わることには抵抗もありました。そんな時期にグノの噂を聞いて、新高1で春期講習に参加してみました。
英語を英語として捉えるグノの方針に共感し、「自分の気に入った塾で学びたい」と考えて入塾しました。
英語を英語として捉えるグノの方針に共感し、「自分の気に入った塾で学びたい」と考えて入塾しました。
松下:
グノに入塾したのは高1の夏期講習の英語からでした。それまでは他の英語専門塾に通っていて、そこで英語を楽しんでいましたが、周りから刺激を受けられる環境ではありませんでした。
英語に強い塾を探していたらグノを見つけて、講習を受けてみたら面白かったのでそのまま入りました。
英語に強い塾を探していたらグノを見つけて、講習を受けてみたら面白かったのでそのまま入りました。
鈴木(友):
僕は高1の春に英語で入って、夏から数学、高2から古文と現代文も始めました。僕の学校では、他塾に通っている人たちが宿題を学校でずっとやっていて、その姿を見て「これでは学校生活と両立できない」と思いました。
中学からグノに通っている人たちは宿題の負担はなさそうだったし、振替制度のことも聞いていたので、「学校生活と両立しながら学べそうだ」と思ってグノに決めました。
中学からグノに通っている人たちは宿題の負担はなさそうだったし、振替制度のことも聞いていたので、「学校生活と両立しながら学べそうだ」と思ってグノに決めました。

伊東:
高2の冬に英語で入りました。私の学校にいる数少ない東大志望の人たちは東大専門塾に通っていましたが、東大だけを見て勉強している雰囲気がありました。
私は本当に身になる英語を求めていたので、東大受験に特化した勉強は好きになれませんでした。そこで見つけたのがグノでした。合格体験記を読んで、「通うならこういう塾がいい」と思いました。
私は本当に身になる英語を求めていたので、東大受験に特化した勉強は好きになれませんでした。そこで見つけたのがグノでした。合格体験記を読んで、「通うならこういう塾がいい」と思いました。
鈴木(悠):
「そろそろ英語の塾に通わないと」と思っていた高2の初め頃、部活の先輩がグノのことを楽しそうに話しているのを聞いて、グノが選択肢に入りました。実際に説明会に参加してみて、「この塾なら間違いない」と思って決めました。それ以前に大手予備校の体験授業を受けたこともありましたが、文法中心の解説があまり頭に入ってこなかったんです。
グノの説明会で受けた模擬授業では、思わず引き込まれる面白さを感じました。高3からは国語も受講しました。
グノの説明会で受けた模擬授業では、思わず引き込まれる面白さを感じました。高3からは国語も受講しました。

小田切:
私は高2の夏期講習から英語と数学を習い始めました。国語は高3の講習で受講しました。それまでは塾に通っていなかったので、少し危機感を抱いていましたが、当時は、勉強以外でやりたいことが続いている時期でした。
そんな時、友達の先輩が「グノは宿題が少ないけれど、授業の密度が濃いから、1回1回きちんと受ければ大丈夫」と勧めてくださいました。塾に学校生活を捧げるのはもったいないと思っていて、あまり時間をとられたくなかったので、グノに魅力を感じました。
そんな時、友達の先輩が「グノは宿題が少ないけれど、授業の密度が濃いから、1回1回きちんと受ければ大丈夫」と勧めてくださいました。塾に学校生活を捧げるのはもったいないと思っていて、あまり時間をとられたくなかったので、グノに魅力を感じました。
■学校生活と塾の両立
忙しい日常の中で学校と塾を両立させるために、どんな工夫をしていましたか?
グノは振替制度などで学校生活を応援してもらえるので、高校生活をエンジョイできました
松下:
確かに塾だけで高校生活が終わってしまうのは嫌ですね。
グノはいくつもの講座を受けなければならないわけでもありませんし、宿題も多くありません。グノの授業を受けていれば市販の問題集を解く必要も全くありませんから、学校生活との両立には困りませんでした。
グノはいくつもの講座を受けなければならないわけでもありませんし、宿題も多くありません。グノの授業を受けていれば市販の問題集を解く必要も全くありませんから、学校生活との両立には困りませんでした。
芝:
僕はずっと部活を続けていましたが、グノは土曜日に授業があったので、平日の部活とうまく両立できました。

伊東:
結果的にもし東大に受からなかったとき、「私、何していたんだろう?」という思いを持ちたくなかったので、高3でも文化祭のリーダーなどをいろいろやって、かなり忙しい日々を過ごしていました。最終的には充実した高校3年間で、東大にも合格できたので、本当に良かったと思います。
鈴木(悠):
僕も高2のとき、部活の部長や国際交流、文化祭実行委員など、いろいろやったので、宿題の量が多くなかったのはありがたかったです。グノは振替制度も充実していて本当に助かりました。
鈴木(友):
人を動かしたり動かされたりする学校行事の準備は、将来の仕事につながるので大事だと思います。もちろん勉強も大事ですが、行事と勉強が共倒れになったらいけないので、どちらも続けられたグノには感謝しています。
清水:
宿題の多い塾と学校生活の両立は無理だと思っていたので、「グノで効率良く勉強して、高校生活を楽しもう」と決めていました。
グノなら振替制度などで学校生活を応援してもらえるので、高校をエンジョイする上で良かったです。
グノなら振替制度などで学校生活を応援してもらえるので、高校をエンジョイする上で良かったです。
■グノーブルの評判
学校ではグノーブルに通っていた生徒は多かったのでしょうか?
筑駒では通っている人たちの間で授業の具体的な内容の話がよくかわされていました
鈴木(悠):
麻布ではグノの悪い評判を聞いたことがありませんでした。特にグノの英語の評判は抜群でした。
芝:
僕のクラスには、グノに通っている人がいっぱいいて、みんな「グノの英語はいい」と楽しんで通っていました。
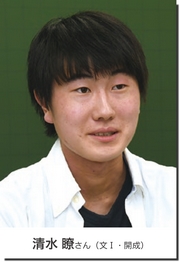
清水:
開成でも、グノ生は全員、満足して通っている印象がありましたし、先生や宿題、テストなどの具体的な話で盛り上がっていました。
グノに通っていない人からは「グノの英語はレベルが高い」と思われていたと思います。
グノに通っていない人からは「グノの英語はレベルが高い」と思われていたと思います。
鈴木(友):
通っている人たちの間で具体的な話がよくかわされていたのは筑駒でも同じです。国語の先生が授業で話してくださったことや、英文のトピックだったり、数学の斬新な授業のことだったり。
小田切:
英語では単語帳の暗記をしないとか、グノではどの科目も他の塾や予備校とはちょっと違ったアプローチで勉強していますから、そういうのが話題になることはありました。
学校の休み時間に数学の宿題を解いていると、他塾の子たちがワーッと集まってきて「何これ?」となって、グノの勉強法のことが話のネタになりました。数学の先生お手製の細かくぎっしり書かれた手書きプリントなどは、他塾の教材とは全然毛色が違ったので、珍しかったんだと思います。
学校の休み時間に数学の宿題を解いていると、他塾の子たちがワーッと集まってきて「何これ?」となって、グノの勉強法のことが話のネタになりました。数学の先生お手製の細かくぎっしり書かれた手書きプリントなどは、他塾の教材とは全然毛色が違ったので、珍しかったんだと思います。
松下:
僕の学校は初めグノ人口が多くなかったので、通っている人たちは「オンリーワンなところに通っている」という誇らしい気持ちを持っていたと思います。
でも評判が良かったので、学年が上がるにつれてグノに入塾する人が段々増えていきました。
でも評判が良かったので、学年が上がるにつれてグノに入塾する人が段々増えていきました。
伊東:
私の学校もグノ人口はとても少なかったです。でも、通っている人の満足度は高くて、「授業が楽しい」「先生が面白い」という話は出ていました。1年前に一橋大に合格した先輩から「グノに入ってから、大嫌いだった英語がどんどん好きになって得点源になった」と聞いていました。
■グノーブルの英語
英語の学習で重要だと思ったことは何でしょうか?
英語の成り立ちを踏まえた解説が私にはとても良かったです。とても興味が持てましたし、自然な文法を習得できました
小田切:
英文を前から英語のまま読むのが好きでした。これができるようになると、リスニングも得点源になりました。
高1のとき、他塾で「これがSで、これがVで、ここを括弧で括って」というアプローチの授業を受けていましたが、複雑な構造の文になると構造を解析することに頭がいっぱいになり、内容が全然わからなくなっていました。こういう英文の読み方があたりまえだと思っていたので、最初グノの英文の読み方には戸惑いもありました。
慣れてしまえばグノの読み方の方が圧倒的に簡単ですし、内容の理解に頭を使えてスラスラ読めるようになったのは大きかったです。
高1のとき、他塾で「これがSで、これがVで、ここを括弧で括って」というアプローチの授業を受けていましたが、複雑な構造の文になると構造を解析することに頭がいっぱいになり、内容が全然わからなくなっていました。こういう英文の読み方があたりまえだと思っていたので、最初グノの英文の読み方には戸惑いもありました。
慣れてしまえばグノの読み方の方が圧倒的に簡単ですし、内容の理解に頭を使えてスラスラ読めるようになったのは大きかったです。
伊東:
グノでは文法もしっかり説明されますが、英語の成り立ちを踏まえた解説なので私にはとても良かったです。非常に興味が持てましたし、自然な文法を習得できました。豊かな表現や微妙なニュアンスの使い分けもできるようになりました。
清水:
先生たちからは、語学の習得にはインプットとアウトプットが大切だとよく言われていました。
グノの読解の授業では興味深い英文をたくさん読めましたし、GSL*も充実していたのでリスニングでのインプットもできました。文法の問題も「ここを聞いてくるのか!」といった発見がいっぱいありました。
アウトプットはプレゼンのように行う音読と、毎週たくさん添削してもらえるライティングです。
インプットとアウトプットの両方を積み重ねて、「英語ではこういう捉え方をする」という感覚とか、英語のリズムや呼吸がわかりました。
* GSL(Gnoble Sound Laboratory):中1から高3までの6学年すべてに毎週用意されているオリジナルの英語音声教材。
グノの読解の授業では興味深い英文をたくさん読めましたし、GSL*も充実していたのでリスニングでのインプットもできました。文法の問題も「ここを聞いてくるのか!」といった発見がいっぱいありました。
アウトプットはプレゼンのように行う音読と、毎週たくさん添削してもらえるライティングです。
インプットとアウトプットの両方を積み重ねて、「英語ではこういう捉え方をする」という感覚とか、英語のリズムや呼吸がわかりました。
* GSL(Gnoble Sound Laboratory):中1から高3までの6学年すべてに毎週用意されているオリジナルの英語音声教材。
受験では数多くの英単語を暗記しなければならないと思いますが、どのように乗り越えたのでしょうか?
グノに入ってからの単語の覚え方は、広がりを持って単語の意味を思い出せる強みがありました

鈴木(友):
僕が一番いいなと思ったのは、英単語の意味を覚えるときに日本語との対応で覚えるのではないということです。単語帳を使って日本語との対応で覚えていると、イメージの広がりがなくて、固定的な日本語でしか意味がとれなくなります。
グノだと、接頭辞や接尾辞、語根のことをちゃんと教えてもらえるし、時には先生が黒板に英単語のイメージを絵に描いてくれたり、体を使って動作で表現してくださります。
例えば、per という接頭辞は「ずっと」という意味で、spect という語根は「見る」という意味だから、perspective は絵画の文脈なら「遠近法」という意味になるし、perspective on life というような使われ方なら「人生観」になります。
このように覚えられると、英文の中で単語が生き生きと見えてきます。語根や接頭辞などがヒントになって意味を推測できるようにもなるし、文脈から和訳のときの日本語を工夫できるようにもなります。
グノだと、接頭辞や接尾辞、語根のことをちゃんと教えてもらえるし、時には先生が黒板に英単語のイメージを絵に描いてくれたり、体を使って動作で表現してくださります。
例えば、per という接頭辞は「ずっと」という意味で、spect という語根は「見る」という意味だから、perspective は絵画の文脈なら「遠近法」という意味になるし、perspective on life というような使われ方なら「人生観」になります。
このように覚えられると、英文の中で単語が生き生きと見えてきます。語根や接頭辞などがヒントになって意味を推測できるようにもなるし、文脈から和訳のときの日本語を工夫できるようにもなります。
清水:
僕は単語帳を一周暗記したことがありますが、どうしても英単語と日本語を一対一で覚えることになってしまい、ひとつの意味を忘れたらそれで終わりになりがちでした。グノに入ってからの単語の覚え方は、広がりを持って単語の意味を思い出せる強みがありました。
小田切:
単語帳を使わなくても、グノの授業できちんと理解した単語は英文の中で自然に覚えられました。単語帳にかける時間がなくなった分、他のことに時間をかけられて良かったです。
鈴木(悠):
僕も単語帳は全然使いませんでした。それでも英文の中で初めて見る単語も、文脈やその単語の成り立ちから意味を推測できるようになりました。単語帳から始めるのとは違う利点がグノのやり方にはありました。
鈴木(友):
高2のときに、語源ノートの作り方を教えてもらいました。それを実際に作り始めてから、より覚えやすくなりました。
語源ノートは、語根を真ん中に書いて、そこから線をのばして関連する英単語をどんどん書いていくメモノートみたいなものです。
語源ノートは、語根を真ん中に書いて、そこから線をのばして関連する英単語をどんどん書いていくメモノートみたいなものです。
英語の授業はどんな雰囲気だったのか教えてください
先生は英文を深く理解した上で説明してくれるので、解説を聞いていると英語的な発想の仕方が見えてきて、感動することもありました
松下:
グノの英語は、受験英語を教えるというよりも、言語としての英語を教えるという点が特徴的でした。
授業で提供される英文の中にはただ難しいのではなくて、英語的な脳みそになっていないと中核までたどり着けない英文もよくありました。先生はその英文を深く理解した上で説明してくださるので、解説を聞いていると、英語的な発想の仕方がわかってきて、ちょっと感動することもありました。
授業ではいろいろな分野の英文や、最新の時事的な英文も扱われました。新しい知識も増えて知的な楽しみを満喫できました。英文の背景に関しては先生がいつも楽しそうに解説してくださっていたので、授業で扱った英文は楽しく復習できました。
授業で提供される英文の中にはただ難しいのではなくて、英語的な脳みそになっていないと中核までたどり着けない英文もよくありました。先生はその英文を深く理解した上で説明してくださるので、解説を聞いていると、英語的な発想の仕方がわかってきて、ちょっと感動することもありました。
授業ではいろいろな分野の英文や、最新の時事的な英文も扱われました。新しい知識も増えて知的な楽しみを満喫できました。英文の背景に関しては先生がいつも楽しそうに解説してくださっていたので、授業で扱った英文は楽しく復習できました。

鈴木(悠):
授業で扱う英文自体がとても面白いんですよ。英語という科目だけでなく、英文の背景にある哲学のようなものも理解できるのが楽しかったです。
グノの英語の授業で学んだことは、受験での得点力アップにつながるのはもちろんですが、現代文の解釈に役立つものもありました。自分の教養の厚みが少し増したように思います。
グノの英語の授業で学んだことは、受験での得点力アップにつながるのはもちろんですが、現代文の解釈に役立つものもありました。自分の教養の厚みが少し増したように思います。
清水:
授業の雰囲気に適度の緊張感があるのもグノの特徴です。
授業は先生と生徒のやり取りで進んでいくので集中がとぎれません。自信のないところに限って自分に回ってきてつらいこともありましたが(笑)、それはそれで楽しいものでした。
答えられなかった内容は悔しいのと同時に忘れがたくなるし、指名される授業だからこそ、わからない単語があっても、その意味を文脈から推測しようと必死になるので、考える習慣がつきました。
授業は先生と生徒のやり取りで進んでいくので集中がとぎれません。自信のないところに限って自分に回ってきてつらいこともありましたが(笑)、それはそれで楽しいものでした。
答えられなかった内容は悔しいのと同時に忘れがたくなるし、指名される授業だからこそ、わからない単語があっても、その意味を文脈から推測しようと必死になるので、考える習慣がつきました。
芝:
緊張感といえば、授業の中で演習したことをすぐに添削して採点してもらえるのは本当に良かったと思います。毎週「今週もがんばるぞ」と思って授業に臨めましたし、できなくても「またがんばろう」というモチベーションにつながりました。
小田切:
授業であてられても大丈夫なように演習時間ギリギリまで解答の根拠を探すから、模試や入試本番でも広い視野で考える練習になりました。
授業内演習では、点数の分布を先生が黒板に書いてくださるので、自分の位置が大体わかります。
グノには本当に優秀な人が多いので、それを見ながら「今日はがんばれたな」などと思えたのが良かったです。
授業内演習では、点数の分布を先生が黒板に書いてくださるので、自分の位置が大体わかります。
グノには本当に優秀な人が多いので、それを見ながら「今日はがんばれたな」などと思えたのが良かったです。
鈴木(悠):
演習のときには隣の人が解いていくスピードもわかるので、その緊迫感を結構楽しんでいました。この経験はとても大きくて、入試本番でも生きたと思っています。
鈴木(友):
確かに、授業内演習を続けていると、模試への抵抗感がなくなるし、東大入試本番でも「時間がきつい」と思いませんでした。
東大の英語は、120 分で読んで書いて聞いてとたくさんこなしますが、グノで何十回も授業内演習を重ねていたら楽になります。
東大の英語は、120 分で読んで書いて聞いてとたくさんこなしますが、グノで何十回も授業内演習を重ねていたら楽になります。

松下:
演習問題のレベル自体がかなり高かったと思います。でも、直後に解説があるので、気持ちが新鮮なまま自分の解いた問題と向き合えました。自分の中で良かった部分と悪かった部分が浮き彫りになって、毎週印象に残る授業でした。
伊東:
私は東大入試本番で世界史を大失敗した自覚があって、英語と国語に救われました。英語の場合、授業内で添削を受けた回数の積み重ねが表れたのだと思います。
先生方の添削は単なる丸つけではありません。例えば英作文の場合だと、文法や語法のミスも指摘していただけますが、「こういうところをまとめられていて良い」とか「こういうところを言及すると良い」とか、内容構成についてのコメントもいただけました。
要約の場合だと、筆者の主張を的確に把握し、その主張をするのに筆者がどのように英文全体を組み立てているか、それを見抜く目を養う指導を厳しくしていただけました。これらを繰り返し鍛えられたおかげで本番での成功につながりました。
先生方の添削は単なる丸つけではありません。例えば英作文の場合だと、文法や語法のミスも指摘していただけますが、「こういうところをまとめられていて良い」とか「こういうところを言及すると良い」とか、内容構成についてのコメントもいただけました。
要約の場合だと、筆者の主張を的確に把握し、その主張をするのに筆者がどのように英文全体を組み立てているか、それを見抜く目を養う指導を厳しくしていただけました。これらを繰り返し鍛えられたおかげで本番での成功につながりました。
■英語の力が伸びた時期
普段の努力が成績の向上として実感できたのはいつ頃からだったのでしょうか?
グノに入ってから英文にたくさん触れるようになって1か月もしたら、新しい英文を読んでもスッと内容が頭の中に入ってくるようになりました
小田切:
「あっ、変わった」と思ったのは高3の夏です。
夏休みは時間をとれるから、朝の目が覚めたときと夜の寝る前に、普段よりも長く音読をしました。その結果、サッカーの英語実況が自然に聞き取れるようになっていたんです。
夏休みは時間をとれるから、朝の目が覚めたときと夜の寝る前に、普段よりも長く音読をしました。その結果、サッカーの英語実況が自然に聞き取れるようになっていたんです。
伊東:
私も音読は毎日やっていました。GSL を聞いて、英文を覚えるくらいまで読み込みました。秋頃には英語を読むのが速くなったことを実感できましたし、直前期までどんどん速読力は伸びました。
何回も音読して理解の深まった英文が増えるにつれて、初見の英文でも速く読めるようになっていました。
何回も音読して理解の深まった英文が増えるにつれて、初見の英文でも速く読めるようになっていました。
松下:
僕はまずグノに入った直後に伸びていると実感しました。このときは英文法を必死に勉強していたので、いい加減だった英文法の土台が整ったからだと思います。
そのあとは高3の2学期の秋にも伸びを実感しました。グノでたくさん読んできた英文の蓄積のおかげだと思います。
そのあとは高3の2学期の秋にも伸びを実感しました。グノでたくさん読んできた英文の蓄積のおかげだと思います。
清水:
グノに入塾後、英文にたくさん触れるようになって1か月もしたら、新しい英文を読んでもスッと内容が頭の中に入ってくるようになりました。
高3の夏以降、慢心していたせいで読み込みをしていなかった時期があったのですが、そうしたら英語の成績が落ち始めてしまいました。
やはり毎日コツコツ英語に触れることは大切です。電車の行き帰りを使って常にグノで扱った英文の読み込みをしているうちに、また英語が頭に入ってくるようになりましたし、読み込みのおかげで語彙力もついて、テストでも点数をとりやすくなりました。
高3の夏以降、慢心していたせいで読み込みをしていなかった時期があったのですが、そうしたら英語の成績が落ち始めてしまいました。
やはり毎日コツコツ英語に触れることは大切です。電車の行き帰りを使って常にグノで扱った英文の読み込みをしているうちに、また英語が頭に入ってくるようになりましたし、読み込みのおかげで語彙力もついて、テストでも点数をとりやすくなりました。
鈴木(悠):
僕も音読を勧められていたにもかかわらず、高3の初めの頃は、社会科目の勉強もあって、音読をサボっていました。おかげで夏の全国模試では、英語が全部解き終わりませんでした。
「これはまずい」と思ってその日から集中的に音読を始めました。先生のアドバイスを参考にして、プレゼンテーションをするように、内容を英語で伝える意識を持った音読です。
夏の模試では英語の偏差値が50 ちょっとしかなかったのですが、秋の模試では偏差値が70までアップして、「本当に伸びた」とうれしくなりました。入試本番でも15 分くらい時間が余りました。
「これはまずい」と思ってその日から集中的に音読を始めました。先生のアドバイスを参考にして、プレゼンテーションをするように、内容を英語で伝える意識を持った音読です。
夏の模試では英語の偏差値が50 ちょっとしかなかったのですが、秋の模試では偏差値が70までアップして、「本当に伸びた」とうれしくなりました。入試本番でも15 分くらい時間が余りました。
鈴木(友):
僕は急激に伸びたのではなく、高1から高3まで少しずつ継続的に伸びていたのだと思います。
高3になってから高1の頃のプリントを見直していたら、当時は「難しい」と思っていた英文もスラスラ読めるようになっていました。この間にメインで取り組んでいたことは、やはりGSL を利用しての音読です。
高3になってから高1の頃のプリントを見直していたら、当時は「難しい」と思っていた英文もスラスラ読めるようになっていました。この間にメインで取り組んでいたことは、やはりGSL を利用しての音読です。
芝:
僕の場合はリスニングがずっと苦手でした。
高3の夏の東大模試のあと、グノの先生に相談し、いただいたアドバイスに従ってGSL を活用したシャドーイングを始めました。そのうちにリスニング力が安定してきて、秋の模試でリスニングが2倍の得点になってびっくりしました。
高3の夏の東大模試のあと、グノの先生に相談し、いただいたアドバイスに従ってGSL を活用したシャドーイングを始めました。そのうちにリスニング力が安定してきて、秋の模試でリスニングが2倍の得点になってびっくりしました。
■グノーブルの数学
文系の皆さんにとって数学の授業はどうだったでしょうか?
グノで数学が劇的に変わらなければ、そもそも国立大学を受けていなかったかもしれません
小田切:
私は高2で英語と一緒に数学も受講しました。
中学受験の頃から算数が嫌いで、高2までの4年間数学をサボっていました。だから、本当に数学ができませんでした。問題の解き方がわからないし、勉強の仕方もわかりませんでした。ほとんどの人は教科書の問題を解いていくとわかるようになるのでしょうが、私は教科書の問題がそもそも全く解けなかったんです。
でも、グノに通ったら、「数学が一番伸びた」と言ってもいいくらい伸びました。高3の秋の模試で全国偏差値が65 を超えましたし、数学が安定したから他の科目にも集中できました。グノで数学が劇的に変わらなければ、そもそも国立大学を受けていなかったかもしれません。
グノの授業で「こういうふうにやればいいんだよ」「この考え方を使えば解けるよ」ということを、感覚ではなく言葉で論理的に教えてもらえたので、体系立って積み重ねることができて、自信とやる気が出てきました。
セルフチェックシートも力になりました。シートを埋めるのは大変でしたが、先生も私以上にコメントを書いてくださるので、それを励みにして、「ちゃんとやろう」と自分を奮い立たせました。
シートを書き続けたおかげで、正答する見込みがある失敗と全く見当違いの失敗とを区別できるようになりました。何よりも最後の方は数学がとても好きになって、本番でも得点源になりました。
中学受験の頃から算数が嫌いで、高2までの4年間数学をサボっていました。だから、本当に数学ができませんでした。問題の解き方がわからないし、勉強の仕方もわかりませんでした。ほとんどの人は教科書の問題を解いていくとわかるようになるのでしょうが、私は教科書の問題がそもそも全く解けなかったんです。
でも、グノに通ったら、「数学が一番伸びた」と言ってもいいくらい伸びました。高3の秋の模試で全国偏差値が65 を超えましたし、数学が安定したから他の科目にも集中できました。グノで数学が劇的に変わらなければ、そもそも国立大学を受けていなかったかもしれません。
グノの授業で「こういうふうにやればいいんだよ」「この考え方を使えば解けるよ」ということを、感覚ではなく言葉で論理的に教えてもらえたので、体系立って積み重ねることができて、自信とやる気が出てきました。
セルフチェックシートも力になりました。シートを埋めるのは大変でしたが、先生も私以上にコメントを書いてくださるので、それを励みにして、「ちゃんとやろう」と自分を奮い立たせました。
シートを書き続けたおかげで、正答する見込みがある失敗と全く見当違いの失敗とを区別できるようになりました。何よりも最後の方は数学がとても好きになって、本番でも得点源になりました。
鈴木(友):
グノの先生は「野生」と「整理」という言葉をよく使っていました。数学が大好きで得意な人が自分のやりたいようにやって正解を出すのは「野生」です。「こういう問題はこうしたら解ける」と自覚的なやり方が「整理」です。
僕は数学が嫌いではなかったので、調子がいいときは好きにやっても解けました。でも、好きにやっているとつまずくこともよくありました。僕のような受験生には、「整理」が大切だったんです。
グノの授業を受けて宿題をこなしていくうちに、「整理」の方法が身について、「野生」で不安定だった数学が安定するようになりました。
僕は数学が嫌いではなかったので、調子がいいときは好きにやっても解けました。でも、好きにやっているとつまずくこともよくありました。僕のような受験生には、「整理」が大切だったんです。
グノの授業を受けて宿題をこなしていくうちに、「整理」の方法が身について、「野生」で不安定だった数学が安定するようになりました。
松下:
グノの授業は、しっかりついていけば、誰でも数学ができるようになる授業形態です。しかも、教科の枠にとらわれず、他のあらゆる面で活かせるメソッドを学べます。
例えば、「メタコグニション」という言葉があります。これは、“自分の認識の仕方を認識すること”を意味し、それができるといろいろな面で役立ちます。
グノのセルフチェックシートでそのメタコグニションが身につきました。シートを書き続けていると「自分がどういう傾向を持っていて、どういうところが苦手なのか?」がわかるようになります。そこに対する解決策を自分なりに考案して実験し、ダメならダメで新しい解決策を考えて、うまくいったらそれを知識として自分の中に蓄えておく、というトライ・アンド・エラーもできるようになりました。
妥当性を持った一般則でも、実際にやってみるとうまくいかないことがあります。そんなときは「どうすればいいのか?」を、セルフチェックシートを書きながら深く考えることになりました。この時間にも大きな意味がありました。
例えば、「メタコグニション」という言葉があります。これは、“自分の認識の仕方を認識すること”を意味し、それができるといろいろな面で役立ちます。
グノのセルフチェックシートでそのメタコグニションが身につきました。シートを書き続けていると「自分がどういう傾向を持っていて、どういうところが苦手なのか?」がわかるようになります。そこに対する解決策を自分なりに考案して実験し、ダメならダメで新しい解決策を考えて、うまくいったらそれを知識として自分の中に蓄えておく、というトライ・アンド・エラーもできるようになりました。
妥当性を持った一般則でも、実際にやってみるとうまくいかないことがあります。そんなときは「どうすればいいのか?」を、セルフチェックシートを書きながら深く考えることになりました。この時間にも大きな意味がありました。
■グノーブルの国語
国語の授業はどうだったでしょうか?
学校にグノの国語に感銘を受けていた人たちがいたので僕も受けてみたのですが、みんなの印象通りでした
鈴木(悠):
高3で受講した東大国語のおかげで、国語の力はかなり伸びて、本番も十分な手応えを感じられました。
堅苦しくて抽象度の高い文章でも、先生が身近で面白い具体例に置き換えて解説してくださったので、本文に対する理解が深まりました。抽象的な事柄は具体的な例を思い浮かべてみると見通しが良くなるという思考法を学べました。
他の予備校だと、ひとつの解答例を挙げて「あなたの解答はここが間違っている」という添削法になりがちです。一方、グノでは、生徒の書いた答案に少しずつ足し引きしていって正しい解答に導いていくという添削法で、僕も納得できる添削を受けられました。
堅苦しくて抽象度の高い文章でも、先生が身近で面白い具体例に置き換えて解説してくださったので、本文に対する理解が深まりました。抽象的な事柄は具体的な例を思い浮かべてみると見通しが良くなるという思考法を学べました。
他の予備校だと、ひとつの解答例を挙げて「あなたの解答はここが間違っている」という添削法になりがちです。一方、グノでは、生徒の書いた答案に少しずつ足し引きしていって正しい解答に導いていくという添削法で、僕も納得できる添削を受けられました。
鈴木(友):
僕は高2からグノの国語を受けていました。
先生は、抽象的な難しいことや一回文章を読んだだけではわからないことを、身近な例を使って具体的に解説してくださいます。そこには深い洞察や教養もあって、授業を受けているうちに、それが自分の一部にもなっていきました。最終的には「読んでわからない」となる文章はほぼなくなりました。
古文・漢文も丁寧に文法を教えていただけて成績が伸びました。古文単語の覚え方も、その成り立ちを踏まえるというグノの英単語の覚え方と似ていて、現代語に関連させたり、漢字に置き換えたりして意味を推測するなど、楽しく本格的に勉強できました。
先生は、抽象的な難しいことや一回文章を読んだだけではわからないことを、身近な例を使って具体的に解説してくださいます。そこには深い洞察や教養もあって、授業を受けているうちに、それが自分の一部にもなっていきました。最終的には「読んでわからない」となる文章はほぼなくなりました。
古文・漢文も丁寧に文法を教えていただけて成績が伸びました。古文単語の覚え方も、その成り立ちを踏まえるというグノの英単語の覚え方と似ていて、現代語に関連させたり、漢字に置き換えたりして意味を推測するなど、楽しく本格的に勉強できました。
伊東:
私はもともと国語がかなり得意でした。古文・漢文は高2で自分なりに完成していたので、「塾に行かなくていいかな」と思っていました。でも、高3の春にグノの授業を受けたら、惚れてしまったんです(笑)。結局1年間ずっと受講しました。
授業では毎回、腹筋が痛くなるほど笑って、いつの間にか力が伸びていく感覚でした。解説は、全然関係ないような先生の面白い昔話から始まって、話が進んでいくうちに設問のヒントにつながっていくんです。ちょっとした日本史のクイズなども多くて、それに答えるのが楽しみでした。
添削は、一人ひとりの答案に対して的確に付け加えたり削ったりしてくださって、本当に丁寧でした。解答例も私たちの手が届くような表現を提示していただけたので、とても参考になりました。
先生が本文に書かれている長い比喩をどう簡潔にまとめるかといったテクニックを教えてくださったおかげで、東大模試でも良い点をとれました。
授業では毎回、腹筋が痛くなるほど笑って、いつの間にか力が伸びていく感覚でした。解説は、全然関係ないような先生の面白い昔話から始まって、話が進んでいくうちに設問のヒントにつながっていくんです。ちょっとした日本史のクイズなども多くて、それに答えるのが楽しみでした。
添削は、一人ひとりの答案に対して的確に付け加えたり削ったりしてくださって、本当に丁寧でした。解答例も私たちの手が届くような表現を提示していただけたので、とても参考になりました。
先生が本文に書かれている長い比喩をどう簡潔にまとめるかといったテクニックを教えてくださったおかげで、東大模試でも良い点をとれました。
小田切:
私も国語は昔から好きでしたが、高3の春期・夏期・冬期・直前の講習は受講しました。以前は、東大で出題されるエッセイふうの文章の場合、何が問われているかわからずに面食らってしまっていたのですが、グノの授業を何回か受けているうちにどんどんできるようになりました。
何より、現代文と古文と漢文とを同じ先生が教えてくださるので、自分のことをトータルにわかっていただける安心感がありました。「古文と漢文は良い感じだから、現代文を安定させようね」とアドバイスをいただき、本当にありがたかったです。
何より、現代文と古文と漢文とを同じ先生が教えてくださるので、自分のことをトータルにわかっていただける安心感がありました。「古文と漢文は良い感じだから、現代文を安定させようね」とアドバイスをいただき、本当にありがたかったです。
松下:
僕も新高2の春期から直前まで、講習だけ受講しました。学校にはグノの国語に感銘を受けた人たちが多くいて、それで僕も受けてみたのですが、みんなの言っていた通りでした。
授業は東大入試を見据えた内容で、テキストの文章自体も先生の話も面白いし、解答解説も十分納得できるものでした。
宿題や見直しは、楽しい授業を思い出しながら取り組めて、自宅学習も楽しくなりました。
僕はグノ以外にも通信教育を受けていて先生はそちらの教材のやり方までアドバイスしてくださいました。
様々なサポートのおかげで不得意な現代文の成績が大きく伸びました。
授業は東大入試を見据えた内容で、テキストの文章自体も先生の話も面白いし、解答解説も十分納得できるものでした。
宿題や見直しは、楽しい授業を思い出しながら取り組めて、自宅学習も楽しくなりました。
僕はグノ以外にも通信教育を受けていて先生はそちらの教材のやり方までアドバイスしてくださいました。
様々なサポートのおかげで不得意な現代文の成績が大きく伸びました。
■グノーブルの先生
先生方はどのように皆さんの勉強と関わってくれましたか?
一方的に授業をして、質問も気軽に行ける感じではない他塾の先生とはまるで違いました
鈴木(悠):
授業でわからないことがあったらグノの場合、気軽に質問できます。
例えば、僕が夏模試でひどい成績だったとき、すがる思いで国語の先生に相談にいったんです。そうしたら、先生は社会科目のことも含めて話してくださって、先生ご自身の経験に基づいた的確なアドバイスをくださいました。勉強計画を立てる上での指針を示していただけたので本当に助かりました。
一方通行の授業で、質問も気軽にいける雰囲気ではない他塾とはまるで違いました。
例えば、僕が夏模試でひどい成績だったとき、すがる思いで国語の先生に相談にいったんです。そうしたら、先生は社会科目のことも含めて話してくださって、先生ご自身の経験に基づいた的確なアドバイスをくださいました。勉強計画を立てる上での指針を示していただけたので本当に助かりました。
一方通行の授業で、質問も気軽にいける雰囲気ではない他塾とはまるで違いました。
小田切:
グノの先生は一人ひとりとちゃんと向き合ってくださいました。その姿に私は感動したことがあります。
新高3の春に電話である先生にちょっとした相談をさせていただいたことがありました。そのことを先生はずっと覚えていて、合格後の報告会のとき、「あのときの電話では……」と先生から話してくださったんです。「私も忘れていたことなのに!」と本当に感動しました。
グノの先生は全員親切です。一見近づきにくくて最初は質問にいくのをためらっていた数学の先生も、いざ質問にいってみると、とても優しく対応してくださり感動しました。
新高3の春に電話である先生にちょっとした相談をさせていただいたことがありました。そのことを先生はずっと覚えていて、合格後の報告会のとき、「あのときの電話では……」と先生から話してくださったんです。「私も忘れていたことなのに!」と本当に感動しました。
グノの先生は全員親切です。一見近づきにくくて最初は質問にいくのをためらっていた数学の先生も、いざ質問にいってみると、とても優しく対応してくださり感動しました。
芝:
質問といえば、グノではメールでも質問できます。すぐに返信が来て驚いたことも何度もあります。たとえ夜遅くても、先生は生徒のためにメールを返信してくださるんです。
「グノの先生の生徒思いはすごい」と思っていました。
「グノの先生の生徒思いはすごい」と思っていました。
松下:
生徒をちゃんと見ていてくださるのは心強いです。僕は高3の夏前に英語のクラス分けテストで失敗してクラスが落ちてしまいました。そのときはどん底でしたが、先生たちに声をかけていただいて救われました。
国語は受験終盤の過去問添削でびっしり赤入れをしていただきましたし、数学も先生と双方向のコミュニケーションがいつもとれていたので、勉強に前向きに取り組めました。それだけでなく学校生活の相談にも一緒に考えてくださったことがありました。
国語は受験終盤の過去問添削でびっしり赤入れをしていただきましたし、数学も先生と双方向のコミュニケーションがいつもとれていたので、勉強に前向きに取り組めました。それだけでなく学校生活の相談にも一緒に考えてくださったことがありました。
鈴木(友):
松下君と同じく、僕も英語のクラス分けテストで落ちたことがあります。だから、結果としていろいろな先生に英語を習いました。数学や国語も含めて何人もの先生にお世話になりました。
グノの先生は皆さん個性的で楽しい方なのですが、面倒見がいいという点では一緒です。親身なアドバイスをくださる一方で、勉強法などは生徒の自由を尊重してくださいます。文化祭のときは準備の進捗を聞いてくださったりと、学校行事への理解があるのも本当にありがたかったです。
グノの先生は皆さん個性的で楽しい方なのですが、面倒見がいいという点では一緒です。親身なアドバイスをくださる一方で、勉強法などは生徒の自由を尊重してくださいます。文化祭のときは準備の進捗を聞いてくださったりと、学校行事への理解があるのも本当にありがたかったです。
伊東:
先生は生徒一人ひとりをよく見ていらっしゃいます。添削もとても丁寧で、細かいところまでコメントした答案を返してくださいました。
何が得意で何が苦手なのかということも的確に見抜いていらっしゃる先生から「あなたはここはこうだから大丈夫」と励ましてもらえると、根拠のない「大丈夫」からは得られない自信につながります。
何が得意で何が苦手なのかということも的確に見抜いていらっしゃる先生から「あなたはここはこうだから大丈夫」と励ましてもらえると、根拠のない「大丈夫」からは得られない自信につながります。
清水:
先生は親身なだけでなく、様々なことにおいてとてもレベルが高くて驚かされました。
英語の先生は毎週新しい英文を何本も用意して授業に持ってきてくださるし、その英文の背景にまで精通している解説を毎回受けられました。とても熱い気持ちを持っていらっしゃるのも伝わってきて、毎週「すごい」と思って授業を受けていました。
英語の先生は毎週新しい英文を何本も用意して授業に持ってきてくださるし、その英文の背景にまで精通している解説を毎回受けられました。とても熱い気持ちを持っていらっしゃるのも伝わってきて、毎週「すごい」と思って授業を受けていました。
■グノーブルの環境
学習環境の面でグノーブルの良いところを教えてください
教室は授業が始まる前も静かで、勉強する雰囲気が整っていました
鈴木(悠):
高2のときは学校のことで忙しかったので振替制度に助けられました。高3になってからも、他とのスケジュールの兼ね合いで季節講習の日程を組むのが大変でしたが、グノは講習を2日ごとに分けて受講できるので良心的でした。
芝:
僕も講習の日程を組むのが大変でしたが、グノは融通が利いたので助かりました。
それから、教室は授業が始まる前も静かで、勉強する雰囲気が整っていました。他塾だと喋っている人たちが多くて、勉強する環境としてはいまいちでした。
それから、教室は授業が始まる前も静かで、勉強する雰囲気が整っていました。他塾だと喋っている人たちが多くて、勉強する環境としてはいまいちでした。
清水:
勉強する環境といえば、教室がきれいで良かったです。
あと、僕も振替制度のおかげで運動会がとても忙しい時期でも、運動会前日の1日以外は休まずにすみました。
あと、僕も振替制度のおかげで運動会がとても忙しい時期でも、運動会前日の1日以外は休まずにすみました。
小田切:
グノの柔軟さには私も助けられました。文化祭前に学校に残らなければいけないときも遅い時間帯の授業に振替ができて大丈夫でした。
鈴木(友):
振替のために電話をしたときも、受付の方がとても優しく対応してくださったので助かりました。
松下:
添削の受け取りで何度も受付のお世話になりましたが、受付の方は本当に丁寧でした。
伊東:
受付の方だけでなく、警備の方も親切でした。教室は少し狭かったのですが、逆に先生との距離の近さを感じられて、一体感を味わえました。
■後輩へのアドバイス
これから受験する後輩に向けて一言お願いします
生きた英語を学ぶ努力をしていれば、いつの間にか東大入試でも自分が思っている以上のところにたどり着けます
鈴木(友):
大学受験はこれまでの受験と違って文系理系や志望大学、科目の選択、勉強法など、決めなければいけないことがたくさんあって悩みます。だからといって、学校やネットで情報集めに躍起になるよりも、グノの先生に相談してアドバイスを受けながら真面目に勉強に向かう方が賢明です。グノと自分を信じて勉強するのが大事です。
小田切:
先生に相談したら親身に現実的なアドバイスをくださいます。勉強そのものでなくても、勉強法や学校の悩みなど、何でもいいから怖がらずにどんどん質問にいきましょう。
清水:
グノの先生たちは、普段から僕たちのことをよく見ていてくださるので、先生のところにまず相談にいってみるのはおすすめです。
でも、その一方で、勉強するのは自分たちなので、やるべきことはしっかりやることが大切です。例えば英語の音読をしっかりやるとか。
でも、その一方で、勉強するのは自分たちなので、やるべきことはしっかりやることが大切です。例えば英語の音読をしっかりやるとか。
鈴木(悠):
僕も英語は音読に尽きると思います。慣れていないうちは、音読がつらくて大変です。でも、続けていくうちにどんどん楽しくなります。
効果が出るまで3、4か月はかかりますが、こらえて続けていれば、ある時期から成績や結果がついてきます。グノの先生を信じて音読してほしいです。
効果が出るまで3、4か月はかかりますが、こらえて続けていれば、ある時期から成績や結果がついてきます。グノの先生を信じて音読してほしいです。
芝:
音読には恥ずかしさが伴うかもしれません。僕も斜に構えて「音読はちょっと……」という時期がありました。でも、最後には先生のおっしゃることを信じて、恥ずかしさを捨てて、人形相手に音読やシャドーイングをすることで、ちゃんと結果につながりました。
松下:
大学受験は最終的には自分の受験です。だから、試行錯誤を最後まで続けなければなりません。そういう過程を手助けしてくれるのがグノです。先生が後押しをしてくださるので、好きなだけ失敗できる塾だと思います。やってみるから、失敗できるのだし、失敗した分、成長につながりますからグノの環境を存分に活用してください。
伊東:
私は、大学受験のために通っていたと思えないほど、生きた知識を学べた充実の一年間でした。生きた英語を学ぶ努力をしていれば、いつの間にか東大入試でも自分が思っている以上のところにたどり着けます*。グノを信頼して真面目に取り組めば大丈夫です。
*伊東さんはTLPの認定を受けました。TLP(Trilingual Program):「グローバルリーダー育成プログラム」の一環で、東大の英語入試で上位1割程度に入った学生に認められています。
*伊東さんはTLPの認定を受けました。TLP(Trilingual Program):「グローバルリーダー育成プログラム」の一環で、東大の英語入試で上位1割程度に入った学生に認められています。